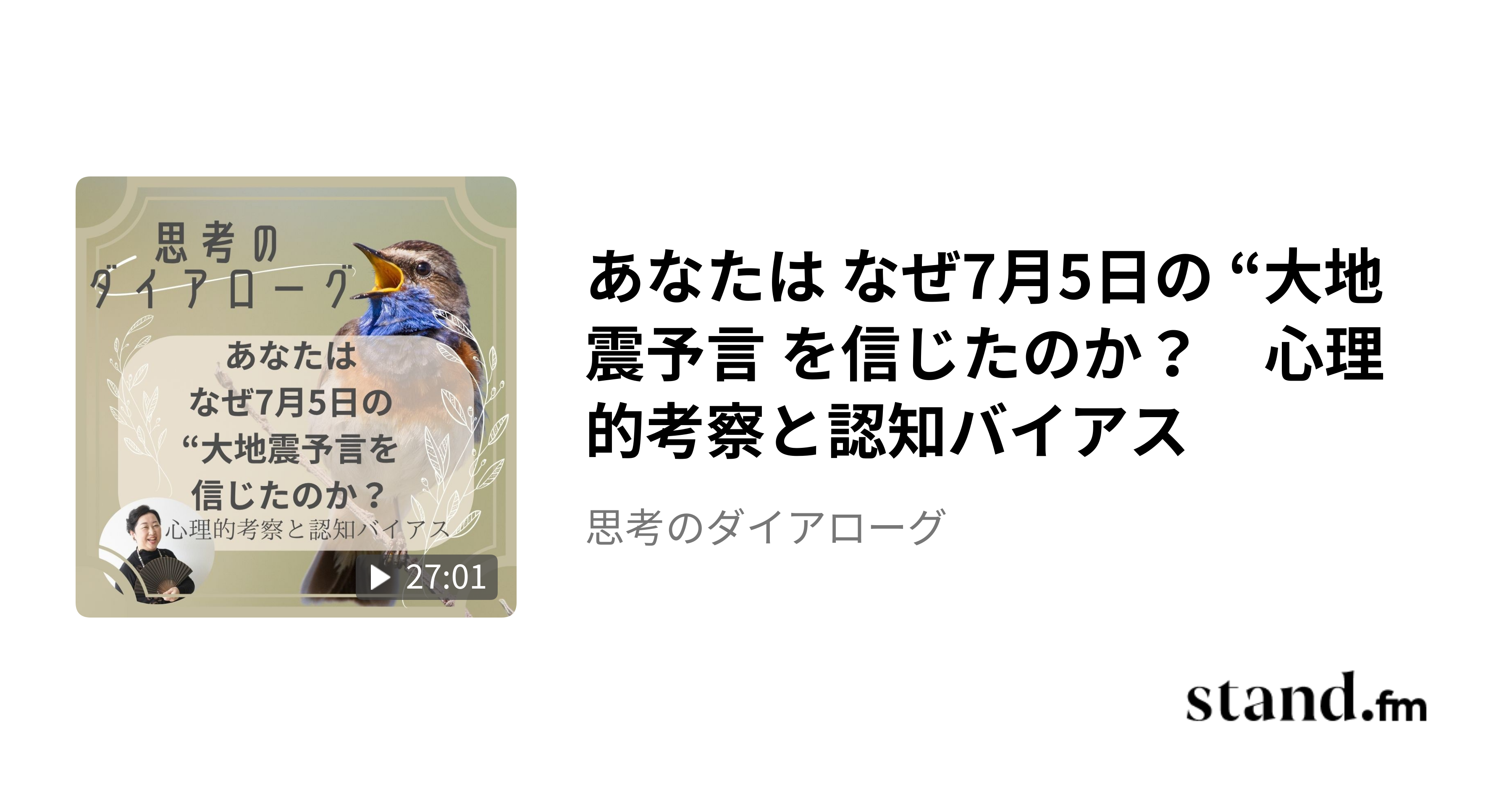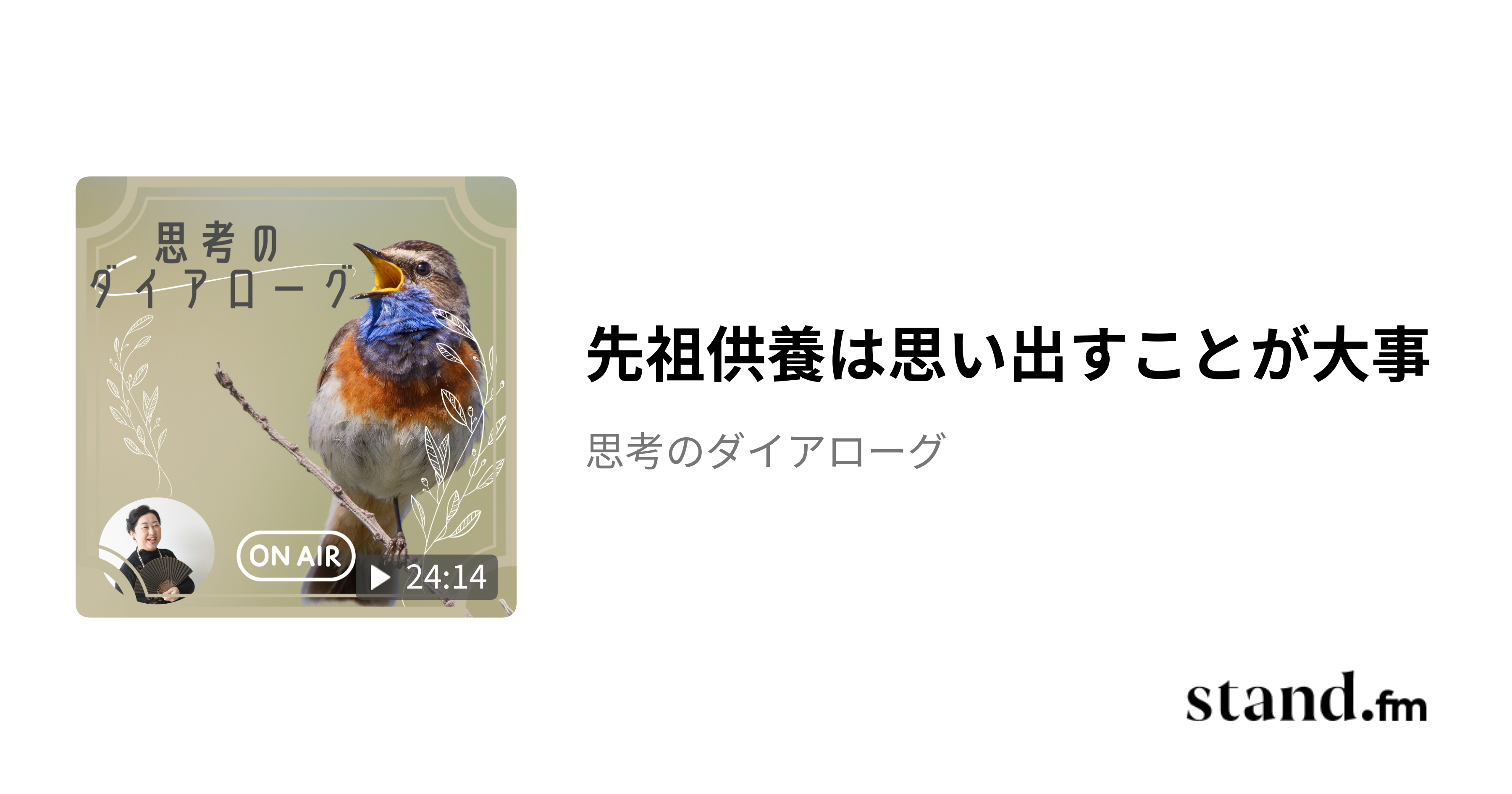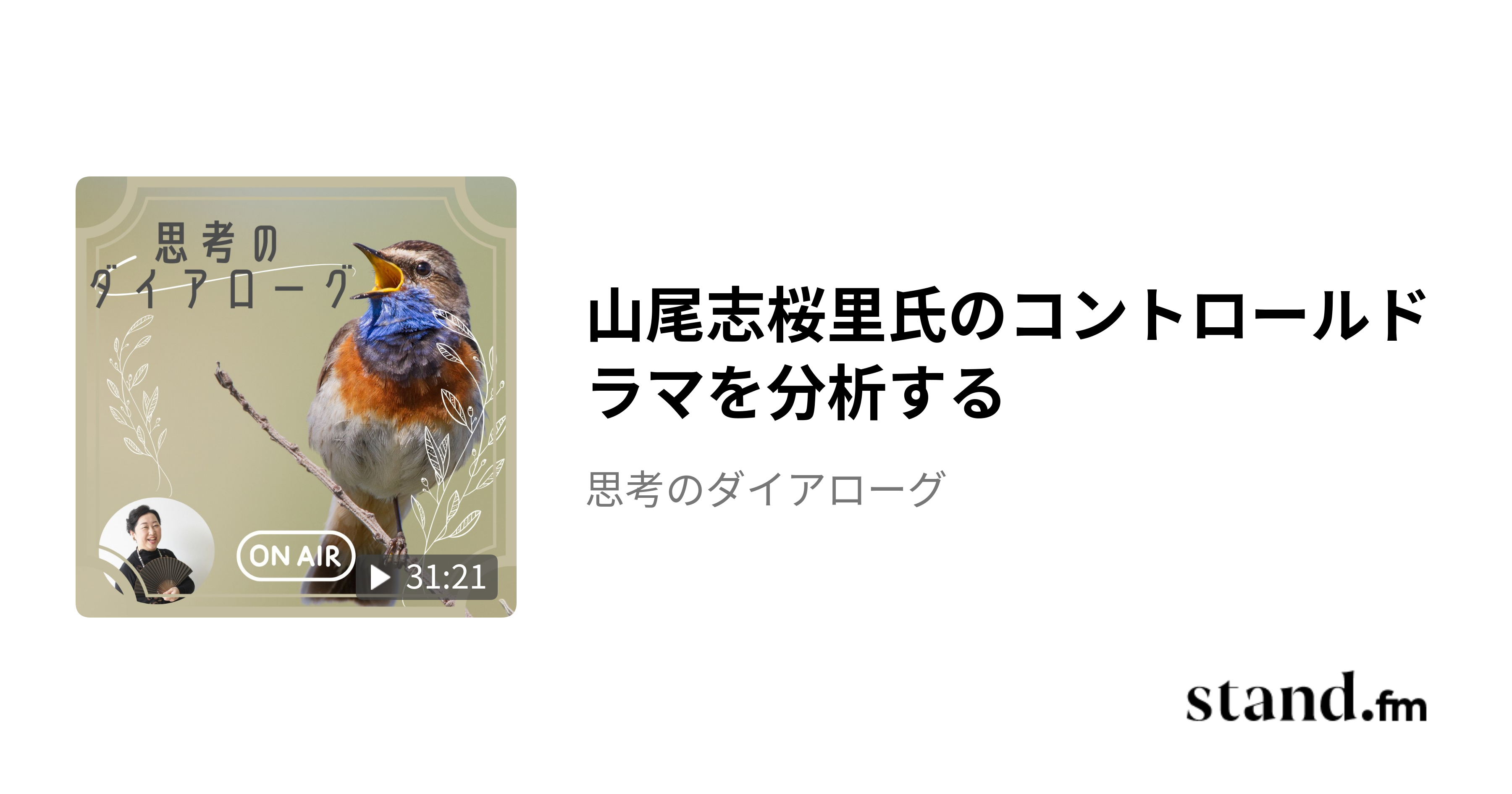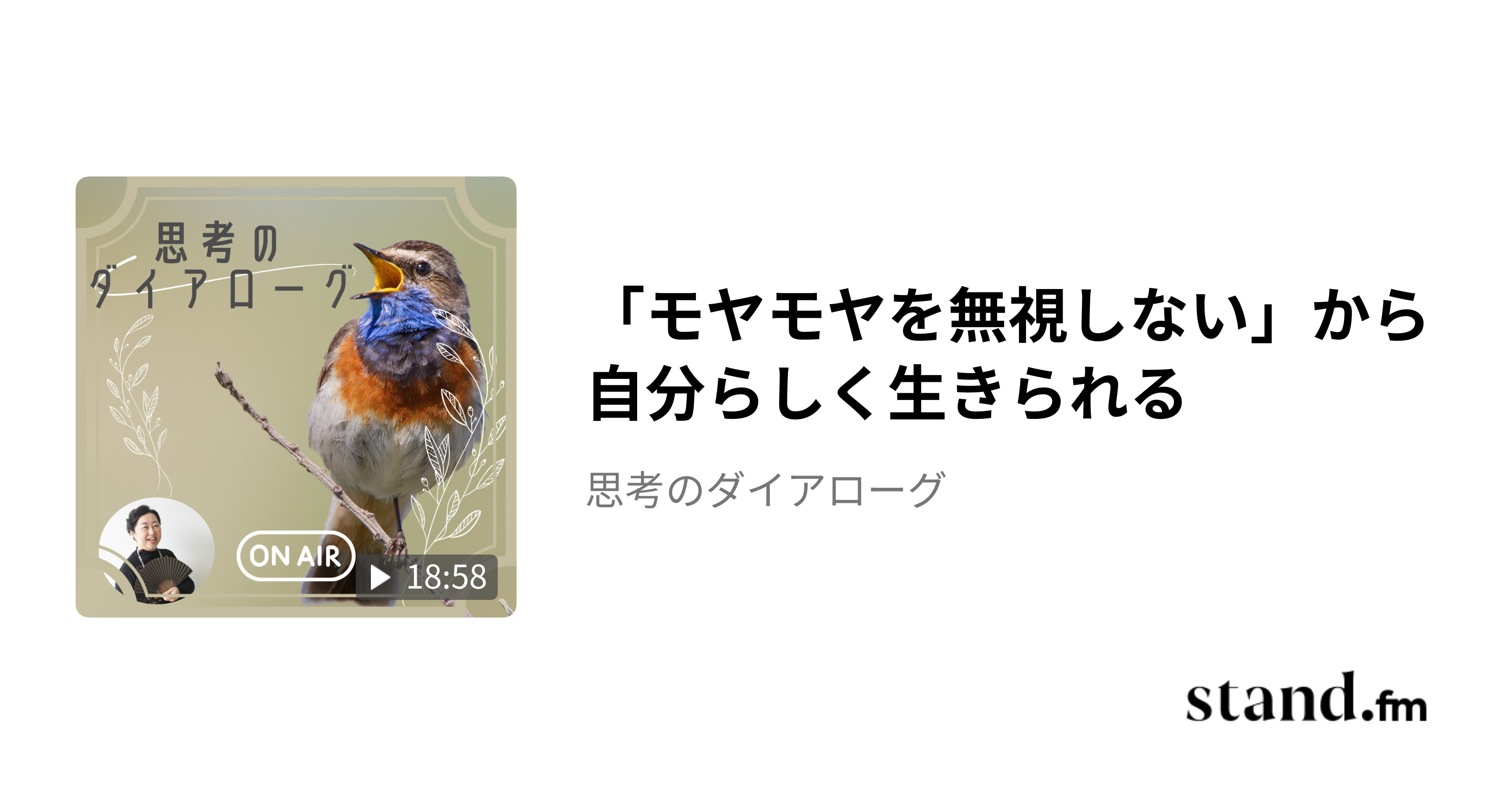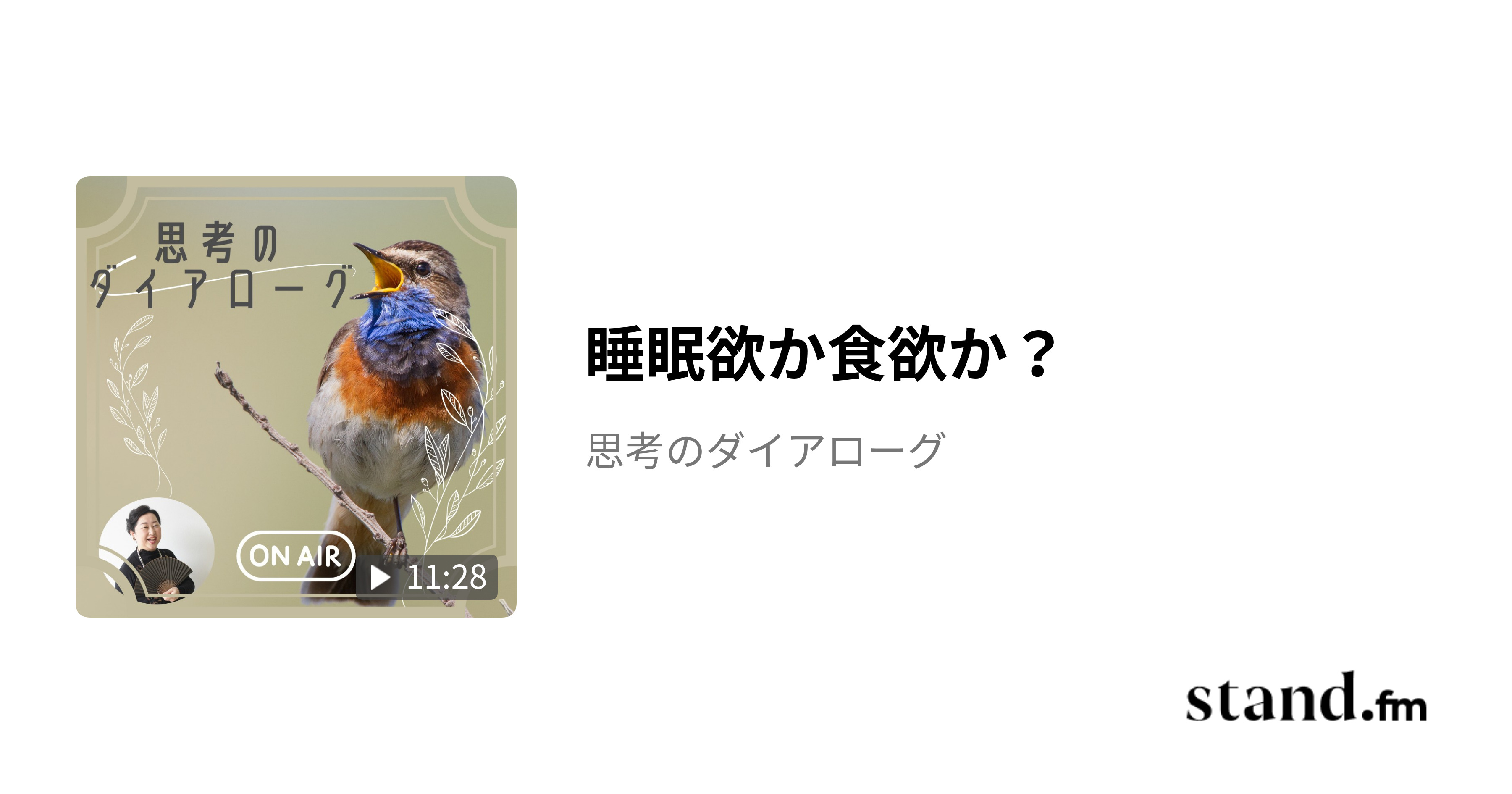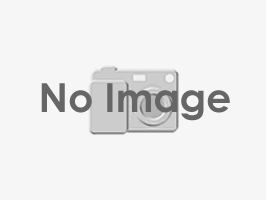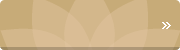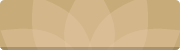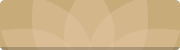雑感の智慧
- あなたはなぜ7月5日の“大地震予言を信じたのか? 心理的考察と認知バイアス
-
お施餓鬼に参加 供養とは何か?
- 山尾志桜里氏のコントロールドラマを分析する
- 選挙は「悪者を倒すゲーム」ではない 深田萌絵氏の出馬、その真意は?八王子市民のつぶやき
- 小さな悪意が心を壊す
- 「なんかしんどい」は、変化のサイン
- 読みやすい記事はちょっとした思いやりでできている
- 「モヤモヤを無視しない」から自分らしく生きられる
- こだわるところそこじゃないんだよなぁ(水素水をお客に出してしまうお店への不信感)
- 睡眠欲か?食欲か?
あなたはなぜ7月5日の“大地震予言を信じたのか? 心理的考察と認知バイアス

2025年の7月5日。
SNSや動画配信の世界では、ある「予言」が話題になっていました。
「この日に大地震が起きる」
「外出は控えた方がいい」
「直感を信じて動かないで」
そんな文言が、まるで警告のように流れてきて、ちょっとドキッとした方もいらっしゃるのではないでしょうか。
私も、何人かから「どう思います?」と聞かれました。
私は地震が起きるとか起きないとか、そのこと自体よりも
「なぜあれだけ多くの人が、予言に注目したのか」
が気になりました。
未来が不確かだと、人はとても不安になります。
たとえば、いつ地震が来るか分からない、何が起きるか見通せない──そんな妙に落ち着かなくなった時
誰かが「〇月〇日に〇〇が起きます」と言い切ってくれると、
「怖いけど、備えられる」
「来るならその日に来ると分かってるほうが安心」
そのようにに思ってしまうんです。
これは心理学的に「不確実性の回避」と呼ばれる反応で、人間の自然な心の動きなのです。
不安に満ちた未来よりも、たとえ怖い未来でも、見通せる方がラクだと感じる。
そう考えると、「予言を信じる」のは人としての自然な反応なのかもしれません。
今回の予言のなかには、「関東で揺れが来るかも」とか、「震度5以上の可能性」みたいな曖昧な表現もありました。
こういう言葉は、当たったように感じやすいんです。
少しでも地震があれば「ほら当たった!」と思えますし、何も起きなくても「警戒してたから回避できたんだ」と納得できてしまう。
これは「バーナム効果」と呼ばれる心理現象で、誰にでも当てはまりそうな言葉を「私のことだ」と感じてしまうこと。
さらに、もともと信じたいと思っている人は、そういう情報だけを集めて、「やっぱり当たる」と思ってしまう。
これが「確証バイアス」と呼ばれる心理的な傾向です。
つまり、私たちの心には「信じたいように見る」仕組みが、そもそも備わっているんですね。
ここまで読むと、「やっぱり予言なんて信じるべきじゃない」と思われる方もいるかもしれません。
でも私は、ちょっと違う視点で見ています。
「信じたい」と思う気持ちは、とても人間らしいものだと思うんです。
それは「弱さ」に見えることもあるでしょうが、そもそも人はそんなに強いわけではありません。どんな時も安心したいし、快適で幸せな状態でいたいものですよね。なら、不安を回避するために、どんな形であれ自分本位に物事を捉えることがあるのも仕方がないことではないかと思います。
でも、もし「信じたい」が「信じ込まされる」に変わってしまったら——
一度、立ち止まってみることも大切かなと思うのです。
「信じたい」はあくまでも自分発信の気持ちですが、「信じ込まされた」ものを信じるのは他人軸になってはいないでしょうか?
他人軸で振り回されていると、それが間違っていた時や、自分の意にそぐわないものだと気付いた時、それは間違いなく他責になります。
自分じゃない、あいつのせいだ!ってやつですね。
そうなってしまうと、自分の間違いに気づくこともしにくくなりますし、自己保身のためにより攻撃的になってしまうことのありえます。
そうなったら内省からどんどん離れていってしまいますね。
予言でも、占いでも、スピリチュアルな言葉でも、信じたい理由があるはずです。それがぶれていないか?
自分の中にある「信じたい理由」を見つめることが、情報に振り回されないための小さなヒントになるように思います。
今回の“7月5日問題”は過ぎ去ろうとしていますが、
これからもきっと、「〇〇が起きるかも」という話題は定期的に出てくるでしょう。
そのとき、誰かの言葉に心が揺れたら、「私は、何のために信じたいと思ったのか?」を考えてみてください。
そして私たちはどんなことも
「自分の見たいようにみて聞きたいように聞き、感じたいように感じる」ことを忘れないでください。
人に振り回されるなんてこと、バカばかしいじゃありませんか。
記事を読んでくださって ありがとうございます
お施餓鬼に参加 供養とは何か?

今日は、昨日参加してきた「お施餓鬼」の法要について、ちょっと語ってみようかなと思います。
我が家の菩提寺は八王子の山のほうにある禅宗のお寺です。毎年、7月にはお盆に「棚経(たなぎょう)」に来てくださっていたんですが、コロナ禍でそれも途絶えてしまいました。そんな中「お施餓鬼」の法要は変わらず続けてくださっていて、今年もお寺に行ってきました。
お施餓鬼ってなに?
「お施餓鬼(おせがき)」というのは、「この世のすべての餓鬼たちへの供養」です。餓鬼というのは仏教の六道のひとつで、飢えと渇きに苦しむ存在のこと。欲を満たそうとしても一瞬で消えてしまい、またすぐに飢えてしまう──そんな苦しみを抱えた存在とされます。
通常のお盆や法要は、自分の家のご先祖さまの供養ですが、お施餓鬼はもっと広く、縁もゆかりもない霊たち──苦しんでいるすべての存在への祈りなのです。
起源は、お釈迦さまの弟子「目連尊者(もくれんそんじゃ)」の伝説。母が餓鬼道に堕ちたのを見た目連さんが、お釈迦さまに相談し、「多くの僧侶に食物を施す法要を営みなさい」とのことで実際に法要を行ったところ、そのおかげで母が救われた、という話から来ています。だから、お施餓鬼は「大いなる施し」なんですね。
このお施餓鬼の行事、お寺に行くと、八王子市内の曹洞宗のいろんなお寺のお坊さんたちが集まって、十数人で一斉にお経を読んでくださるんです。
これがなかなか見応え、聞き応えがあります。ジャンジャン、ポクポクと鳴り物も響きわたって、正式な作法で丁寧にお経があげられる。
「こんなにたくさんのお坊さんが一緒に祈ってくれるなんて、すごいことだなあ」と思いながら、わたしは静かに手を合わせていました。もちろん、我が家のご先祖のための塔婆もたてましたが、それだけでなく、「今苦しんでいるかもしれない誰かのために」という祈りのかたちに、少し胸が熱くなりました。
供養とは、思い出すことなのかもしれない
わたしは供養とは、「亡くなった人を思い出すこと」なのではないかと思います。お墓参りに行ったり、お仏壇に手を合わせたりするとき、きっとみなさんも、その人のことをふと思い出すと思います。
「こんな人だったな」「あんな言葉をかけてくれたな」──そうやって、亡くなった方を思い出すことが、供養になるのではないでしょうか。
そしてその行為は、自分を大事にすることにもつながっている。
なぜならわたしたちは、無数のご先祖の命のリレーの果てに、今ここに生きているんです。自分ひとりでここに存在しているわけじゃありませんよね。
戸籍の話にも触れましたが、わたしたちは家族の、そして歴史の「末端」にいます。
ルーツを辿ると、知らなかった祖父母の人生が見えてきたりします。大家族だったり、子どもをたくさん育てたり──その積み重ねの果てに、今の自分がある。
文化や歴史というものは、簡単に絶やしてはいけないなと思います。
「今ここ」があるのは、過去があるから。私たちが今できることは、そのつながりを感じ、受け継いでいくことだと思いませんか。
お施餓鬼の法要に参加して、
「わたしにできることなんて小さいけれど、でも、手を合わせることはできる」
そういう優しさを持ち寄る場に参加できたことがありがたかったと思いました。
機会があったら、ぜひお寺の行事に足を運んでみてください。
面倒くさい、暑い、忙しい……いろんな理由はあります。でも、「そこに行くこと」でしか感じられないものも、あるはずです。
わたしたちは、つながりの中に生きている──そんなことを考えた、今年のお施餓鬼でした。
記事を読んでくださって ありがとうございます
山尾志桜里氏のコントロールドラマを分析する

ここしばらく体調を崩しておりましたが、ようやく復調の兆しを感じております。眠りによって回復するのは自明の理。バイオリズも上下するものですからね。
今日はネット界隈では炎上気味だったことをコントロールドラマ視点で語ってみようと思います。
コントロールドラマって何?
人は誰しも、他者との関係の中で「何かしらのキャラ」を演じています。これは意図的というより、無意識のうちにやってしまっているもので、これを「コントロールドラマ」と呼びます。
コントロールドラマには、次の4タイプがあります:
脅迫者:相手を威圧して主導権を握ろうとする
被害者:同情や保護を引き出すために弱さを演出する
尋問者:質問攻めで相手を責め、優位に立とうとする
傍観者:距離をとって関心を集める、安全な場所から関係性を支配する
これらは、幼少期の家庭環境、特に親子の関係の中で身につけた、対人関係のクセのようなものです。
参院選の候補者擁立の動きの中で注目を集めた山尾志桜里さん(本名:菅野志桜里さん)。記者会見や言動を見ていて感じたのは、彼女の中に浮かび上がる“被害者”と“傍観者”のドラマです。
たとえば、国民民主党からの公認を取り消された件。彼女は「私は声をかけられたから立候補を決めたのに、それをひっくり返された」と主張していました。客観的な事実なので、それだけ聞いてあぁそうなのねと捉えるだけならばドラマに乗らずに済むのですが、これは「自分は傷つけられた側」というメッセージであり、同情や共感を誘う語り方。まさに“被害者”のドラマです。
一方で、「言えることはありません」「その点については話しません」といった、距離を取った物言いも多く見受けられました。この態度には“傍観者”のドラマも重なって見えます。出来事の当事者でありながら、どこか他人事のように見える態度です。元検察官だそうなので、さまざまな物事を割り切ったり客観的な見方をすることができる方なのかもしれません。今の自分と過去の自分、プライベートな自分と公的な自分。自分で自分に傍観者のドラマを仕掛けるなんて、なかなかのテクニシャンです。
山尾さんの語り口は、理路整然としていて、知的であることは間違いありません。しかし、「だから応援したい」と思わせる“熱”や“人間味”が、私にはいまひとつ伝わってきませんでした。
政治家には知性と人間味の両方が必要なのかも
人は感情の生き物です。
政治家には、論理の筋道だけでなく、「人として信用できる」と思わせるような、情や誠実さの表現が求められるのではないでしょうか。
過去にスキャンダルに見舞われた玉木代表が、謝罪し再出発を図った姿は、その意味で多くの人の心をつかみました。潔さや率直さに、日本人は弱い。だからこそ、誤魔化しや言い訳が透けて見えてしまうと、逆に大きく信頼を損なうのです。
人は、つい自分のキャパシティを越えたものに手を出したくなります。「できるかもしれない」「やれるはず」と。それは好奇心であり向上心の表れなので、否定されていいものではありません。
しかし、器(うつわ)以上のものを抱えれば、いずれ歪みが生まれ、ひび割れ、崩れてしまう。そうなる前に、「自分の器を知る」こと、「今の自分に合った役割を選ぶ」ことは、とても大切です。
それは政治家に限らず、私たち一人ひとりに言えることです。社会の中で、どんな関係性を築いていきたいのか。どんな関わり方で、自分らしさを保っていきたいのか。静かに、丁寧に、見つめ直したいところです。
コントロールドラマは、誰もが無意識に演じてしまう“クセ”。しかし、そのクセに気づいたとき、わたしたちは選択肢を持てるようになります。
・無意識にドラマを仕掛けて相手からエネルギーを奪うのか
・エネルギーを奪うためのドラマをせず不愉快さを撒き散らすことをやめるのか
選挙の季節。政策やスローガンだけでなく、「この人はどんなドラマを演じているのか?」という視点で候補者を見ると、少し違った風景が見えてくるかもしれません。
その人の“演技”の奥にある、本当の素顔を見極める、そんな視点もあっても良いかと思います。
選挙は「悪者を倒すゲーム」ではない 深田萌絵氏の出馬、その真意は?八王子市民のつぶやき

小さな悪意が心を壊す

先日、運転免許の更新に行ってきました。久しぶりの免許センター。
平日だというのに人は多く、入口からして行列。ここでは、日々たくさんの人が同じ手続きをしているのでしょう。案内の導線もとても効率的にできていて、まるで工場のように「あちらへ」「こちらへ」と流れていきます。
私はというと、「はい、次の方」「こちらにどうぞ」と、矢印に従い、番号に呼ばれ、写真を撮られ、講習を受け、無事に新しい免許証を受け取って帰ってきました。
手続きはスムーズ。何も問題はありません。なのに、なぜか虚しいというか、寂しい気持ちになってしまいました。
「心を殺して」働いているように見えた人たち
というのも、窓口にいた職員の方々の言葉や態度が、まるで機械のように感じたからです。
「◯番にお進みください」「免許証を出してください」「そちらのイスでお待ちください」
マニュアルに沿った言葉に、マニュアルに沿った口調。笑顔もなく、抑揚もなく、ひたすらに、同じ言葉を何百回と繰り返しているようでした。
もちろん、それがその人の“本当の人柄”だとは思ってはいません。むしろ、毎日毎日、次から次へとやってくる人を淡々とさばいていかなければならない現場で、いちいち心を込めていたら身がもたないのかもしれない、と想像しました。
そうして“心を殺して”仕事をしているように見えてしまったその姿に、私はなんだか切ない気持ちになったのです。
これこそAIが担ってもいい仕事なのかもしれない
こういう仕事こそ、AIとかアンドロイドで代替できたらいいんじゃないかと思ってしまいました。手続きそのものはルールに沿って流れ作業でできるし、そこには“心”というよりも、丁寧さや問題が起きた時のクレーム対応を迅速にできることのほいが求められるように思うのです。思いやりや、心づかいの“ように”感じさせることができれば、それはそれで十分なのかもしれません。クレーム対応をAIに任せようというのも、私はアリだと思います。人を傷つけることでストレスを解消しようとする悪意に対して、心を人質に取られているようなことはおかしなことだと思います。
生身の人間に心を動かさずに仕事に徹してと言っても、それは無理な相談です。心を守るために、心ない無感情な対応をせざるを得ないのは苦しいことでしょう。
AIやロボットがすべてを奪う時代が来るのが怖い、という声もよく聞きます。しかし人の“心”を押し殺さなければやっていけないような仕事なら、むしろ機械にやってもらったほうがいいのかもしれない。おそらく心を奪ったものは業務の効率化。そしてそれ以上に彼らの気づかいや思いやりが無視されたり、おざなりにされたりしたことによる疲弊感なのではないでしょうか。人が人に向けるちょっとした悪意。それが少々でも、日常的に多く積み上がれば大きな悪意になるでしょう。
免許センターで、機械的に書類をさばいていた職員さんをロボットのようにしてしまったのは、受け手である免許証を更新に来た私たちにあるのではないかと思ってしまうのです。人間にしかできない「心を使う仕事」「心を届ける仕事」は、一方通行では成り立ちません。人が人と対峙する時、お互いが相手を思いやることで生まれる感謝がなければ、気持ちの良い関係は築けないなと確認させられるような出来事でした。
「なんかしんどい」は、変化のサイン

誕生月の低空飛行。変化の波に乗って、生きてますよ。
こんにちは、自分を知りたい・変わりたい方に向けて「楽園志向」を指南するアリカ塾を主宰している、語り部の星野つゆ子です。
ゴールデンウィークも過ぎて、平日なのか休日なのかわからない感覚のまま日々が進んでおりますが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。私も帰省したり、母のいる施設に会いに行ったり、兄弟とお寿司をつまんでおしゃべりしたりと、ちょっと「休日らしい休日」を過ごしていました。
身体の不調と医療との付き合い方
ところがその直後、謎の腹痛で一晩中うんうん唸り、挙句の果てには急な悪寒からの高熱。いやもう、子どもかっていうくらいガタガタ震えて、布団の中で「これはくるぞ…」ってやつでした。
けれど救急車を呼ぶかというと、まぁ、呼ばないんですよね。痛み止めくらいしか打てないって、わかってるから。しかも私、病歴も薬歴もけっこう複雑で、いちいち説明するのがもうしんどい。
もちろん、こんな自己判断は全然おすすめしません。私はたまたま医療の知識があって、主治医とも長年の信頼関係があるからできてるだけ。でも、こういうとき思うんですよね。
「原因がわからない不調」にどこまで突っ込むべきか。検査も治療もやりすぎれば別のリスクが出る。その微妙なさじ加減って、本当に難しい。
変化の折り返し地点に立つとき
そんなわけで体調は低空飛行。だけど、この状態って、何かの「変わり目」なんじゃないかなってふと思いました。波って、上がる時よりも、上がる前とか下がる前の「折り返し」の時が一番しんどい。
人生の中でもそういう瞬間ってありますよね。変化の入口って、ざわつくし、不安だし、落ち着かない。でも、そのざわつきに「今、変わろうとしてるんだな」と気づけたら、少しラクになるかもしれません。
ちゃんと見なきゃいけない時と、見すぎない方がいい時。人生には、両方あるんだと思います。
すべてを明確にしようとすればするほど、不安や恐怖もリアルに迫ってくるから。だから私は「これは仮説」「今は流していい」と、自分の中で整理するようにしています。
誕生月は心の棚卸し
実は、今月は私の誕生日月でもあります。50を過ぎると別に嬉しくもないけれど、やっぱりくるんですよね、この「1年分の棚卸し」感。
なんだか心身の底から、いろんな感情や思考が浮かび上がってきて、「ああ、今、整理しろってことなのかもな」と。
誕生月ってそういう作用がある気がします。見ないふりしてたこと、流してきたこと。そういうものが顔を出す。
見えなかったものが見えてきたり、聞こえなかった声が聞こえてきたり。私にとっては、それが「生きてる証」なんでしょうね。
ということで、今日は「とりあえず、生きてますよ」というご報告でした。
体調はぐずぐずですが、こんなふうに言葉を綴ることで、自分がちゃんとまだここにいるって確認してる気がします。
みなさんも、もし誕生月が近い方がいらしたら、ちょっと自分の心と身体に目を向けてみてくださいね。
見えてくるものがあるかもしれません。
読みやすい記事はちょっとした思いやりでできている

私は文章を書くときに、いつも気にかけていることがあります。
それは、「読みやすさ」。
パソコンで文章を打ち込むとき、
変換キーを押せば、いろんな漢字がぱっと出てきますよね。
普段、話し言葉ではよく使うけれど、
漢字にしてしまうと急に読みづらくなる言葉も、意外と多いものです。
これは、変換ありきで文章を打っていると、
つい見逃しがちなことだなぁと、最近改めて感じることがありました。
たとえば、「お咎め」。
(おとがめ)と読むこの言葉、
先日、あるブログで漢字表記で出てきたのですが、
私はふと立ち止まってしまいました。
「これ、なんて読むんだっけ?」
すぐに調べて「ああ、そうだった」と思い出したのですが、
そこそこ本を読む私でも、迷ってしまう瞬間があるんだなぁと、苦笑い。
もちろん、これは私の知識不足と言われれば、それまでです。
でも、人に読んでもらうための文章であるならば、
「一瞬でもつまずかせない工夫」は、とても大事なことだと思います。
もし私なら、
きっと「お咎め」とは書かずに、
ひらがなで「おとがめ」と表記するでしょうね。
私が良く使う「拘り(こだわり)」なんかも、そうですね。
漢字で書いた方が意味が引き締まる場面もあれば、
逆に、読み飛ばされたり、硬く感じられたりすることもある。
文語と口語。
文字と声。
その違いを意識しながら、どちらがふさわしいかを、
その都度、選んで表現したいと思います。
文章は、誰かに届けるものです。
「わかりやすさ」や「読みやすさ」は、
書き手から読み手への、思いやりだと、私は思うのです。
読みにくさも、もちろん時には表現の一部になり得ます。
でも、それは意図して選ぶものであって、無意識に押し付けるものではないと思います。
最近はAIを使用して文章を書かれる方も多いでしょう。
それが悪いことだとは思いません。
文章を整理したり、まとめたり、AIにサポートしてもらうことで新しい切り口の表現が生まれることもあると思うからです。
ただこの読みやすさや、自分らしい語り口になっているかは、最後ちゃんと出来上がった文章を読んで、手直しすることは大切ではないでしょうか。
自分が発信する内容が、自分らしくなかったら上手く書けていても、面白くはないと思うし、読み手にはそれがちゃんと感じられるものです。
読みやすさは思いやりですし、自分らしさは自分へのリスペクトです。
文章を書くうえで、私はこれらを忘れないようにしていきたいと思います。
「モヤモヤを無視しない」から自分らしく生きられる

最近個人経営のお店がどんどん閉まっていて
チェーン店ばかりになっている中で
新しくオープンしたお気に入りのお店。
夫と何度かランチどきにうかがって、
オープンキッチンだし
お値段もお手頃で
セットに私の大好きな茶碗蒸しがついているのも
お気に入りポイント。
でも、先日。SNSで見かけたある投稿に、
心がざわついてしまいました。
それは、某お笑い芸人出身の著名人
(仮に「N氏」とします)のアカウント。
彼が手がけた作品「●●ル」(※伏字)
のチケットを50枚購入すると、
本人が直接お礼に伺うというキャンペーンをしていて、
そのお店が、まさにそれに参加していたのです。
店主さんとスタッフらしき人たちが、
満面の笑みでN氏と一緒に並んでいる写真。
それを見た瞬間、
胸の奥に、もやもやとした感情が広がってしまいました。
正直に言うと、
私はN氏のビジネスのやり方に、
かねてから違和感を抱いていました。
「応援」や「夢」を看板に掲げながら、
その裏で、
「これって本当に必要なことなんだろうか」
「誰かの無理な善意を、利用していないだろうか」
そんなふうに感じる場面が、
何度もあったからです。
そして『●●ル』という作品についても、
個人的には、あまり心に響かなかったというのが
本当のところだったりして。
そんな背景があったからこそ、
お気に入りのお店が、
その世界観に嬉々として加わっている姿を見るのは、
思った以上にこたえるものがありました。
まるで、
大好きだった友人が、
自分とは相容れない何かに心酔してしまったのを
知ったときのような。
そんな、勝手な寂しさ。
冷静に考えれば
お店の味にも、
値段にも、何も関係ない。
もちろん店主さんにも、
自由に応援する権利がある。
それでも、
心は理屈通りにはいかないものです。
好きだったからこそ、
勝手に裏切られたような気持ちになってしまいました。
「好き」と「信じる」は、似て非なるもの。
似ているからこそ
心が勝手に勘違いを起こしてしまったのかもしれません。
誰かを、何かを、好きになった瞬間に、
無意識に
「この人は、私と同じ、もしくは似た価値観だろう」
と自分なりの信頼を重ねてしまう。
それが、違う方向を向いていると知ったとき、
自分でも驚くほど、心は脆くなってしまう。
つまらない、
小さなことと言えなくもない。
気にしなくてもいいし
わざわざネガティブな気持ちで
不愉快にならなくてもいいもかもしれません。
しかし、私は小さな違和感を、
「たいしたことない」とごまかしたくないのです。
心に生まれたモヤモヤを、なかったことにしたくない。
なぜなら、
このネガかもしれないこのモヤモヤが
私自身が何を大切にしているのか、
何に違和感を覚えるのか、
どんな価値観を選んで行きたいのか
その“本音”を教えてくれる、
かけがえのないサインなのかもしれないと思うからです。
好きだったものにがっかりするのは、悲しいことです。
でも、悲しさを感じられるのは、
素直に自分の感情を感じている証拠ですし
それが自分の心に誠実に生きようとしている証なのではないかとも思うのです。
心が「違う」と感じる時、
私は、ちゃんとそれを受け止める。
なぜなら、
自分の心に嘘をつき
大袈裟かもしれませんが裏切るようなことに慣れてしまったら、
いつか、大切なものを見失ってしまうかもしれないと思うから。
小さな違和感やモヤモヤを無視せず、
「これは違う」と思った自分をちゃんと見つめる。
これも自分軸を確認する作業だったりしなやかに、
生きるのに必要なことかもしれません。
こだわるところそこじゃないんだよなぁ(水素水をお客に出してしまうお店への不信感)

鴨南蛮そばが好きです。温かいおつゆに噛むたびにじゅわっと鴨のあぶらの旨味が広がってそこに葱の香ばしさが合わさって。最後に蕎麦の香りがふわっと追いかけてくる感じが、たまらないなぁと毎回しみじみ思う。
そんな鴨そばを出すお店が、最寄り駅の近くにあるのを知ったのは、つい最近のこと。「いつか夫を誘っていってみよう」と思っていたお店です。SNSもやっていて、店主さんが蕎麦へのこだわりや産地の話を投稿していて、それも好感を持って眺めていたんです。
ところが、ある日目にした投稿に、ふと心が引っかかってしまいました。
「当店では、お水にもこだわっています。“水素水”をお出ししております」
……水素水。
ああ、そっちか、と。
「水素水」と聞いた途端、心が遠のいてしまいました。好きな人には申し訳ないんですけど、どうにもその言葉には「ん?」と思ってしまうのです。
もちろん、水にこだわること自体は理解できます。料理に使う水は、素材の味を引き立てる大切な要素ですから。でも、「水素水」というワードになると、怪しさの方が先んじてしまいます。だって、水素ですよ。水素分子はとても小さくて、まぁ水素が溶け込んだ水を缶とかペットボトルに詰めたとしても飲む頃には全部飛んじゃってますよ。水素水ってただの水を飲んでいるのと変わりませんからね。
興味のある方は、現役の科学者の方々がわかりやすく解説している動画もあります。
少し怪しげなビジュアルで始まりますが、中身はとても信頼できる内容です。こちらからご覧いただけます。
視聴者の期待に応えて、水素水をブッ叩く!!!!
私が躊躇するのは、そのお店が信じていることへの違和感というより、「わたしがこの店に感じていた“確かさ”みたいなものは、少し幻想だったのかな?」と寂しくなってしまう、そのズレの方なんです。
ああ、もったいないなぁ。鴨そば、おいしいんだろうなぁ。でも今の私は、その湯気の向こう側にうっすらと「水素水」が浮かんで見えてしまって、なんとなく足が向かなくなってしまう。
これはもう好みの問題なんでしょう。信じているものが違うと、少しだけ距離が生まれるのは、食べ物に限らず、どんなことでもあるものですから。
睡眠欲か?食欲か?

皆さん、体調がすぐれない時、そこから回復するのにいろいろ手段を講じるかと思いますが、私の場合「寝るか?食べるか?」の二択なんですよね。
生命維持に必要なこの二つ。
それでもギリギリの時、どちらを選ぶかといえば、私は「寝ること」を選びます。
貧乏看護学生だった時、食べるものがなかったのでお腹が空いたら東京水道水を飲んで、お腹を膨らませて寝ていたこともあるくらい、寝ないと活動できませんでした。それは今も変わらず、体調のすぐれない時は1日の半分寝ていることもあります。こんなに寝てばかりいると「なんて怠け者なんだ」と自分を責めてしまうこともありましたが、実際寝ずに無理して起きていたとしても、起きている時もパフォーマンスはあまり良いものではありません。結局起きていていいことがないなら、寝て少しでも体の調子を上げたほうがいいことに気づきました。
行動は間違いなく怠け者に見えることでも、私にとっては必要なことだということです。
歳をとったこともあるかもしれませんが、自分にちょうどいいことの方が、周りにどう思われるかで判断することよりも大切なことになってきているようです。