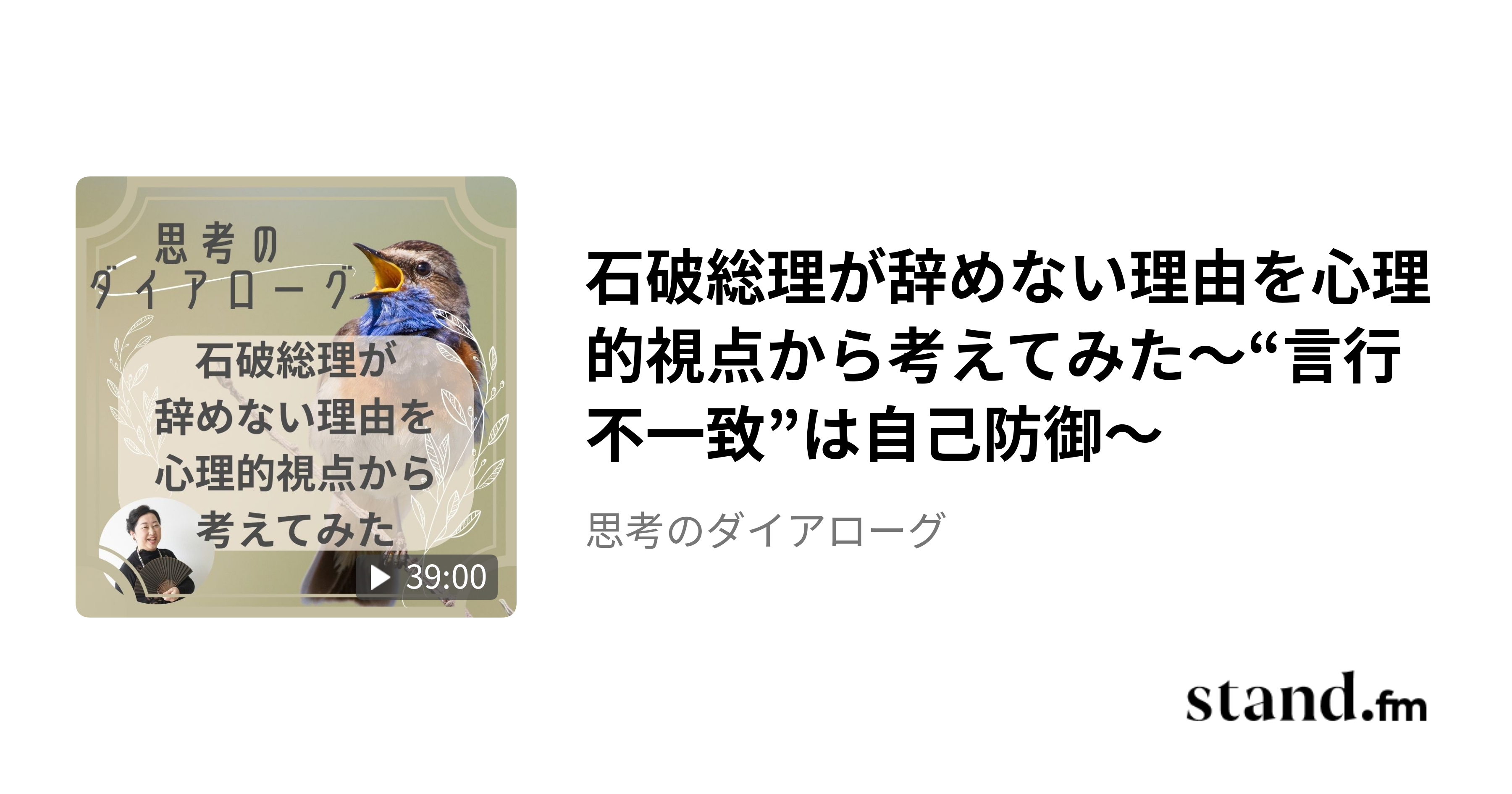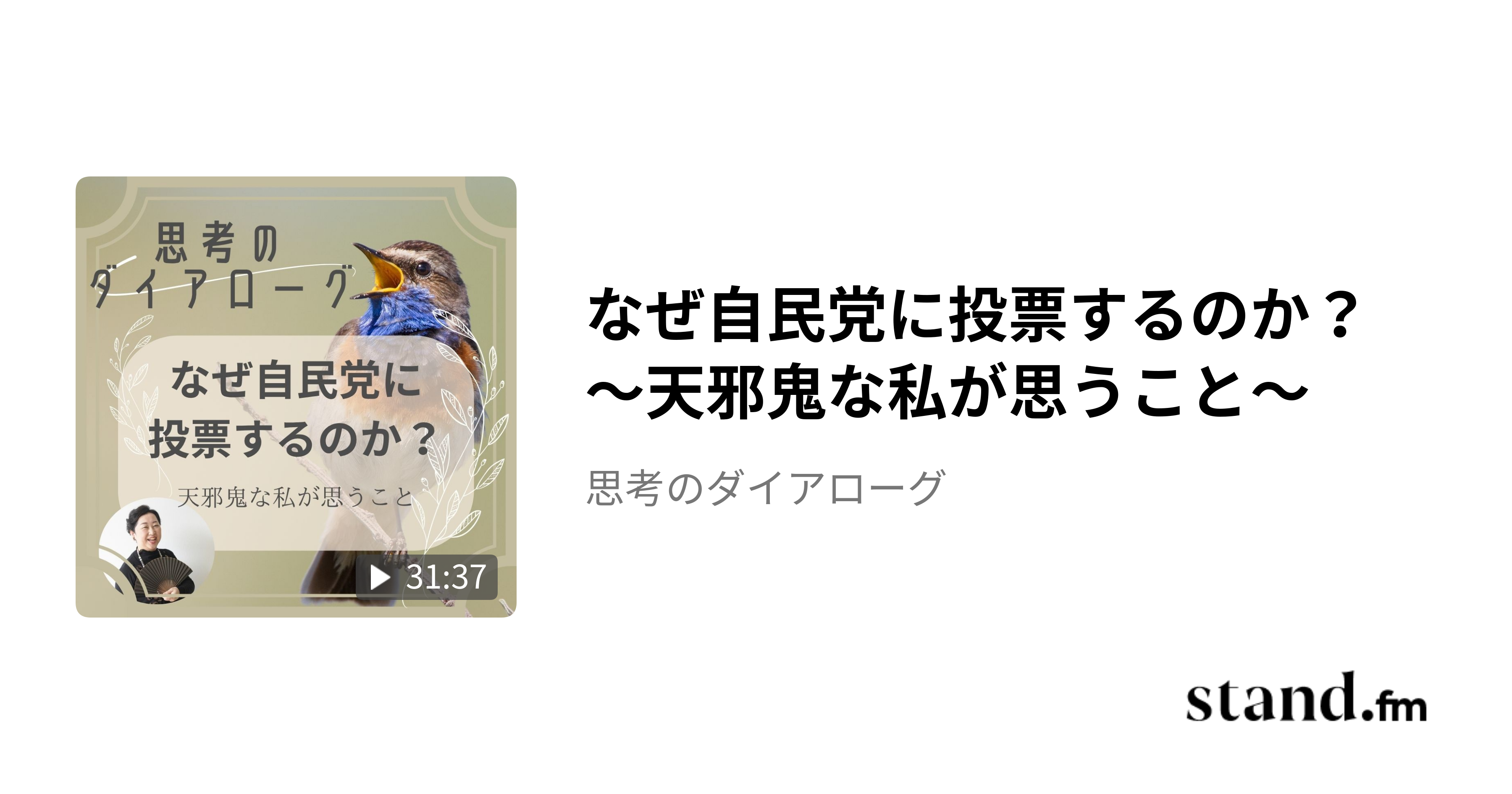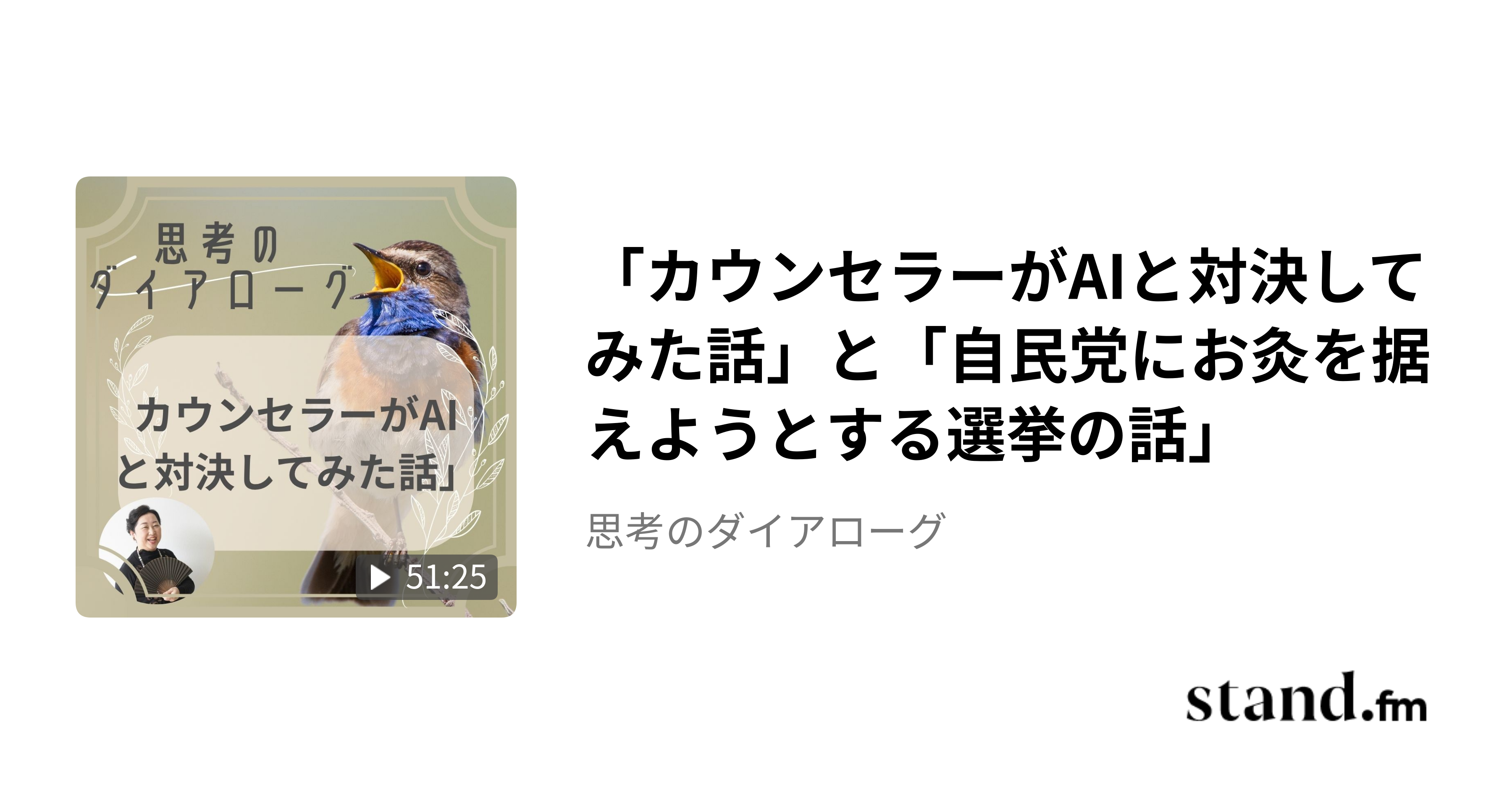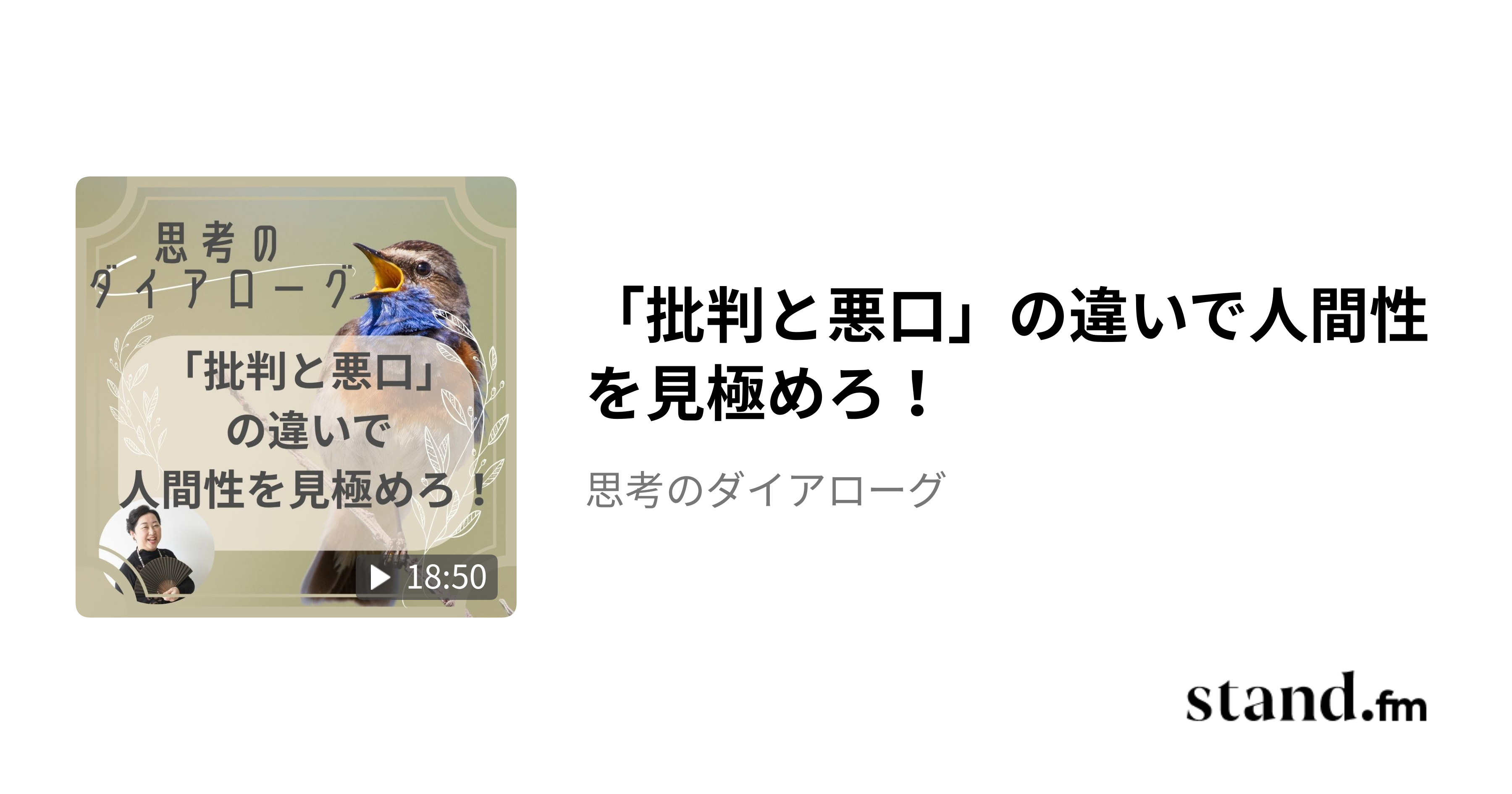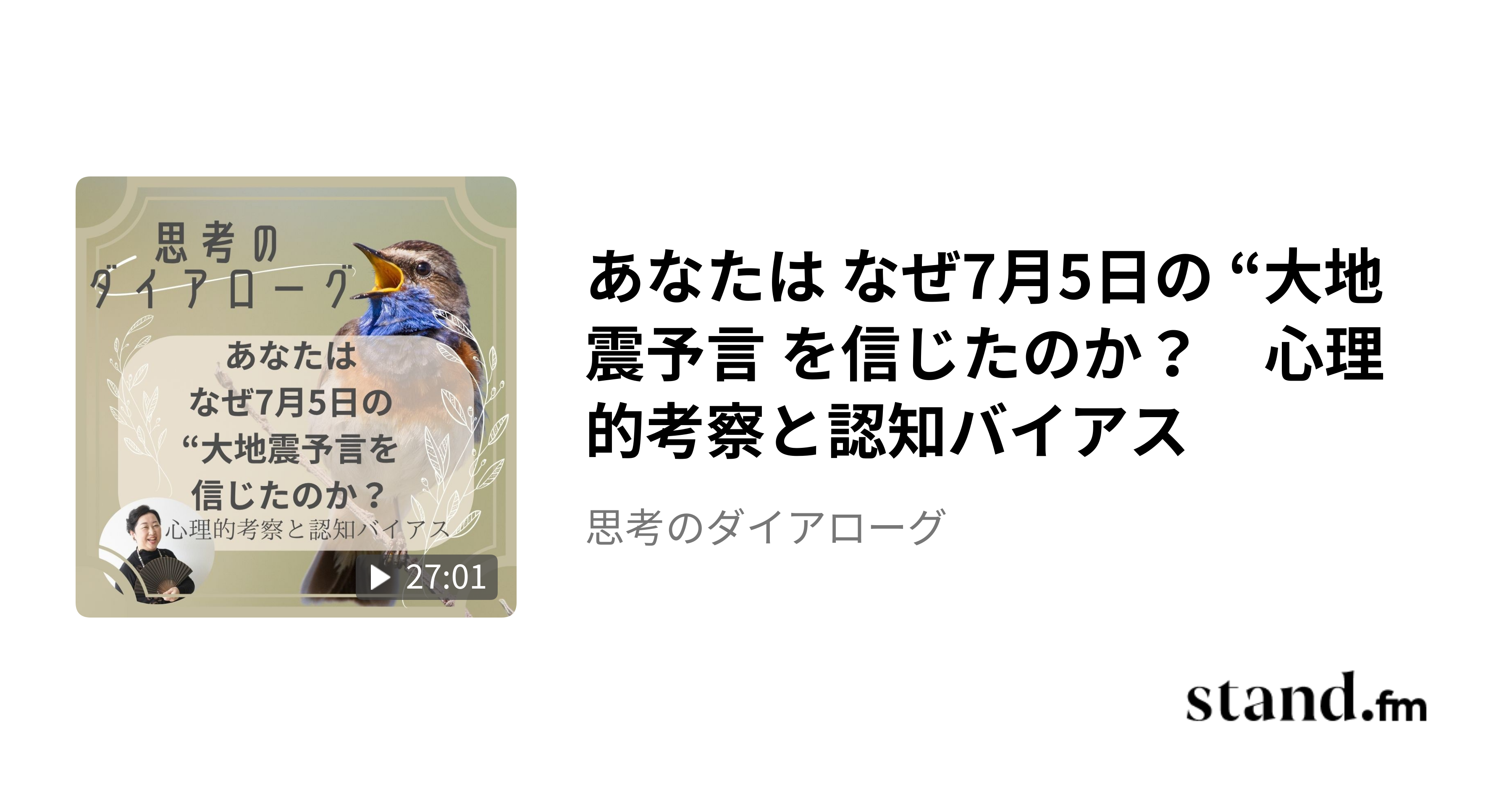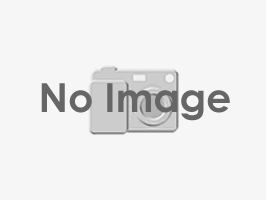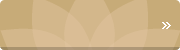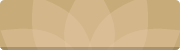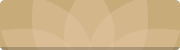雑感の智慧
- 石破総理が辞めない理由を心理的視点から考えてみた〜“言行不一致”は自己防御〜
- なぜ自民党に投票するのか? 〜天邪鬼な私が思うこと〜
- 「カウンセラーがAIと対決してみた話」と「自民党にお灸を据えようとする選挙の話」
- 「批判と悪口」の違いで人間性を見極めろ!
- あなたはなぜ7月5日の“大地震予言を信じたのか? 心理的考察と認知バイアス
石破総理が辞めない理由を心理的視点から考えてみた〜“言行不一致”は自己防御〜

参院選で自民・公明が過半数を割り込み、いよいよ政権への信任が揺らぎはじめている
そんな中でも、石破総理は「辞任せず、政権の立て直しに全力を尽くす」と続投を表明しました。
一見すると、強い覚悟。
けれど、「え?それって矛盾してない?」という感情です。
なぜなら、かつて石破氏は、他の総理に対して選挙の敗北を理由に辞任を促してきた人だったからです。
その姿勢に信頼や期待を寄せていた人も少なくないはず。
それなのに、自分が総理の立場になったとたんに、かつて自分が他人に求めていた「けじめ」をつけようとはしない。
この姿勢は、一体どう理解すればいいのでしょうか。
言っていたことと、やっていることが違うとき
私たちも日常の中で、「あれ?この人、前と言ってること違わない?」と感じる瞬間があります。
政治家だけでなく、上司や親、パートナーや自分自身に対してさえ、そんな違和感を抱くことはあります。
心理学では、こうした「言ってることと、やってることが噛み合っていない状態」を
認知的不協和(cognitive dissonance)と呼びます。
人は、自分の言動に矛盾があるとき、強い不快感や葛藤を抱きます。
そしてその矛盾を解消するために、さまざまな「理由づけ」や「例外」を作り出すのです。
たとえば石破総理がこう考えていたとしたらどうでしょう。
「今回の敗北は政権への不信ではなく、選挙区事情や候補者の問題」
「過去と今とでは状況が違う。今は自分が立て直すしかない」
「辞めることは責任ではない。残って全うするのが本当の責任」
この理屈は一見、筋が通っているように見えます。
しかしこの筋の通り方は、あくまで石破総理自身の正当性を誇示するための自分勝手なご都合主義の筋であり、彼のリーダーとしての責任を取るであったり、状況や役割に則った筋ではないように思えます。
人は、自分の矛盾には鈍感になりやすい
これは石破総理だけの問題ではありません。
私たち人間は基本的に、「自分の矛盾には寛容」で、「他人の矛盾には厳しい」傾向があります。
かつて「政治家は潔く辞任すべきだ」と語った彼の言葉は、ある意味、正論でした。
でもその正論は、いざ自分が当事者になると、「状況が違う」「今は特別だ」と、例外扱いされてしまう。
そして私たちの信頼は、この“言行不一致”に最も敏感に反応します。
信頼とは、過去の言葉と今の行動の重なりの上にしか成り立たない。
それが、政治であれ、家庭であれ、どんな関係でも変わらない真理なのだと思います。
石破総理の「辞めない」という選択は、もしかすると本人なりの責任感かもしれないと取ることもできます。。
しかし、今は「かつての言葉」と「行動」に追いかけられ、刺されていると言えます。
自己矛盾を孕んで発せられる言葉は、自分をも騙し、他者の信頼を大きく損ないます。自分を騙し始めたら、軸も正義も大きく捻じ曲がっていくと私は思います。
石破さんは何をみて何を守ろうとしているのでしょうか?
政治は国民の安らかな生きる世界をつくり、それを守るためにあるのではないですか?
自分を守るために自分都合を正当化するのは、総理のやることではないように思えます。心を取り戻して欲しいと思ったりしてしまいます。
記事を読んでくださって ありがとうございます
なぜ自民党に投票するのか? 〜天邪鬼な私が思うこと〜

本日のお話は「選挙」です。みなさん、参院選、行きましたか?
我が家では「選挙は必ず行くもの」と決めていまして。先ほども、暑い中、主人と一緒に投票に行ってまいりました。
選挙は、私にとって「大事な権利を行使する日」。息子たちが高校生だった頃から、「自分の一票を無駄にしないように」と伝えてきました。選挙権が18歳に引き下げられたあの年、高3の長男が初めて投票所へ。その翌年は次男も。家族4人で車に乗って、小学校の投票所へ向かい、投票を終えたらラーメンだの、うどんだの、焼肉だの…好きなものを食べて帰ってくる。
そんな“選挙の日の外食”が、ちょっとした家族のイベントになっていたんですよね。今は息子たちも独立し、別々に暮らしていますが、きっと彼らも、変わらず投票に行っていると思います。
今日、投票所に行ったら、いつもより人が多くて驚きました。なにせ八王子は自民、公明のガチガチの保守地盤。年配の方が多い印象ですが、今回は小さなお子さんを連れた若いご夫婦もたくさん見かけました。
「このままじゃいけない」と思った人たちが、重い腰を上げて足を運んだ。そんな空気がありました。選挙率が上がること自体は喜ばしいことです。でもその一方で、「なんとなく」の雰囲気や、名前を知っているからという理由だけで投票されてしまうことの安易さと意志の軽薄さも感じています。
選挙は「アイドルの人気投票」ではないですよね。
だからこそ、一人ひとりがちゃんと政策を読み、考え、調べ、自分の考えに近い人を選ぶという姿勢が必要なのだと思います。
今回の選挙は、自公が過半数割れするかも、という大方の予想が出ていて、ある意味、政権選択選挙のような意味合いも帯びています。
私個人は、与党と野党、両方に投票しました。
与党には、ただ自民党というだけでなく「この人なら」と思える政治家に。野党には「与党にしっかり意見できる存在」としての役割を期待して。バランスの取れた政治が大事だと思っているからこその選択でした。
私は自民党を全面的に肯定するつもりはありません。でも、政権を担う力のある人材が最も多くいるのもまた自民党であるとも思っています。ただ、だからこそ、きちんとした「正常化」が必要だと考えてもいます。多様な考えを内包する懐の深さを活かして、国の未来を見据えた政治をしてほしい。それを心から願っています。
「なんとなくいい感じだから」とか、「名前を知ってるから」とか、そんな理由で投票することは、やっぱり怖いことです。
選挙の一票は、単なる好感度ではなく、その人に「国の舵取りを託す」という意味を持つ。だからこそ、私たちは主権者として、責任を持って選ばなければいけないと思うのです。
自衛隊、防衛費、外交、憲法、経済、ジェンダー、文化…複雑でデリケートな問題が山積みです。でも「知らないから考えない」では、あまりにも無責任ではありませんか。何も変わらないのではありません。変えようとしていないだけかもしれません。誰かがやってくれる、私でない人の方がうまくやれるだろう。そんなことはよくある話です。でもどうでもいいやと投げるのではなく、あなたにお願いするね、とちゃんと意志のある方向性を持って手渡しすることが、政治にはあってもいいように思います。
情報はあふれています。だからこそ、情報を「選ぶ力」「見抜く力」が必要なんです。一人ひとりが、「今、自分はどんな時代に生きていて、どんな未来を選び取ろうとしているのか?」を、きちんと意識していきたいと私は思っています。
「カウンセラーがAIと対決してみた話」と「自民党にお灸を据えようとする選挙の話」

セッションを受けてくれたかたが
私のアドバイスの後、AIにも壁打ちした結果を報告してくれました。
「批判と悪口」の違いで人間性を見極めろ!

参院選が公示されました。物価高でインフレで、給料の額面は上がっても、税金取られて手取りは増えない。インバウンドで観光客が多いし、街を歩けば異国の人たちが目について、ちょいちょいトラブルの話も聞く。ここまで経済的に苦しいと感じるこの時期に、選挙に行こうと考えて、さてだれに投票しようかと思っている人もいらっしゃるのではないでしょうか?人間観察が好きな私は選挙大好きなんですが、そんな私が候補者を選ぶときに何を考えて選んでいるか?をお話ししてみようかと思います。
もちろん政治家を選ぶのですから、私はまずは人間性を見極めようとします。選挙戦中の演説や討論会などで、候補者が何を言っているか。特に批判や批評ではなく「悪口」を言っているかどうかをよく見るようにしています。政治の世界では意見の違いを表出し合って議論するのは当然です。でも、その言葉が「批判」ではなく、ただの「悪口」になっていると私はどうしても、気になって仕方がありません。選挙でネガティブキャンペーンは、戦略としてアリだと認識はしていますが、やはり悪口は聞いていて気持ちの良いものではありません。
「批判」と「悪口」の違い
「批判」と「悪口」、どちらも相手に対して否定的なことを言うことがありますが、その目的と中身は違います。
批判は、冷静に問題点を指摘して、より良い方向へ導くための意見。
悪口は、相手をおとしめたり、貶したりするための感情的なことば。
私が感じる違和感は、「批判」の顔をして「悪口」を言っていること。たとえば、「○○議員の政策は現実を見ていない」ではなく、「○○は嘘つきで根性が悪い、顔が変だ」と言ってしまうようなこと。それはもう、議論ではなくただの罵倒でしかありません。
そしてもう一つ、候補者を応援している人たちに共感できるかも、見極めるポイントかもしれません。「悪口」を言っている候補者に同調して、それを聞いて笑ったり拍手したりしている応援者がいることがありますね。応援すると言うことは彼らの意見や主張に共感するからなのだろうし、悪いことではありませんが、人として相手を貶めたりばかにするようなことに共感したり、ような自分はどうなのかと思い至ることはないのでしょうか。ただただ自分が応援している人を盲信することは、カルトの信者と同じです。私は「批判」は歓迎するけれど、「悪口」は嫌いです
誰かと意見が違ってもいい。建設的な「批判」や「批評」はとても大事だと思っています。異なる意見の中に、新しい可能性があると信じているからです。
でも、ただ人を貶めるための言葉──それがまかり通るような空気には、やっぱりどうしても賛同できません。そして平気で悪口を言う人がトップに立っている党を応援することもできません。
みなさんは、今回の選挙誰を応援し、誰に投票しますか?迷ったら「批判」と「悪口」の違い、気にしてみてくださいね。
あなたはなぜ7月5日の“大地震予言を信じたのか? 心理的考察と認知バイアス

2025年の7月5日。
SNSや動画配信の世界では、ある「予言」が話題になっていました。
「この日に大地震が起きる」
「外出は控えた方がいい」
「直感を信じて動かないで」
そんな文言が、まるで警告のように流れてきて、ちょっとドキッとした方もいらっしゃるのではないでしょうか。
私も、何人かから「どう思います?」と聞かれました。
私は地震が起きるとか起きないとか、そのこと自体よりも
「なぜあれだけ多くの人が、予言に注目したのか」
が気になりました。
未来が不確かだと、人はとても不安になります。
たとえば、いつ地震が来るか分からない、何が起きるか見通せない──そんな妙に落ち着かなくなった時
誰かが「〇月〇日に〇〇が起きます」と言い切ってくれると、
「怖いけど、備えられる」
「来るならその日に来ると分かってるほうが安心」
そのようにに思ってしまうんです。
これは心理学的に「不確実性の回避」と呼ばれる反応で、人間の自然な心の動きなのです。
不安に満ちた未来よりも、たとえ怖い未来でも、見通せる方がラクだと感じる。
そう考えると、「予言を信じる」のは人としての自然な反応なのかもしれません。
今回の予言のなかには、「関東で揺れが来るかも」とか、「震度5以上の可能性」みたいな曖昧な表現もありました。
こういう言葉は、当たったように感じやすいんです。
少しでも地震があれば「ほら当たった!」と思えますし、何も起きなくても「警戒してたから回避できたんだ」と納得できてしまう。
これは「バーナム効果」と呼ばれる心理現象で、誰にでも当てはまりそうな言葉を「私のことだ」と感じてしまうこと。
さらに、もともと信じたいと思っている人は、そういう情報だけを集めて、「やっぱり当たる」と思ってしまう。
これが「確証バイアス」と呼ばれる心理的な傾向です。
つまり、私たちの心には「信じたいように見る」仕組みが、そもそも備わっているんですね。
ここまで読むと、「やっぱり予言なんて信じるべきじゃない」と思われる方もいるかもしれません。
でも私は、ちょっと違う視点で見ています。
「信じたい」と思う気持ちは、とても人間らしいものだと思うんです。
それは「弱さ」に見えることもあるでしょうが、そもそも人はそんなに強いわけではありません。どんな時も安心したいし、快適で幸せな状態でいたいものですよね。なら、不安を回避するために、どんな形であれ自分本位に物事を捉えることがあるのも仕方がないことではないかと思います。
でも、もし「信じたい」が「信じ込まされる」に変わってしまったら——
一度、立ち止まってみることも大切かなと思うのです。
「信じたい」はあくまでも自分発信の気持ちですが、「信じ込まされた」ものを信じるのは他人軸になってはいないでしょうか?
他人軸で振り回されていると、それが間違っていた時や、自分の意にそぐわないものだと気付いた時、それは間違いなく他責になります。
自分じゃない、あいつのせいだ!ってやつですね。
そうなってしまうと、自分の間違いに気づくこともしにくくなりますし、自己保身のためにより攻撃的になってしまうことのありえます。
そうなったら内省からどんどん離れていってしまいますね。
予言でも、占いでも、スピリチュアルな言葉でも、信じたい理由があるはずです。それがぶれていないか?
自分の中にある「信じたい理由」を見つめることが、情報に振り回されないための小さなヒントになるように思います。
今回の“7月5日問題”は過ぎ去ろうとしていますが、
これからもきっと、「〇〇が起きるかも」という話題は定期的に出てくるでしょう。
そのとき、誰かの言葉に心が揺れたら、「私は、何のために信じたいと思ったのか?」を考えてみてください。
そして私たちはどんなことも
「自分の見たいようにみて聞きたいように聞き、感じたいように感じる」ことを忘れないでください。
人に振り回されるなんてこと、バカばかしいじゃありませんか。
記事を読んでくださって ありがとうございます