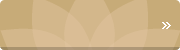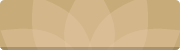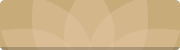読みやすい記事はちょっとした思いやりでできている

私は文章を書くときに、いつも気にかけていることがあります。
それは、「読みやすさ」。
パソコンで文章を打ち込むとき、
変換キーを押せば、いろんな漢字がぱっと出てきますよね。
普段、話し言葉ではよく使うけれど、
漢字にしてしまうと急に読みづらくなる言葉も、意外と多いものです。
これは、変換ありきで文章を打っていると、
つい見逃しがちなことだなぁと、最近改めて感じることがありました。
たとえば、「お咎め」。
(おとがめ)と読むこの言葉、
先日、あるブログで漢字表記で出てきたのですが、
私はふと立ち止まってしまいました。
「これ、なんて読むんだっけ?」
すぐに調べて「ああ、そうだった」と思い出したのですが、
そこそこ本を読む私でも、迷ってしまう瞬間があるんだなぁと、苦笑い。
もちろん、これは私の知識不足と言われれば、それまでです。
でも、人に読んでもらうための文章であるならば、
「一瞬でもつまずかせない工夫」は、とても大事なことだと思います。
もし私なら、
きっと「お咎め」とは書かずに、
ひらがなで「おとがめ」と表記するでしょうね。
私が良く使う「拘り(こだわり)」なんかも、そうですね。
漢字で書いた方が意味が引き締まる場面もあれば、
逆に、読み飛ばされたり、硬く感じられたりすることもある。
文語と口語。
文字と声。
その違いを意識しながら、どちらがふさわしいかを、
その都度、選んで表現したいと思います。
文章は、誰かに届けるものです。
「わかりやすさ」や「読みやすさ」は、
書き手から読み手への、思いやりだと、私は思うのです。
読みにくさも、もちろん時には表現の一部になり得ます。
でも、それは意図して選ぶものであって、無意識に押し付けるものではないと思います。
最近はAIを使用して文章を書かれる方も多いでしょう。
それが悪いことだとは思いません。
文章を整理したり、まとめたり、AIにサポートしてもらうことで新しい切り口の表現が生まれることもあると思うからです。
ただこの読みやすさや、自分らしい語り口になっているかは、最後ちゃんと出来上がった文章を読んで、手直しすることは大切ではないでしょうか。
自分が発信する内容が、自分らしくなかったら上手く書けていても、面白くはないと思うし、読み手にはそれがちゃんと感じられるものです。
読みやすさは思いやりですし、自分らしさは自分へのリスペクトです。
文章を書くうえで、私はこれらを忘れないようにしていきたいと思います。
-
 なぜ自民党に投票するのか? 〜天邪鬼な私が思うこと〜
本日のお話は「選挙」です。みなさん、参院選、行きましたか?我が家では「選挙は必ず行くもの」と決めていまして。先
なぜ自民党に投票するのか? 〜天邪鬼な私が思うこと〜
本日のお話は「選挙」です。みなさん、参院選、行きましたか?我が家では「選挙は必ず行くもの」と決めていまして。先
-
 石破総理が辞めない理由を心理的視点から考えてみた〜“言行不一致”は自己防御〜
参院選で自民・公明が過半数を割り込み、いよいよ政権への信任が揺らぎはじめているそんな中でも、石破総理は「辞任せ
石破総理が辞めない理由を心理的視点から考えてみた〜“言行不一致”は自己防御〜
参院選で自民・公明が過半数を割り込み、いよいよ政権への信任が揺らぎはじめているそんな中でも、石破総理は「辞任せ
-
 私が看護師を辞めたワケ
私が看護師を辞めたワケ - 思考のダイアロ
私が看護師を辞めたワケ
私が看護師を辞めたワケ - 思考のダイアロ
-
 ホスピタリティって何だろう?銀行窓口でカードを叩きつけられたらどうする
今日は八王子、珍しく曇り空。いやぁ、これがまた過ごしやすいのなんのって。太陽が隠れてくれているだけで、身体がふ
ホスピタリティって何だろう?銀行窓口でカードを叩きつけられたらどうする
今日は八王子、珍しく曇り空。いやぁ、これがまた過ごしやすいのなんのって。太陽が隠れてくれているだけで、身体がふ
-
 自分を変化させる勇気:ルック(見た目)は意志だ
ここ最近の私は、毎日せっせと国会中継を見ています。思想や感情は人それぞれ。しかし、丁寧に観察していると「政治
自分を変化させる勇気:ルック(見た目)は意志だ
ここ最近の私は、毎日せっせと国会中継を見ています。思想や感情は人それぞれ。しかし、丁寧に観察していると「政治