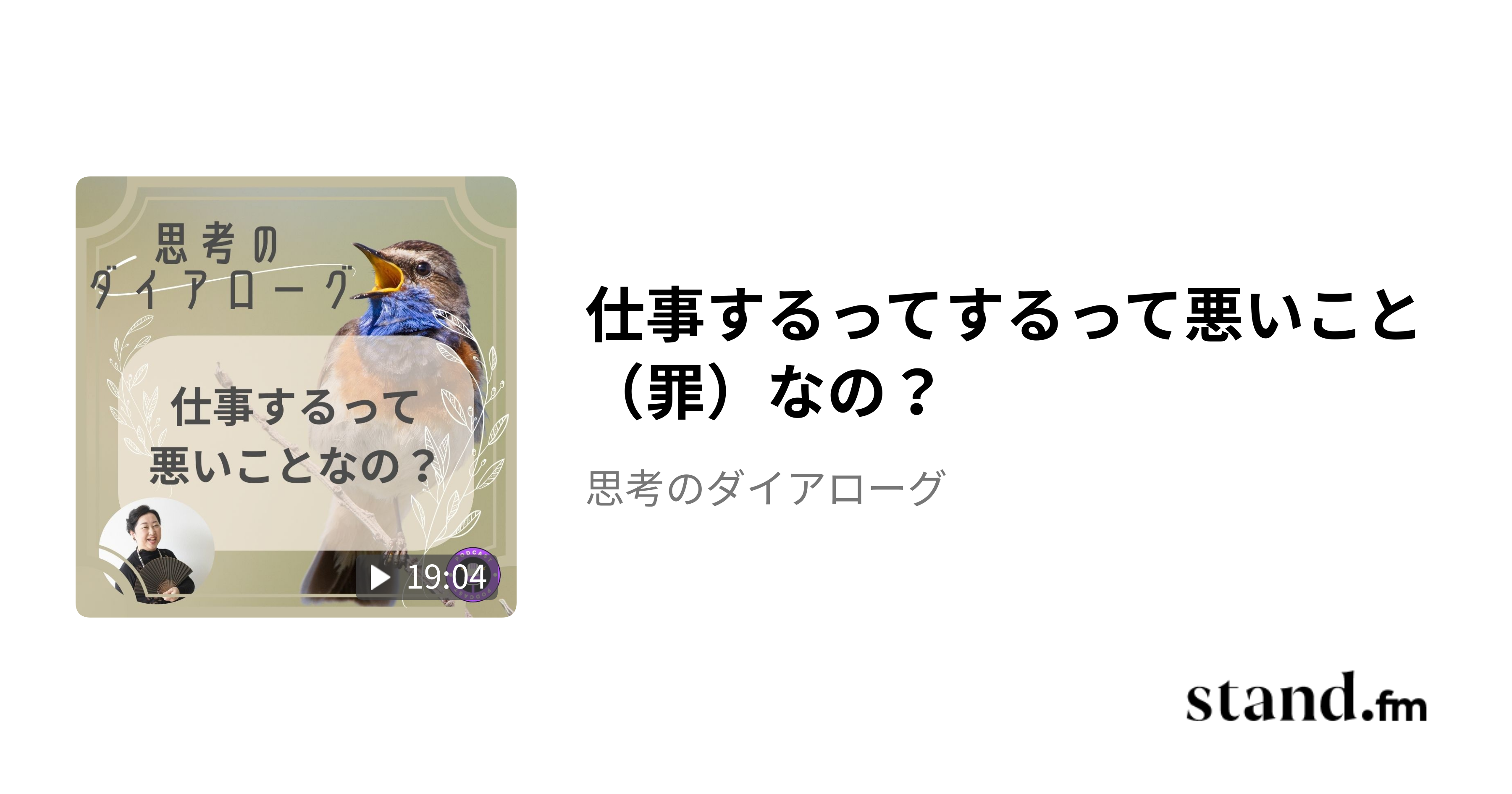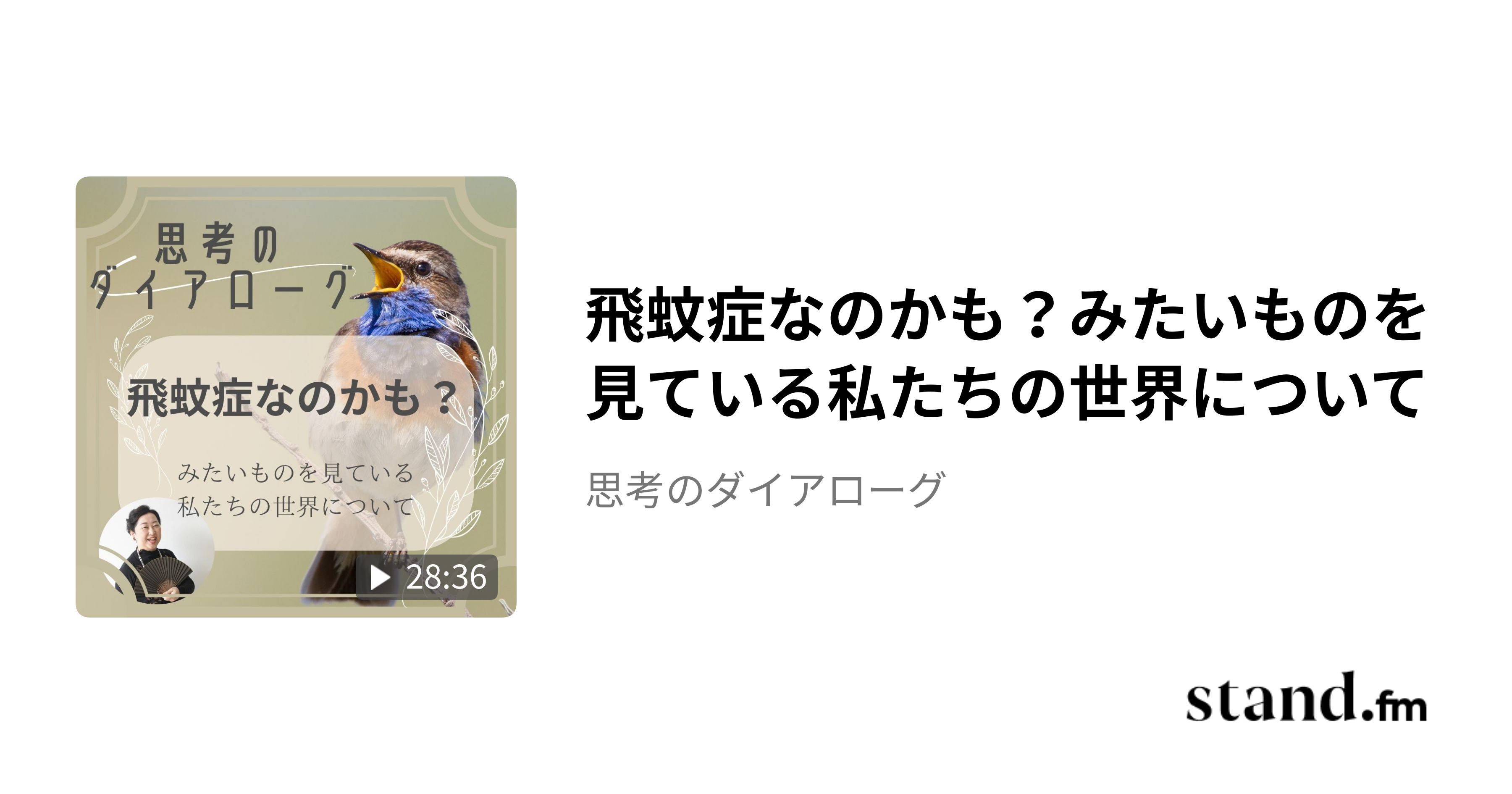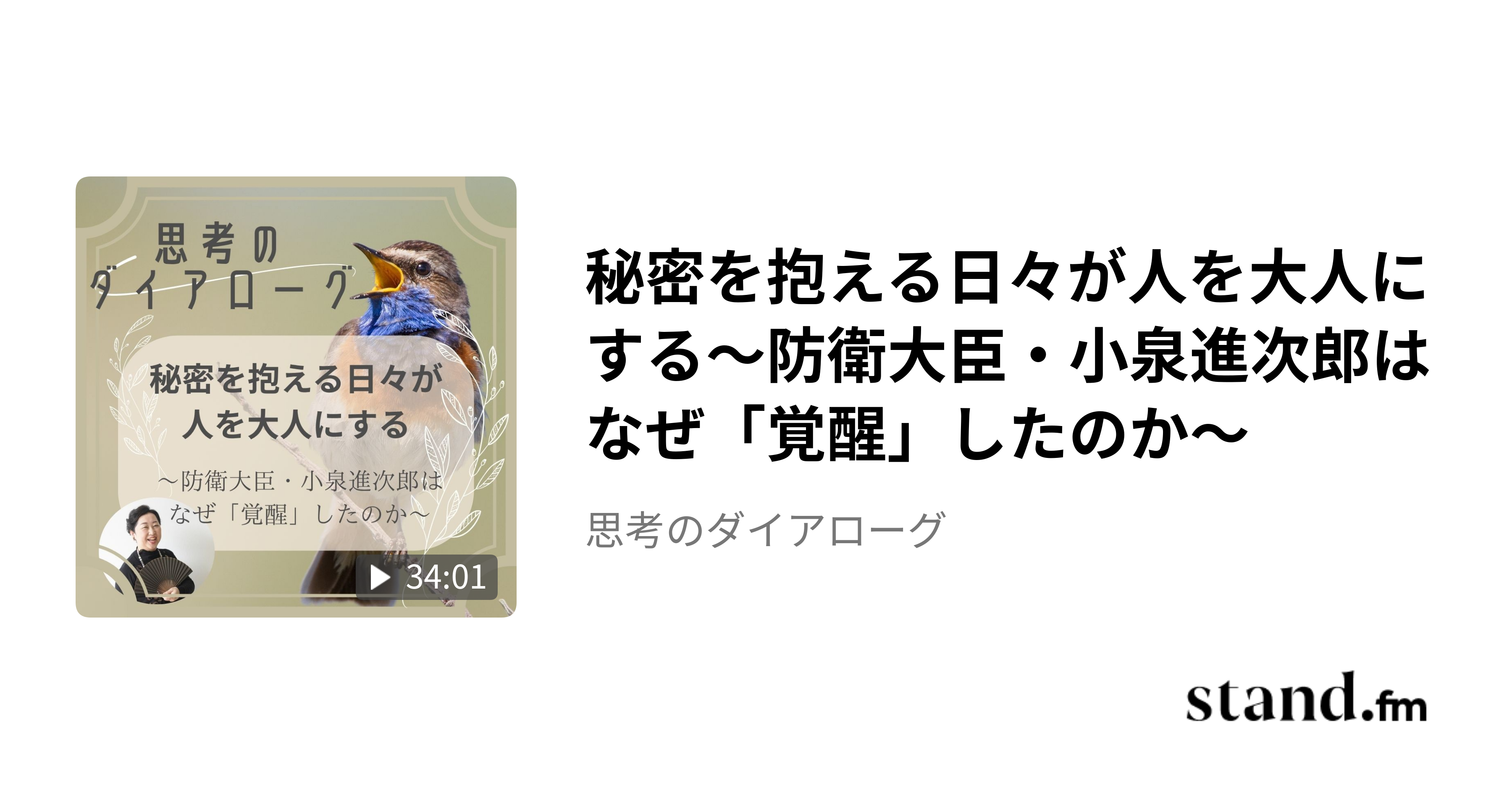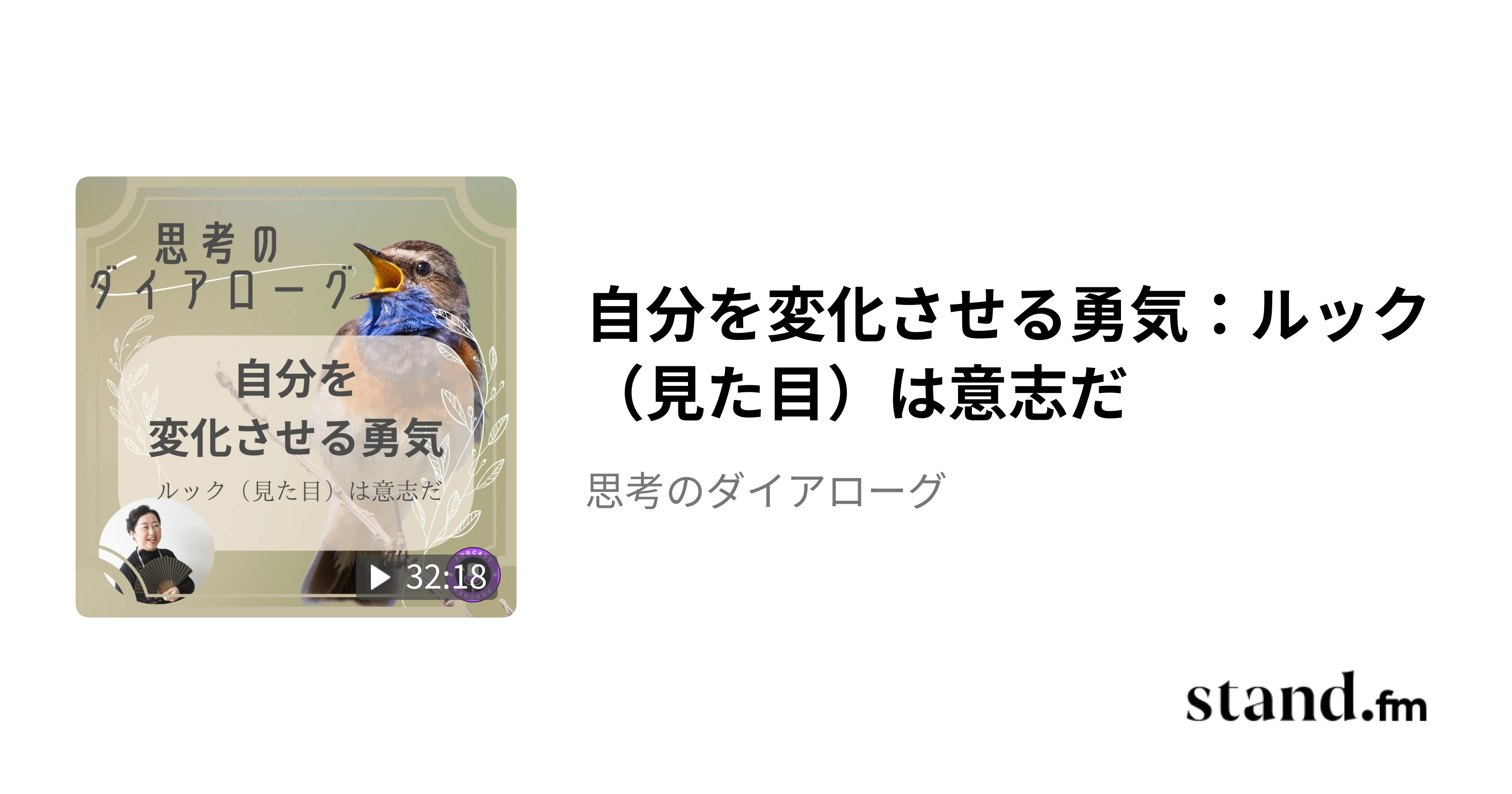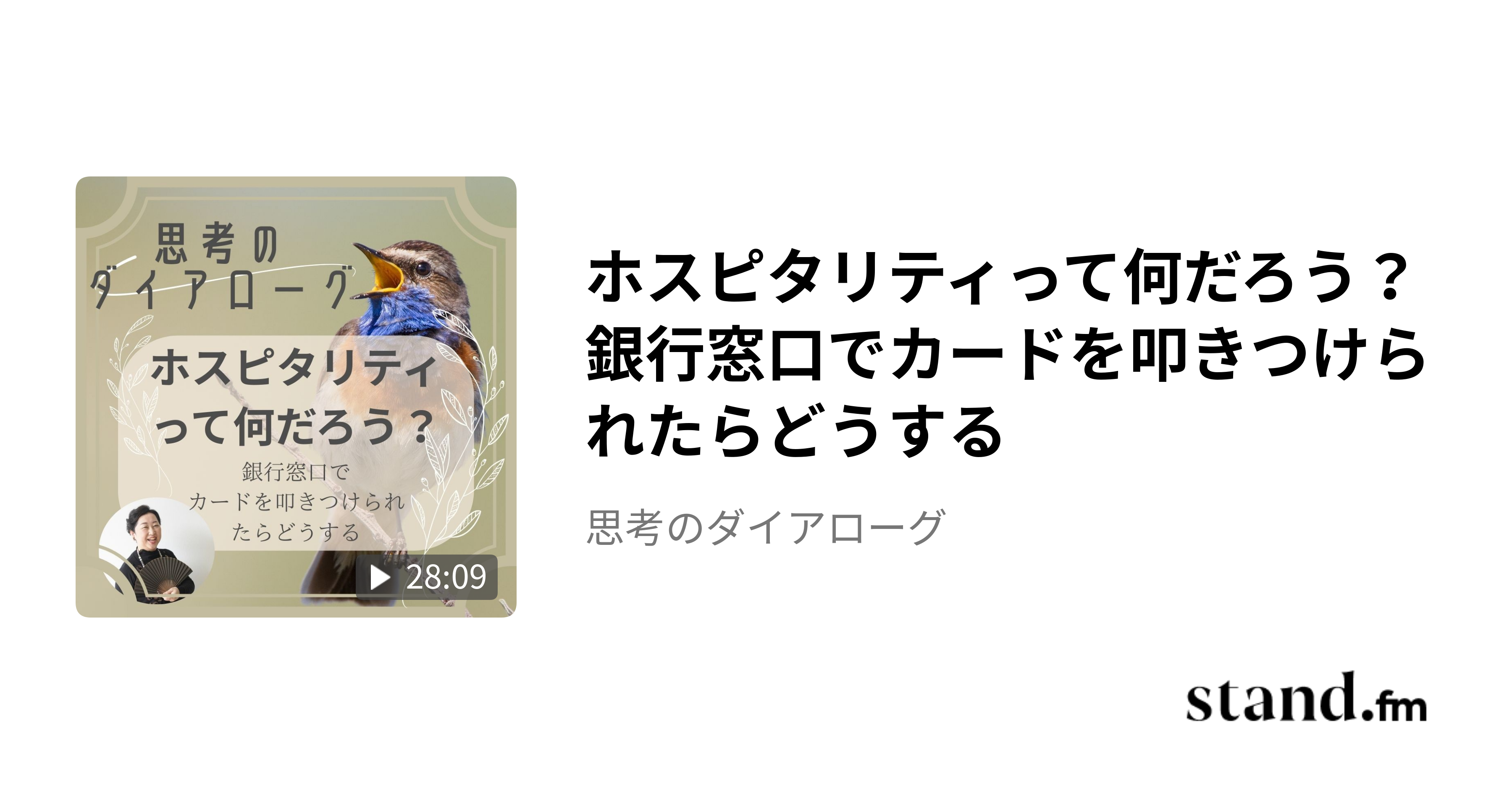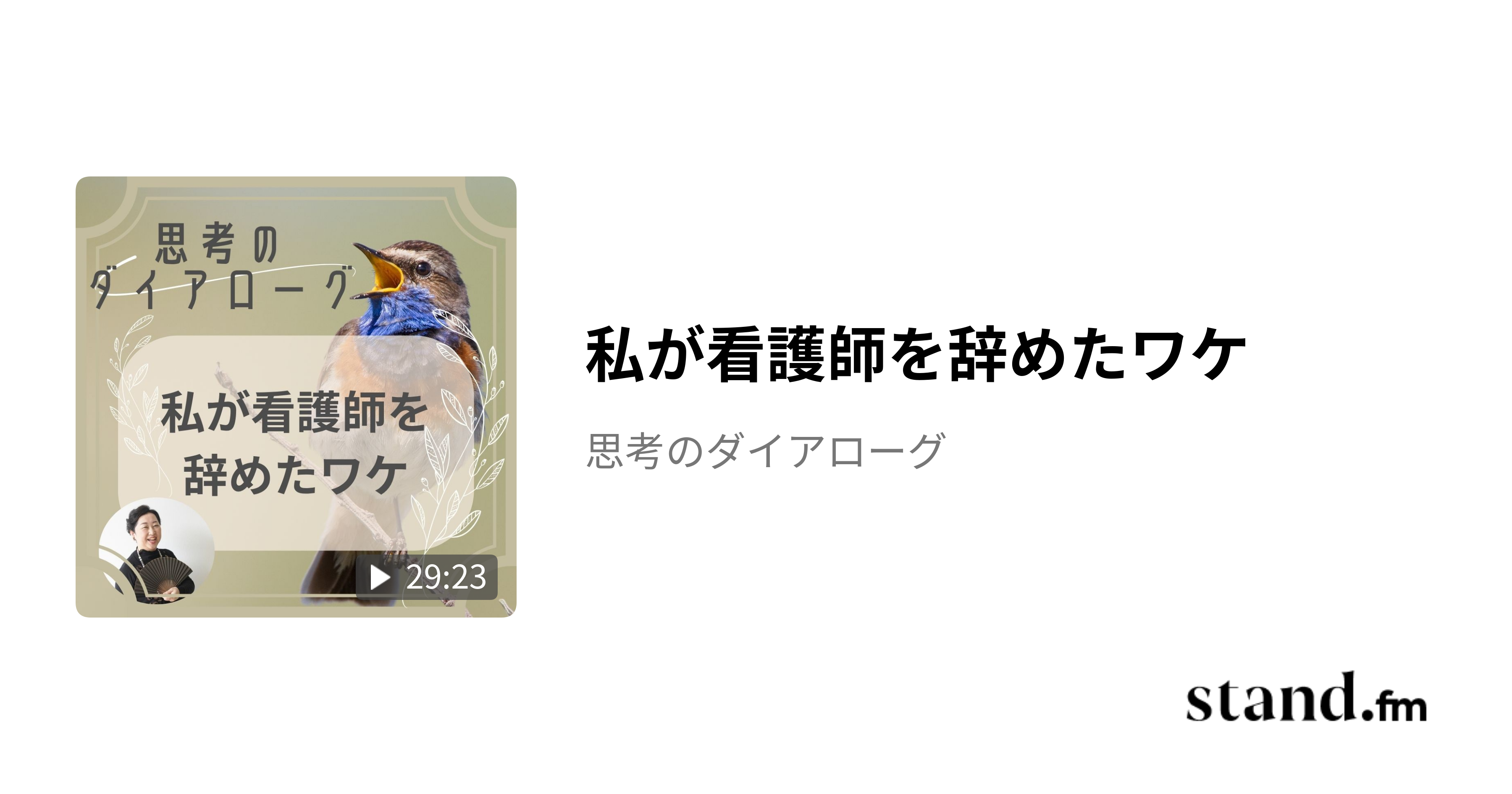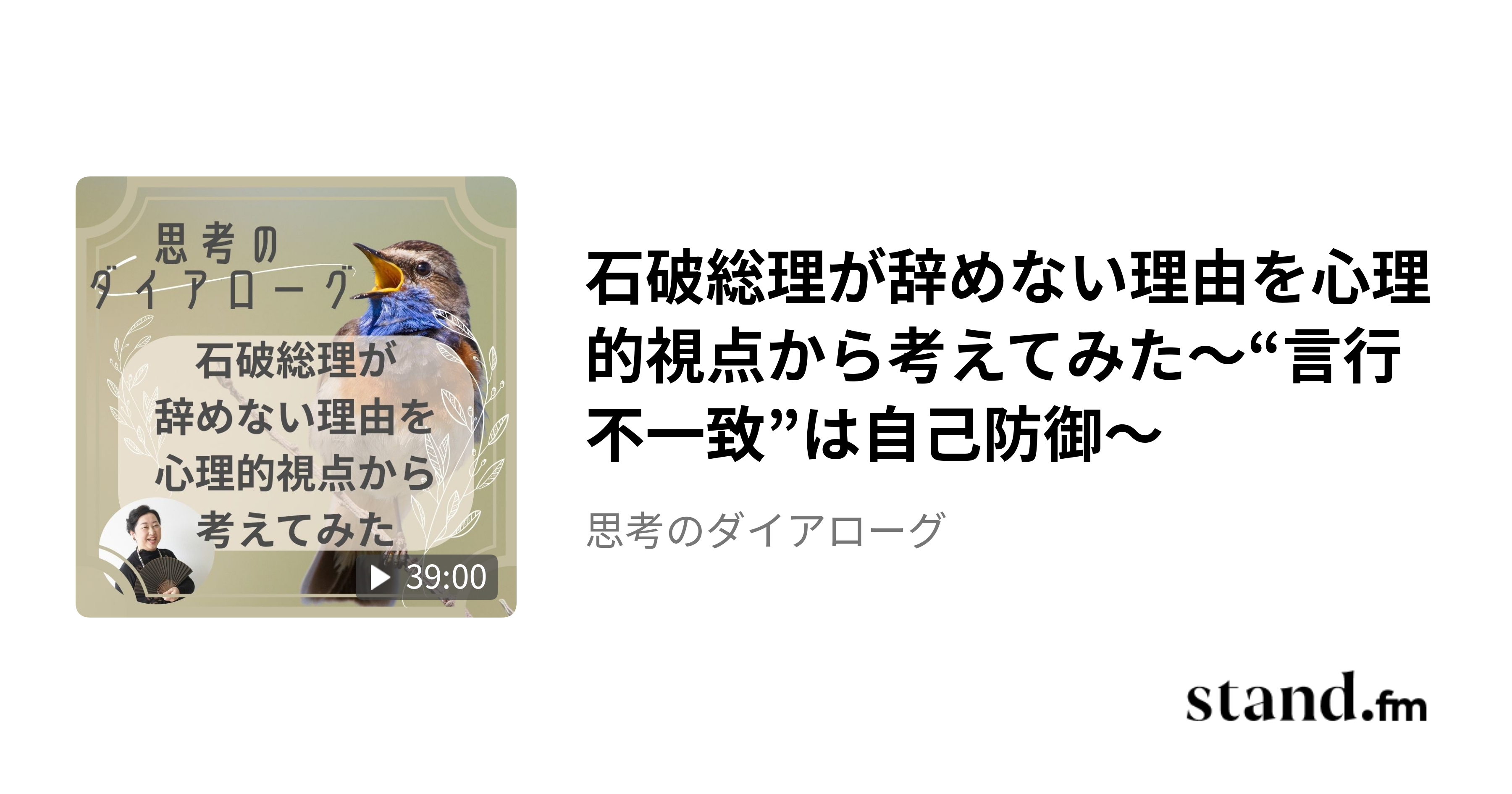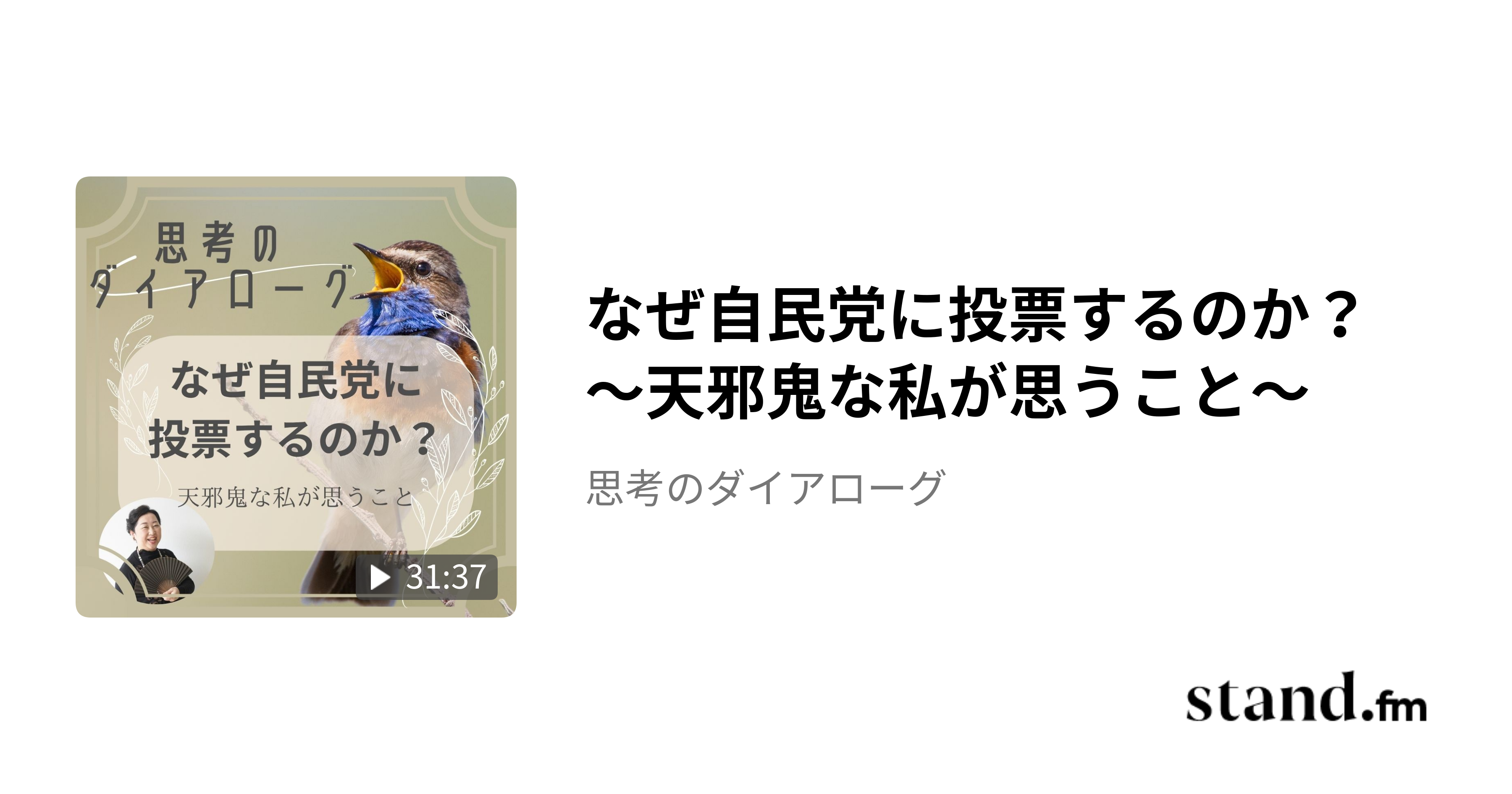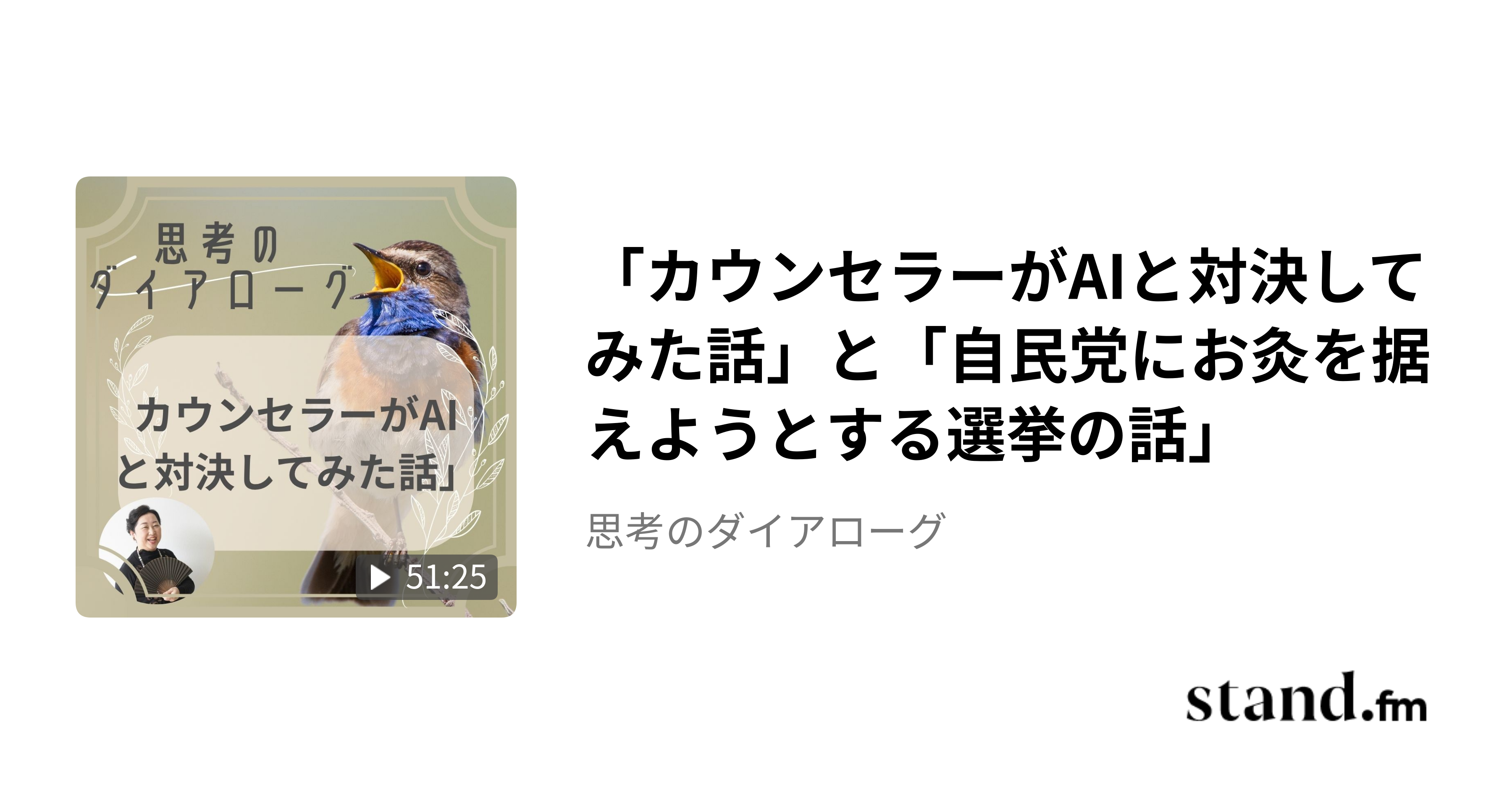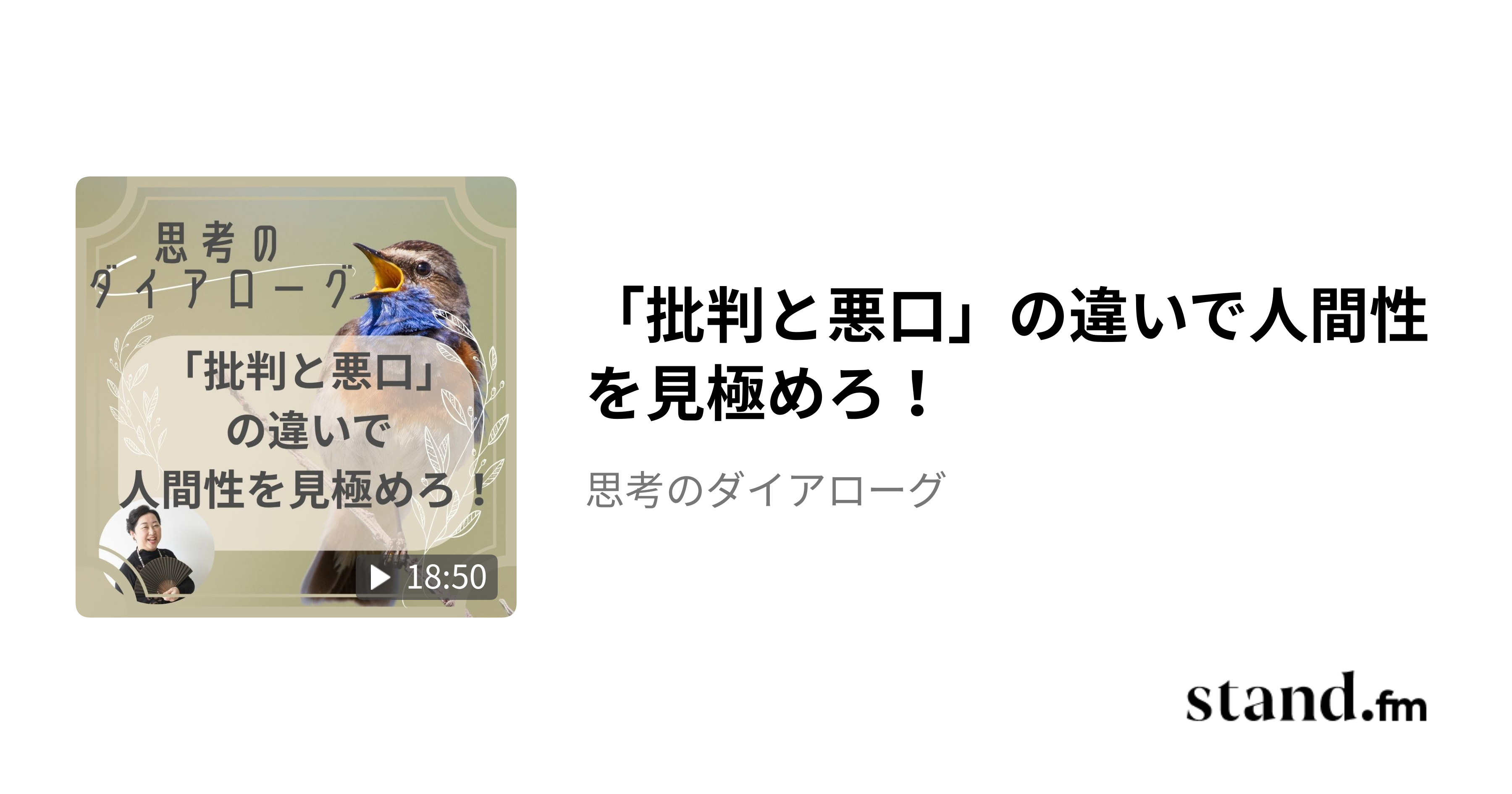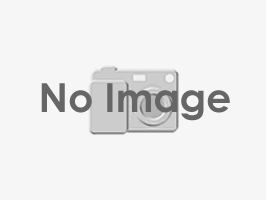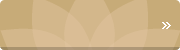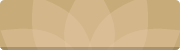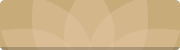雑感の智慧
- 仕事するってするって悪いこと(罪)なの?
- 飛蚊症なのかも?みたいものを見ている私たちの世界について
- 秘密を抱える日々が人を大人にする〜防衛大臣・小泉進次郎はなぜ「覚醒」したのか〜
- 自分を変化させる勇気:ルック(見た目)は意志だ
- ホスピタリティって何だろう?銀行窓口でカードを叩きつけられたらどうする
- 私が看護師を辞めたワケ
- 石破総理が辞めない理由を心理的視点から考えてみた〜“言行不一致”は自己防御〜
- なぜ自民党に投票するのか? 〜天邪鬼な私が思うこと〜
- 「カウンセラーがAIと対決してみた話」と「自民党にお灸を据えようとする選挙の話」
- 「批判と悪口」の違いで人間性を見極めろ!
仕事するってするって悪いこと(罪)なの?

本日のお話は、流行語大賞に選ばれた高市総理のあの一言について。食事中に夫がつけたテレビで受賞式の様子が流れていて、「あ、こんな場にも出てこられるんだ」と少し驚きました。総裁選での「働いて、働いて——働いてまいります」というフレーズ。もちろん、働き方をめぐる議論があるのは承知のうえで、私はあの言葉を“誰かに強いる宣言”ではなく、「まず自分がやる」「仲間を鼓舞する」という決意の言葉として受け取りました。言葉は切り取り方ひとつで印象が変わります。人は見たいように見て、聞きたいように聞くもの。だからこそ、「この人はそう捉えたのね。では私はどう感じる?」と、自分の視点を持ち直すことが大切だと思います。
ここからは“働く”という行為の話。ドラマ『アンナチュラル』に、「なんで働くんですか?」という同僚の質問に法医学者の主人公が「美味しいものを食べるためかな。生きるために仕事してる」と答える場面があります。「イタリアでは労働は罪なんだって」というセリフにもドキッとしました。私は看護師として働いてきました。仕事が大好きで、大変なことももちろんありましたが、充実していました。仕事が心底おもしろかったのを思い出します。担当の患者さんの向こう側に、チーム、病棟、病院全体の動きが見えはじめて、自分の働きが誰かの役に立っている実感が生まれたとき——あれは喜びでした。私にとって労働は“罪”ではなく、生き甲斐とプライベートの自由を得るためのものです。仕事をすることでその労働に対しての対価が生まれ、その対価が自分や家族の暮らしを支える。その循環に、私は自分の“ちょうどよさ”を感じます。
もちろん、過労は問題です。心身を壊すほどの働き方は、どこかで「やめる」「逃げる」と決めていい。やらされるだけの働き方から距離を取り、やると決めたら腹を括る。そのバランスを学ぶのが、社会と自分との健全な付き合い方なのだと思います。だから私は、「働くこと=悪」でも「休むこと=悪」などと一括りにするのは違うと思います。人にはそれぞれのリズムがあり、支え合える関係があれば、がんばる人にも、いったん緩める人にも、それぞれのやり方が尊重される必要があると思います。。
高市総理の言葉を私は、“決意表明”として受け取りました。実際どこまでやれるのか、やって見せてください——そんな素直な期待もあります。私自身は、働くことにはポジティブなイメージを持っています。働くとは、世界と自分をたがいに支え合う、エネルギーの循環の一つではないでしょうか。
働くことは、あなたにとって何ですか?罪でも罰でもなく、あなたがあなたとして生きるための方法なのだとしたら、今日をどう過ごしますか?がんばる時間、緩める時間、その間にある静かな余白。それぞれの“ちょうどよさ”で、プライベートと仕事をつないでいけたらいいですね。
飛蚊症なのかも?みたいものを見ている私たちの世界について

ここ1か月ほど、朝起きると視界に黒い点がいます。目を動かすと、点も“ぷいーん”と付いてくる。以前も疲れたときに数日だけ現れては消えたのですが、今回は定住なさっているご様子。
「これは世にいう飛蚊症(ひぶんしょう)かしら?」と思ったわけですが、私は糖尿病があるので、いちばん怖いのは網膜の出血。放っておけば視野欠損や失明につながることもあるので、コレは違うと思いつつまずは診断が大事ですから、今回はサッと眼科受診へ向かいました。
瞳孔を開いての検査、眼底カメラ、視力・眼圧、CTなどフルコースでチェックしていただきました。結果は眼底に出血なし。ひと安心。先生からのレクチャーがとても分かりやすかったので、素人メモとして共有します(用語はざっくり)。
目の中には硝子体(しょうしたい)というゼリー状の物質が詰まっています。
若いときは“ぷるぷる”ですが、加齢でサラサラ化(液状化)してきます。
動くたびにゼリーとゼリーを包む膜がゆらゆらし、微小な濁りや繊維が網膜に影を落とす——これが飛蚊症として「虫や糸が見える」感覚になる。
加齢変化なので、ゼリーを“元のぷるぷる”に戻す治療は基本ありません。
つまり、コレは加齢による変化なわけで、病的な出血ではないと確認できたなら黒い点=いま可視化されている私の一部ということです。病的な出血ではないと確認できたなら、付き合い方を決めるのが次のステップです。
※赤い稲妻のような光が走る(光視症)、黒い幕がかかったような視野の欠け、急に数が増えた——こうした変化があれば至急受診が安心です。
人間の耳や目は情報をぜんぶ集めて、脳が取捨選択しています。雑踏の中でも友人の声が拾えるのは、そのため。黒い点も同じ。注視すれば、ずっと気になる。でも「自分はどこにピントを合わせるか」を決めることはできる。
私はこう決めました。「黒い点も私。あるけれど、世界のほうにピントを合わせて生きる」。点は点として受け入れ、視界全体を見にいく。すると、不思議と心も広がります。
白髪や白内障と同じく、飛蚊症も加齢のサイン。私の体には、めまい、寝姿勢の制約、肩の痛み(たぶん五十肩)など見守り案件がいくつも常駐しています。健康なときには要らなかった配慮や工夫が、今は必須です。
医療の現場では、「完治」よりも寛解という考え方があります。私にとってのキーワードは、“良くする”より“ちょうどよくする”。薬や生活を乱暴にいじらず、いまの安定をキープする——そんな選択が最善の日もあるのです。
秘密を抱える日々が人を大人にする〜防衛大臣・小泉進次郎はなぜ「覚醒」したのか〜

本日の話は、最近よく耳にする「小泉進次郎さん、覚醒した?」という噂について。これは私が日々の観察とセッション経験から感じた個人的な考察=ほぼ独り言です。事実の断定ではなく、「この人、こうなんじゃない?」という読み物としてお楽しみください。
“軽い”“中身が見えない”“軽い神輿は担ぎやすい”など今まで小泉さんには、そんなあまり良いとは言えない評価があったように思います。私もあまり良い印象はありませんでした。見た目の華やかさや立ち振る舞いの良さはある。でも、「政治家として何を成し遂げたいのか」「どの場面でどこまで腹を括るのか」が見えにくかった。日本人はイメージに振り回されやすい国民性もあるからこそ、私はずっと不安だったのです。
ところが最近の記者会見や、予算委員会の質疑でカメラが抜かれるたびに思うのは、表情が変わったということ。ドヤ顔ではない。けれど、目が座っている。短い言葉の端々に、曖昧さではなく「責任の重さに触れている人の体温」を感じるようになったのです。
防衛大臣は、日々のブリーフィングで“言えない情報”に触れ続けます。
日本周辺の海や空で何が起きているか
それにどう対処しているか
どこまでが公表でき、どこからが機密か
日本の防衛の観点から、他国からさまざまな侵犯があるのにそれらの情報は機密だから国民に言うわけにはいかない。だが、もしものことがあれば決めねばならないし責任も取らなければならない。この矛盾を抱えながら、淡々と判断を積み重ねる日々は、人の内側に忍耐と芯を育てるのだと思います。「守る」と決めて、黙って耐える。ここに“軽さ”が入り込む余地はありません。
小泉さんは横須賀の地で育ち、国防が暮らしの近くにある環境にいた人。それでも、実務の最前線の温度に触れるのは大臣になってからです。生活の延長線上に“現場の重さ”が直に乗ってくるとき、人は初めて自分の言葉を持ち始める。私はその瞬間を見ている気がしています。
「覚醒」とは突如の変身ではなく、内在していた資質が“場”によって育つことなのではないでしょうか。言えないことを抱え、耐え、なお決める。その繰り返しが、子どもっぽさを削り、大人の輪郭をつくる。私はそこに、人が変わるプロセスがあると思います。
結局、私たちの生活も同じなのではないでしょうか。
・どう生きたいかを意思にする
・そのために何を決めるか明確にする
・決めたらやる(言い訳を減らし、行動で積む)
この三点セットを回し続ける人は、静かに強くなる。
人間性が整っていくと申しましょうか、これさえやっとけばなんとかなるような気さえします。
「覚醒したの?」と聞かれれば、私はこう答えます。はい。“内在していたものが、仕事によって成熟に向かっている”のだと。そして、その成熟は特別な人だけのものではなく、私たちの日々の選択の中にも、確かに芽生えうるのではないかとも思えます。誰にだって怒ることです。役割が人を育てると言う人もいますが、彼の場合はまさにそうなのでしょう。そしてその役割を与えた高市首相はマネジメントとして、腕利なのかもしれないと思わざるを得ません。
これからの小泉進次郎さんの変化から目が離せません。楽しみが増えましたね。
自分を変化させる勇気:ルック(見た目)は意志だ

ここ最近の私は、毎日せっせと国会中継を見ています。思想や感情は人それぞれ。しかし、丁寧に観察していると「政治って生活のすぐとなりにある」そんな肌感があります。
とりわけおすすめは、今行われている予算委員会。総理への代表質問よりも各大臣への具体的な質疑なので、各議員の切り口や準備力、そして大臣の現場感が見える。いわば“素の実務”が顔を出す場面が多いから、見ていておもしろいんです。キャラクターも見えてくるし、見応えがありますよ。
良いところも悪いところもある。それでも長く政権を担ってきた与党には、保守からリベラルまで幅の広さと、人材の厚みがあるのも事実。(いっとくと、自民党は基本保守政党ですからね)実務は官僚が回すけれど、決めるのは政治。大臣だけでなく、副大臣や政務官、委員会のポスト、そして山ほど必要な“現場の手”があって初めて動く。だからこそ、与党側に“主導できる優秀な人”がどれだけいるかは、やっぱり大きい。もちろん間違いもあるし、ダメダメな人もいるので、だからこそ野党の追及が必要だし、選挙で誰を選ぶかっていうのが大切なんですよ。
ここからは私の“推し語り”。私はずっと高市さんを応援してきました。今回の総裁選、ふと気づいたんです。——高市さんメイクが変わった。眉、リップ、前髪。強さを前面に出す“昭和的きりっとメイク”から、少しエッジを落としてしなやかな強さへ変化しましたよね。「信頼感」が増したように感じました。女性なら「あ、変えたな」って、説明できなくても感覚で分かる変化でしたよね。
男性陣が「変わったの?どこが?」と言っているのも見かけました。いや、そこなんです。女性の観察眼は、生活の中のコミュニケーションと直結している。相手の小さな変化をキャッチして言葉にすることで、距離を縮め、心を汲む。だから、メイクや所作の変化は“決意の言語化”にもなる。そう、ルックは意志なんですよ。
歴代の総理の誰かが言っていました。「総理は明るい方がいい」。なぜか? 希望が連鎖するから。変化の初速はいつも期待で生まれる。期待が現実に落ちていくには時間がかかるけれど、その間を支えるのがリーダーの“明るさ”なのではないでしょうか。明るさは決して軽さではありません。信頼に裏打ちされた前向きさのこと。高市さんのルックの変化から、私はその「明るさを伴う覚悟」を確かに受け取った気がしました。
それに加えてこれは私の原体験なのですが、子どもの頃日本舞踊を習っていて、先生に何度も言われたのが「腰を入れなさい」ということ。腰が座らないと、所作はすべてぶれる。立つ・座る・振り向く。どの一挙手一投足にも芯が通らない。芯が定まれば、動きはなぜか上品に、美しく見える。政治家の“目の力”や“立ち姿”を見ていると、この「腰=芯」を思い出すんです。人は何かをつかんだ瞬間、目にぐっと力が宿る。あれは誤魔化すことができないものです。そんなものも感じました。
人は変われる。諦めないこと、手放すこと
私の特技は「諦めない」ことだと自分で思っています。握りしめすぎて見えなくなりそうなときは、そっと脇に置く。でも、手の届くところに置いておく。ある日ふっと点が線になって、「あ、これかもしれない」と腑に落ちる。そのとき必要なのは、自分を変化させる勇気。手放す・受け入れる・やり尽くす。高市さんのメイクチェンジに、私はその覚悟を見ました。外見の調整は、内側の決意の反映なんですよ。
メイクひとつ、姿勢ひとつ。そこに芯が通ると、見る景色が変わる。政治も、仕事も、家庭も同じ。私たちは日々、小さな選択で自分をつくっています。変化を恐れない。変わるなら何はなくとも勇気が必要です。諦めないで、まずは自分の見た目の変化から取り掛かるのもありかもしれませんよ。
ホスピタリティって何だろう?銀行窓口でカードを叩きつけられたらどうする

今日は八王子、珍しく曇り空。
いやぁ、これがまた過ごしやすいのなんのって。
太陽が隠れてくれているだけで、身体がふっと楽になるんですよね。
ここ1週間、10日くらいずっと灼熱続きで、雨も一滴も降らず。ニュースではゲリラ豪雨の映像が流れているのに、うちのあたりはカンカン照り。車の中でも、家の中でも、あの太陽光線と紫外線にじりじり攻められる感じ。暑いとかいう次元を超えて、身体の芯までやられてしまう。
私はもともと体調不良持ちですから、太陽を避けて、どうにかこうにか日々をやり過ごしていたんです。熱が体にこもると下がらなくなって、そうなるともう眠れない。不眠に拍車がかかって、ただでさえ夜中にトイレで起きるのに、細切れの睡眠すら奪われて、ほんと、地獄のようでした。
だから今日の曇りはまさに「雲さまさま」。青空は好きだけど、続きすぎるとしんどいこともあるんですよね。
さて 事件です
そんな中、用事があって銀行に行きました。最近はネットで手続きができることがほとんどで、窓口に行くのなんて滅多にないんですけど、今回は「解約」と「再登録」が必要で、どうしても本人確認がいる手続き。仕方なく足を運んだんです。
最初はコールセンターに電話をして準備をしました。これがとても丁寧でありがたかった。必要な書類や持ち物をきちんと教えてくれて、「あぁ、助かった」と思いました。私はね、気持ちのいい対応をしてもらったときは必ず「良かったです」と本部に伝えるようにしているんです。クレームは世の中にあふれているけど、褒め言葉こそ人を支える力になると思うので。
さて、問題はその後の窓口。
最初に対応してくれたのは、年齢も近そうなベテラン風のAさん。少し不慣れな様子もありつつ、一生懸命で丁寧な方でした。
そのAさんが確認に行ったのが、若くてキリッとしたBさん。明らかに仕事ができるオーラをまとった人。でも、その「できる感」が裏目に出ていたというか、Aさんに指示を出すときの態度や雰囲気にイライラが滲んでいたんです。
手続きの途中で、私の古いキャッシュカードが問題になりました。ICチップが入っていないから暗証番号での確認ができない、と。なるほど仕方ないことだとは思います。
でもね、そのときのBさんの動作。
カードをトレイから持ち上げて、「これじゃダメです」と言いながら、パンッとトレイに叩きつけたんです。
その音を聞いた瞬間、正直カチンときました。
だって、それは私が長年大事に使ってきた銀行のカード。つまり、ずっとその銀行を使い続けてきた客の証でもあるわけですよね。それを、軽くとはいえ叩きつける? それは違うんじゃないか、と。
その場で立ち上がって、「ちょっと、それは失礼じゃないですか?」と声をあげそうになったけれど、やめました。もし私が強く言えば、矛先がAさんに向かうような気がしたからです。怒りを処理できない人って、自分より弱い立場に向けてしまうことがあるじゃないですか。
だからこそ、逆に人間観察をしてしまいましたよ。
Bさんはお客(ワタシ)に怒りをぶつけられない、かといって自分で消化もできない。それが態度や手癖に現れてしまった。つまり「思いやりの想像力」が働かなかったんだと思うんです。
ホスピタリティとはなんぞや?
この出来事から改めて考えたのは「ホスピタリティ」ってなんだろう、ということ。
ホスピタリティとは、相手を大切に思う心が自然に行動に表れることだと私は思います。
特に銀行やホテルのように「信頼」で成り立っている場所では、安心感を与えることが何よりも大切です。
もちろん人間だから、体調が悪いときやイライラするときはある。だけど、それを仕事中にコントロールできなかったら──少なくとも「一期一会の場」である窓口や接客業では、大きな問題になってしまう。
人の思いは行動に出る。だからこそ、相手に見せてはいけない一瞬の感情というものがあるならそれはどんなに小さくても出してはならないのではないでしょうか。
人が人を思う
私自身、感情がすぐ顔に出てしまうタイプです。
嘘をつくのも下手。
だからこそ、仕事では緊張感を持って、出す表情と出さない表情を選んでいます。
でも日常ではなかなか難しいこともあります。気が緩んでますから、つい本音が滲んでしまう。
人が人を思う心は行動に出るものです。
ホスピタリティとは、その「一瞬の反応」まで含めて、相手に安心と信頼を与えられるかどうかがキモになると思います。
今日の銀行での出来事を通して、あらためて自分にも問いかけました。
「自分は、相手を大切にできているだろうか?」
「感情に振り回されていないだろうか?」
ホスピタリティは特別なスキルではなく、人としての思いやりの延長線上にあるんだなと、曇り空の帰り道にしみじみ思いました。
記事を読んでくださって ありがとうございます
私が看護師を辞めたワケ

石破総理が辞めない理由を心理的視点から考えてみた〜“言行不一致”は自己防御〜

参院選で自民・公明が過半数を割り込み、いよいよ政権への信任が揺らぎはじめている
そんな中でも、石破総理は「辞任せず、政権の立て直しに全力を尽くす」と続投を表明しました。
一見すると、強い覚悟。
けれど、「え?それって矛盾してない?」という感情です。
なぜなら、かつて石破氏は、他の総理に対して選挙の敗北を理由に辞任を促してきた人だったからです。
その姿勢に信頼や期待を寄せていた人も少なくないはず。
それなのに、自分が総理の立場になったとたんに、かつて自分が他人に求めていた「けじめ」をつけようとはしない。
この姿勢は、一体どう理解すればいいのでしょうか。
言っていたことと、やっていることが違うとき
私たちも日常の中で、「あれ?この人、前と言ってること違わない?」と感じる瞬間があります。
政治家だけでなく、上司や親、パートナーや自分自身に対してさえ、そんな違和感を抱くことはあります。
心理学では、こうした「言ってることと、やってることが噛み合っていない状態」を
認知的不協和(cognitive dissonance)と呼びます。
人は、自分の言動に矛盾があるとき、強い不快感や葛藤を抱きます。
そしてその矛盾を解消するために、さまざまな「理由づけ」や「例外」を作り出すのです。
たとえば石破総理がこう考えていたとしたらどうでしょう。
「今回の敗北は政権への不信ではなく、選挙区事情や候補者の問題」
「過去と今とでは状況が違う。今は自分が立て直すしかない」
「辞めることは責任ではない。残って全うするのが本当の責任」
この理屈は一見、筋が通っているように見えます。
しかしこの筋の通り方は、あくまで石破総理自身の正当性を誇示するための自分勝手なご都合主義の筋であり、彼のリーダーとしての責任を取るであったり、状況や役割に則った筋ではないように思えます。
人は、自分の矛盾には鈍感になりやすい
これは石破総理だけの問題ではありません。
私たち人間は基本的に、「自分の矛盾には寛容」で、「他人の矛盾には厳しい」傾向があります。
かつて「政治家は潔く辞任すべきだ」と語った彼の言葉は、ある意味、正論でした。
でもその正論は、いざ自分が当事者になると、「状況が違う」「今は特別だ」と、例外扱いされてしまう。
そして私たちの信頼は、この“言行不一致”に最も敏感に反応します。
信頼とは、過去の言葉と今の行動の重なりの上にしか成り立たない。
それが、政治であれ、家庭であれ、どんな関係でも変わらない真理なのだと思います。
石破総理の「辞めない」という選択は、もしかすると本人なりの責任感かもしれないと取ることもできます。。
しかし、今は「かつての言葉」と「行動」に追いかけられ、刺されていると言えます。
自己矛盾を孕んで発せられる言葉は、自分をも騙し、他者の信頼を大きく損ないます。自分を騙し始めたら、軸も正義も大きく捻じ曲がっていくと私は思います。
石破さんは何をみて何を守ろうとしているのでしょうか?
政治は国民の安らかな生きる世界をつくり、それを守るためにあるのではないですか?
自分を守るために自分都合を正当化するのは、総理のやることではないように思えます。心を取り戻して欲しいと思ったりしてしまいます。
記事を読んでくださって ありがとうございます
なぜ自民党に投票するのか? 〜天邪鬼な私が思うこと〜

本日のお話は「選挙」です。みなさん、参院選、行きましたか?
我が家では「選挙は必ず行くもの」と決めていまして。先ほども、暑い中、主人と一緒に投票に行ってまいりました。
選挙は、私にとって「大事な権利を行使する日」。息子たちが高校生だった頃から、「自分の一票を無駄にしないように」と伝えてきました。選挙権が18歳に引き下げられたあの年、高3の長男が初めて投票所へ。その翌年は次男も。家族4人で車に乗って、小学校の投票所へ向かい、投票を終えたらラーメンだの、うどんだの、焼肉だの…好きなものを食べて帰ってくる。
そんな“選挙の日の外食”が、ちょっとした家族のイベントになっていたんですよね。今は息子たちも独立し、別々に暮らしていますが、きっと彼らも、変わらず投票に行っていると思います。
今日、投票所に行ったら、いつもより人が多くて驚きました。なにせ八王子は自民、公明のガチガチの保守地盤。年配の方が多い印象ですが、今回は小さなお子さんを連れた若いご夫婦もたくさん見かけました。
「このままじゃいけない」と思った人たちが、重い腰を上げて足を運んだ。そんな空気がありました。選挙率が上がること自体は喜ばしいことです。でもその一方で、「なんとなく」の雰囲気や、名前を知っているからという理由だけで投票されてしまうことの安易さと意志の軽薄さも感じています。
選挙は「アイドルの人気投票」ではないですよね。
だからこそ、一人ひとりがちゃんと政策を読み、考え、調べ、自分の考えに近い人を選ぶという姿勢が必要なのだと思います。
今回の選挙は、自公が過半数割れするかも、という大方の予想が出ていて、ある意味、政権選択選挙のような意味合いも帯びています。
私個人は、与党と野党、両方に投票しました。
与党には、ただ自民党というだけでなく「この人なら」と思える政治家に。野党には「与党にしっかり意見できる存在」としての役割を期待して。バランスの取れた政治が大事だと思っているからこその選択でした。
私は自民党を全面的に肯定するつもりはありません。でも、政権を担う力のある人材が最も多くいるのもまた自民党であるとも思っています。ただ、だからこそ、きちんとした「正常化」が必要だと考えてもいます。多様な考えを内包する懐の深さを活かして、国の未来を見据えた政治をしてほしい。それを心から願っています。
「なんとなくいい感じだから」とか、「名前を知ってるから」とか、そんな理由で投票することは、やっぱり怖いことです。
選挙の一票は、単なる好感度ではなく、その人に「国の舵取りを託す」という意味を持つ。だからこそ、私たちは主権者として、責任を持って選ばなければいけないと思うのです。
自衛隊、防衛費、外交、憲法、経済、ジェンダー、文化…複雑でデリケートな問題が山積みです。でも「知らないから考えない」では、あまりにも無責任ではありませんか。何も変わらないのではありません。変えようとしていないだけかもしれません。誰かがやってくれる、私でない人の方がうまくやれるだろう。そんなことはよくある話です。でもどうでもいいやと投げるのではなく、あなたにお願いするね、とちゃんと意志のある方向性を持って手渡しすることが、政治にはあってもいいように思います。
情報はあふれています。だからこそ、情報を「選ぶ力」「見抜く力」が必要なんです。一人ひとりが、「今、自分はどんな時代に生きていて、どんな未来を選び取ろうとしているのか?」を、きちんと意識していきたいと私は思っています。
「カウンセラーがAIと対決してみた話」と「自民党にお灸を据えようとする選挙の話」

セッションを受けてくれたかたが
私のアドバイスの後、AIにも壁打ちした結果を報告してくれました。
「批判と悪口」の違いで人間性を見極めろ!

参院選が公示されました。物価高でインフレで、給料の額面は上がっても、税金取られて手取りは増えない。インバウンドで観光客が多いし、街を歩けば異国の人たちが目について、ちょいちょいトラブルの話も聞く。ここまで経済的に苦しいと感じるこの時期に、選挙に行こうと考えて、さてだれに投票しようかと思っている人もいらっしゃるのではないでしょうか?人間観察が好きな私は選挙大好きなんですが、そんな私が候補者を選ぶときに何を考えて選んでいるか?をお話ししてみようかと思います。
もちろん政治家を選ぶのですから、私はまずは人間性を見極めようとします。選挙戦中の演説や討論会などで、候補者が何を言っているか。特に批判や批評ではなく「悪口」を言っているかどうかをよく見るようにしています。政治の世界では意見の違いを表出し合って議論するのは当然です。でも、その言葉が「批判」ではなく、ただの「悪口」になっていると私はどうしても、気になって仕方がありません。選挙でネガティブキャンペーンは、戦略としてアリだと認識はしていますが、やはり悪口は聞いていて気持ちの良いものではありません。
「批判」と「悪口」の違い
「批判」と「悪口」、どちらも相手に対して否定的なことを言うことがありますが、その目的と中身は違います。
批判は、冷静に問題点を指摘して、より良い方向へ導くための意見。
悪口は、相手をおとしめたり、貶したりするための感情的なことば。
私が感じる違和感は、「批判」の顔をして「悪口」を言っていること。たとえば、「○○議員の政策は現実を見ていない」ではなく、「○○は嘘つきで根性が悪い、顔が変だ」と言ってしまうようなこと。それはもう、議論ではなくただの罵倒でしかありません。
そしてもう一つ、候補者を応援している人たちに共感できるかも、見極めるポイントかもしれません。「悪口」を言っている候補者に同調して、それを聞いて笑ったり拍手したりしている応援者がいることがありますね。応援すると言うことは彼らの意見や主張に共感するからなのだろうし、悪いことではありませんが、人として相手を貶めたりばかにするようなことに共感したり、ような自分はどうなのかと思い至ることはないのでしょうか。ただただ自分が応援している人を盲信することは、カルトの信者と同じです。私は「批判」は歓迎するけれど、「悪口」は嫌いです
誰かと意見が違ってもいい。建設的な「批判」や「批評」はとても大事だと思っています。異なる意見の中に、新しい可能性があると信じているからです。
でも、ただ人を貶めるための言葉──それがまかり通るような空気には、やっぱりどうしても賛同できません。そして平気で悪口を言う人がトップに立っている党を応援することもできません。
みなさんは、今回の選挙誰を応援し、誰に投票しますか?迷ったら「批判」と「悪口」の違い、気にしてみてくださいね。