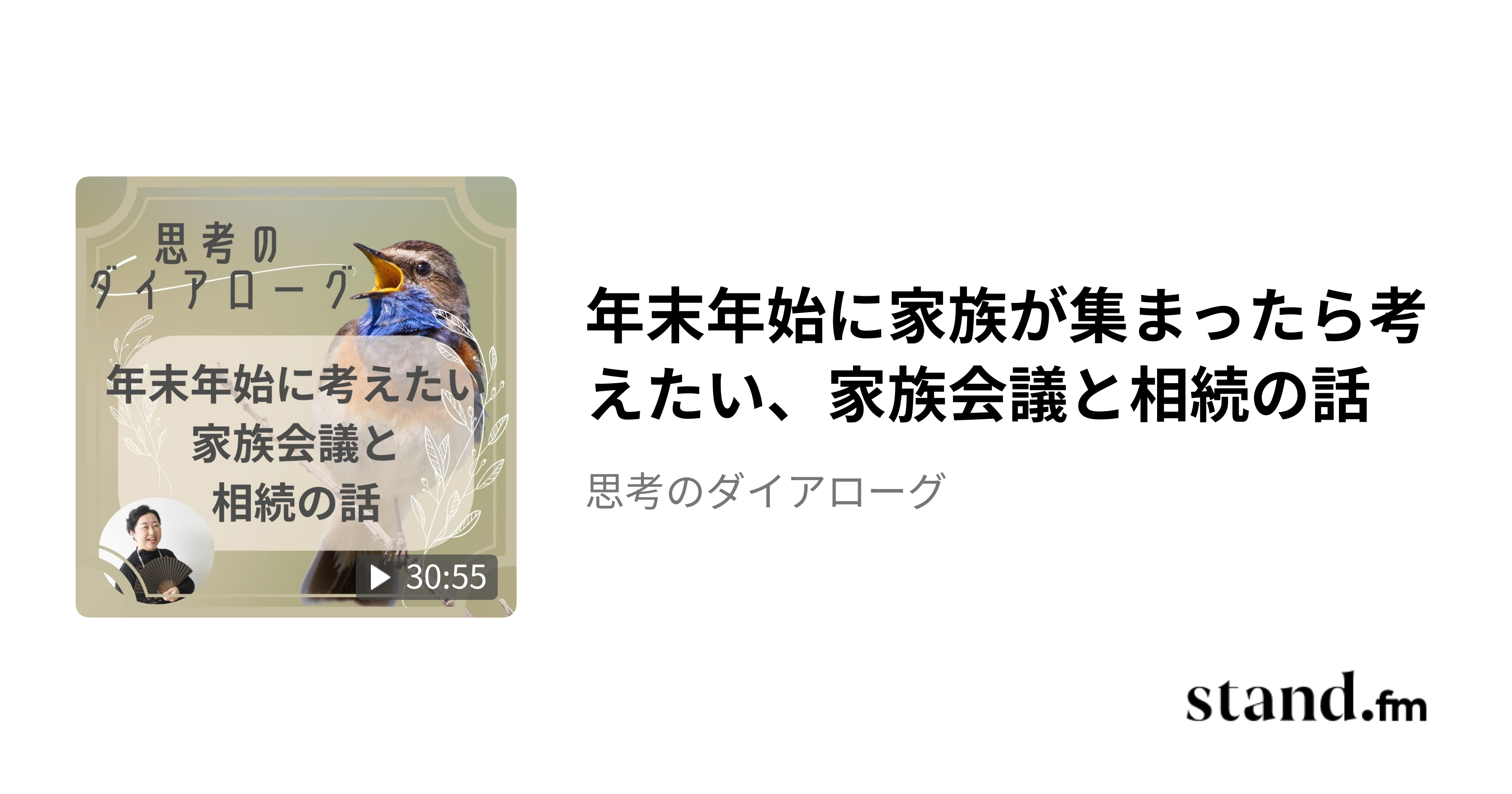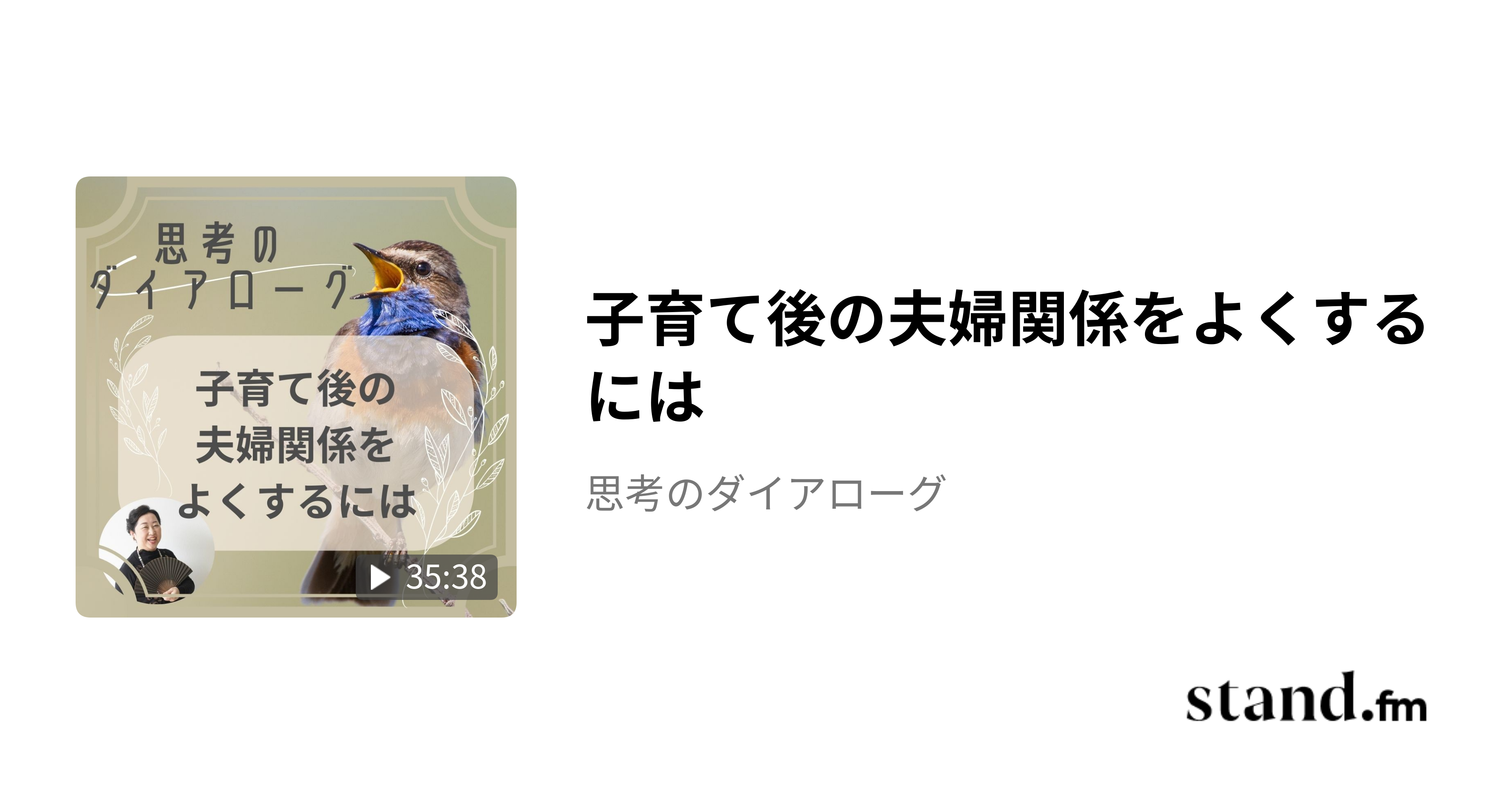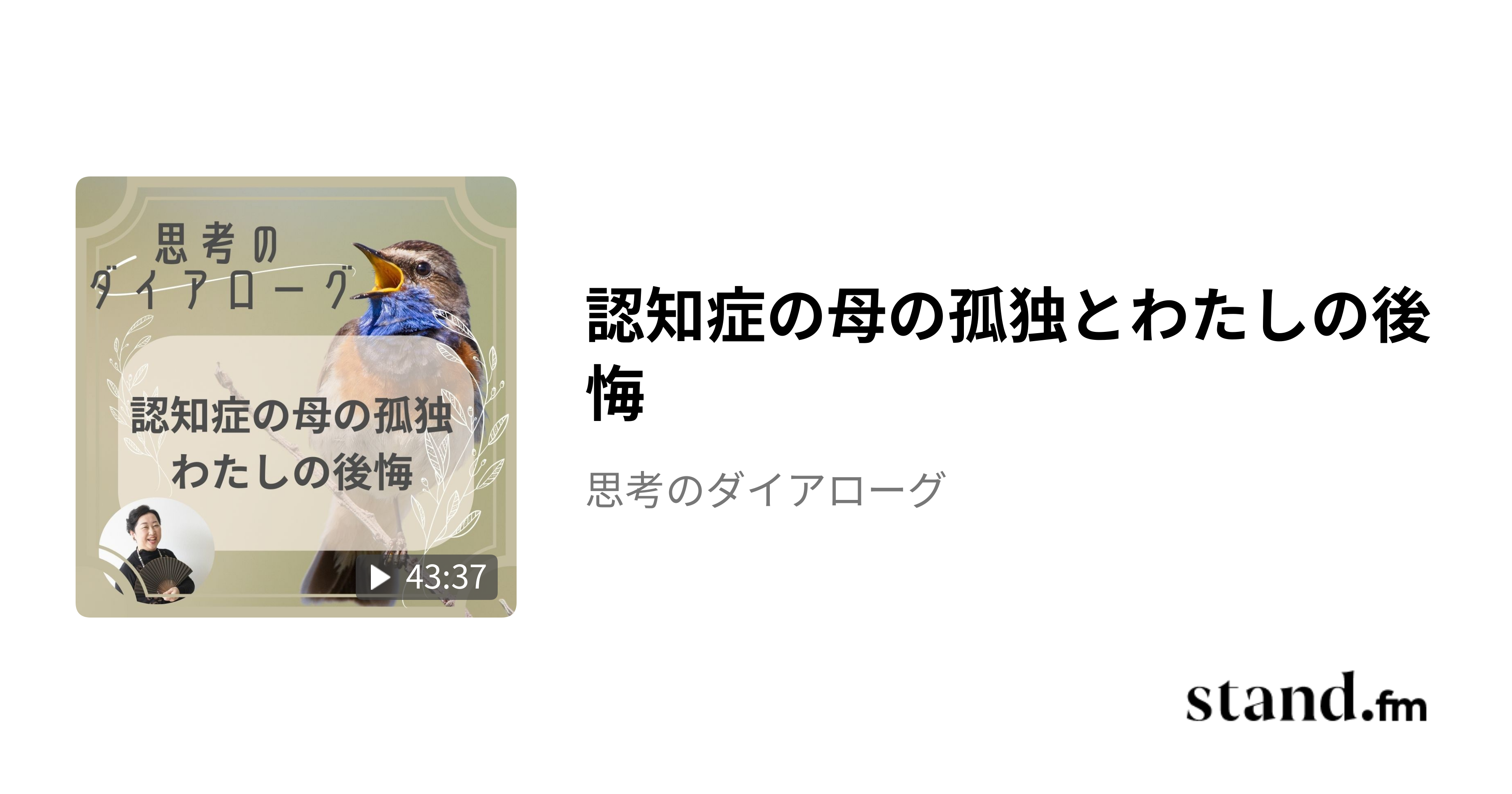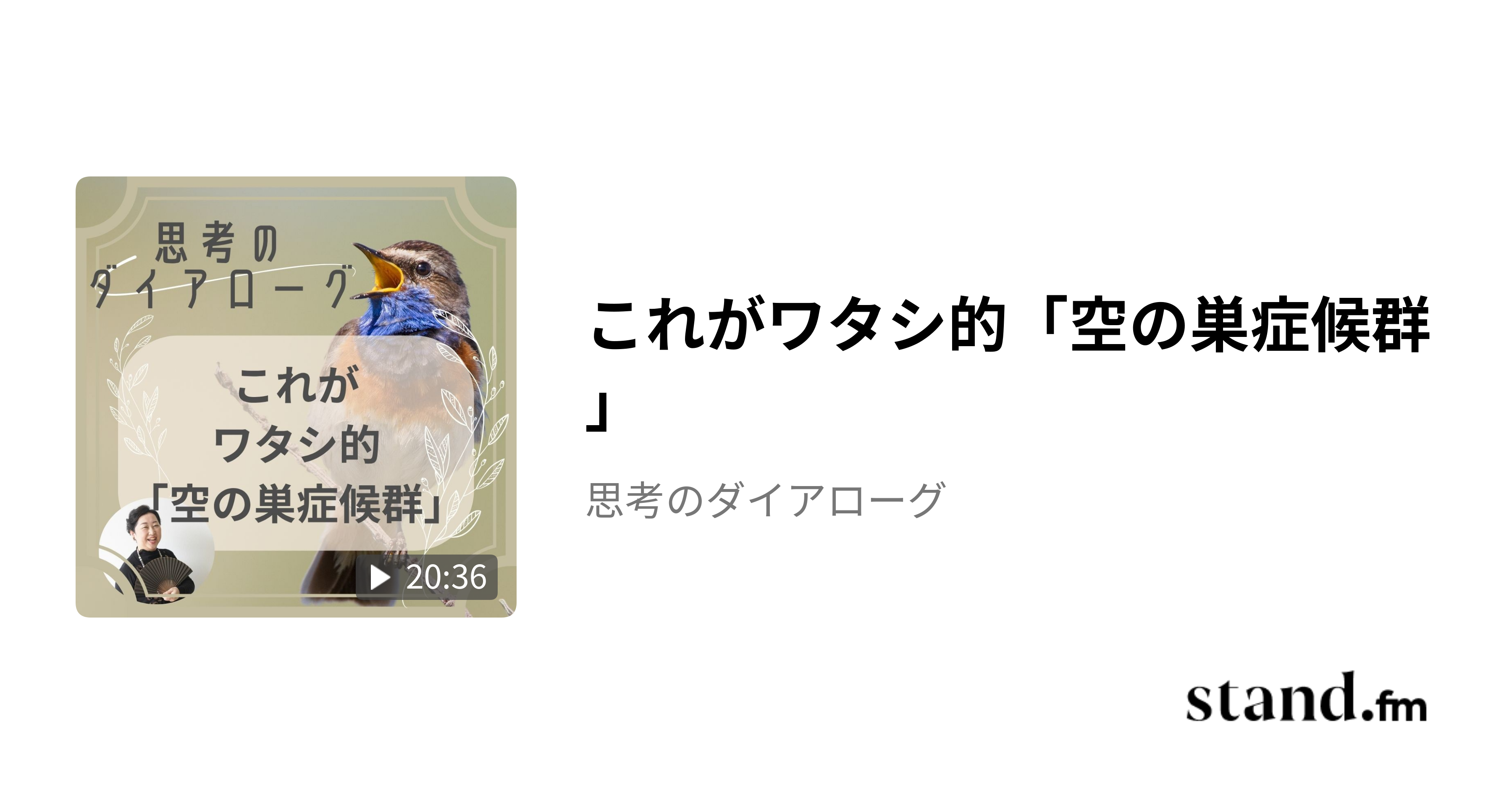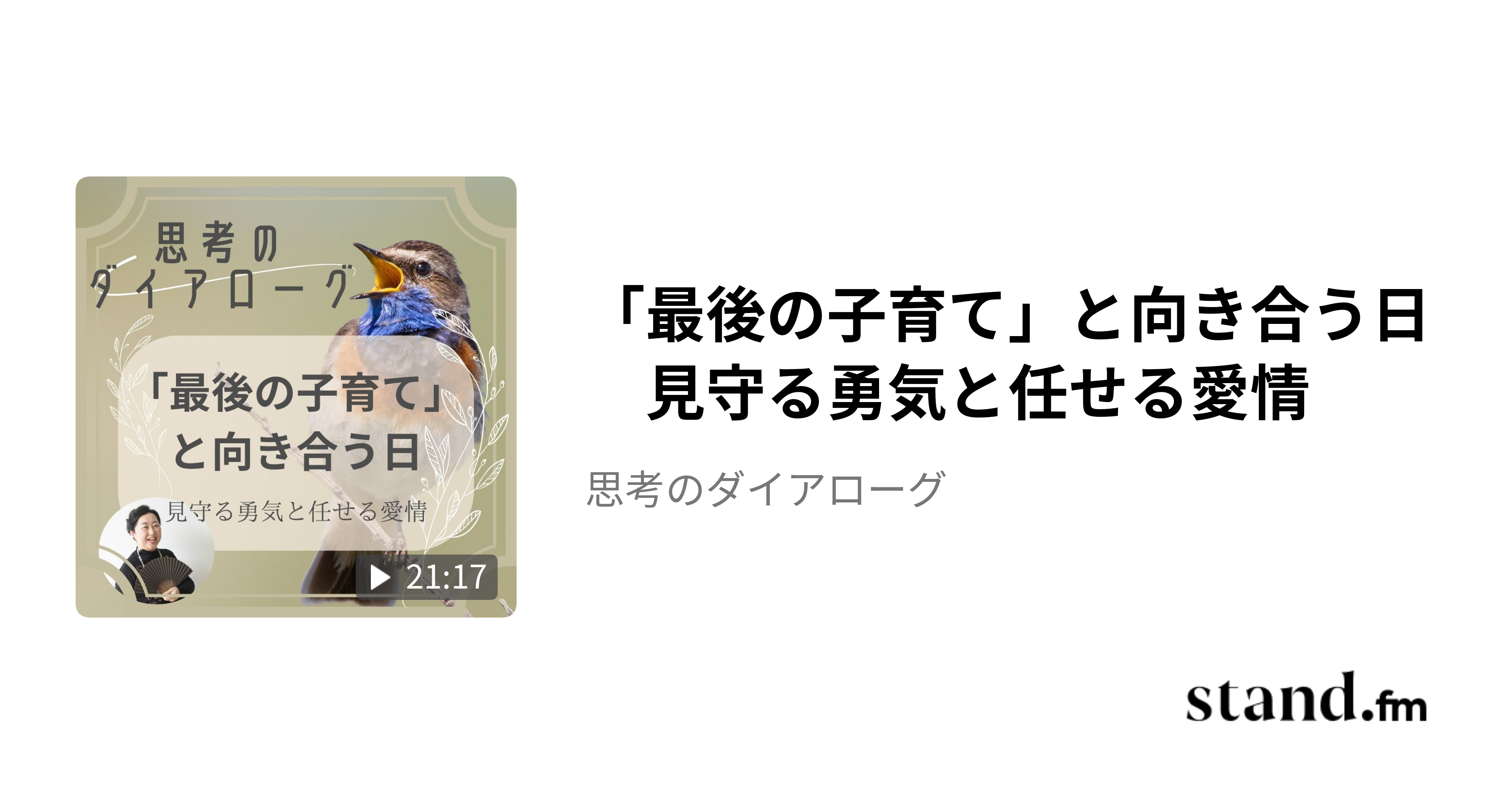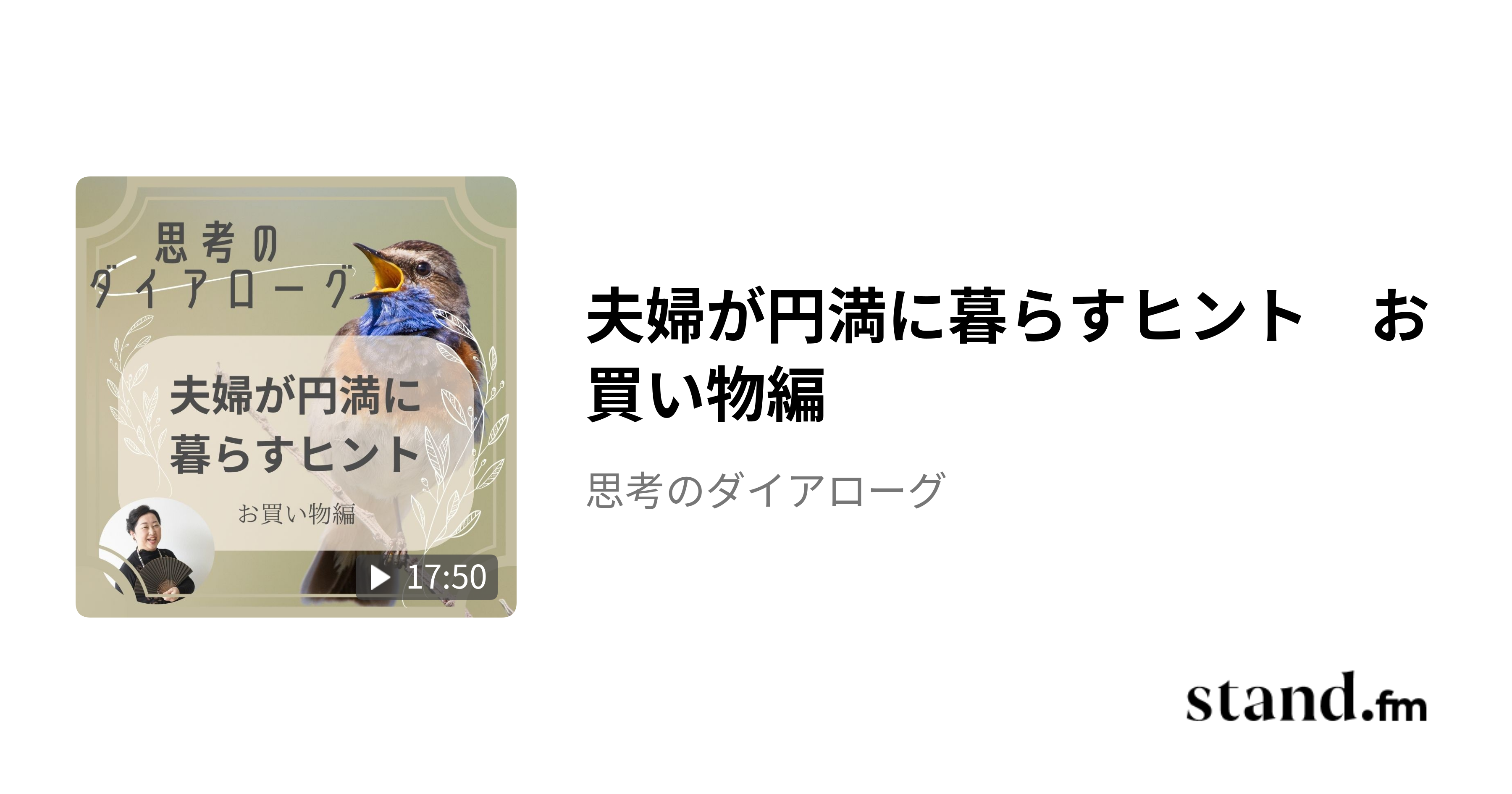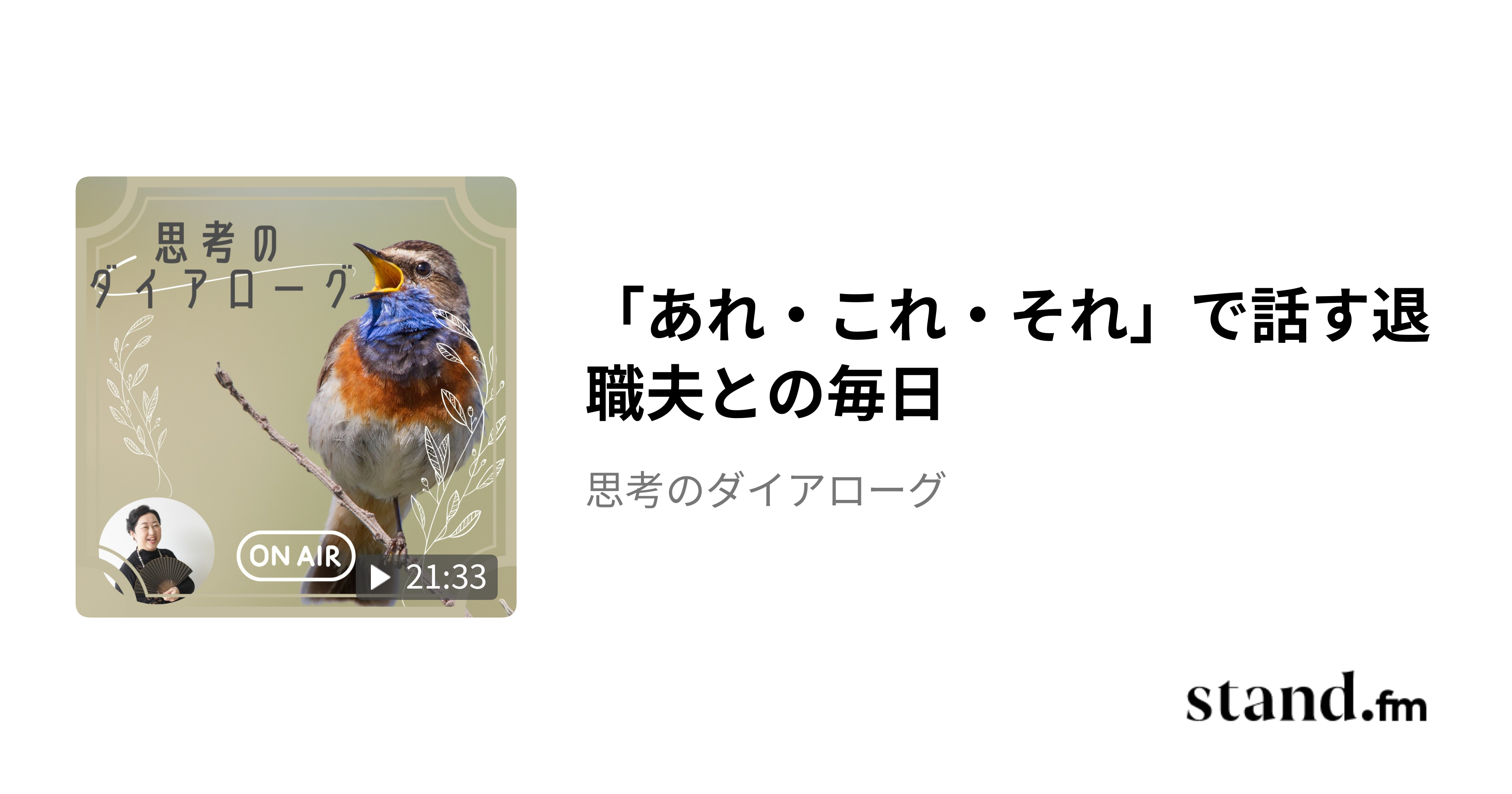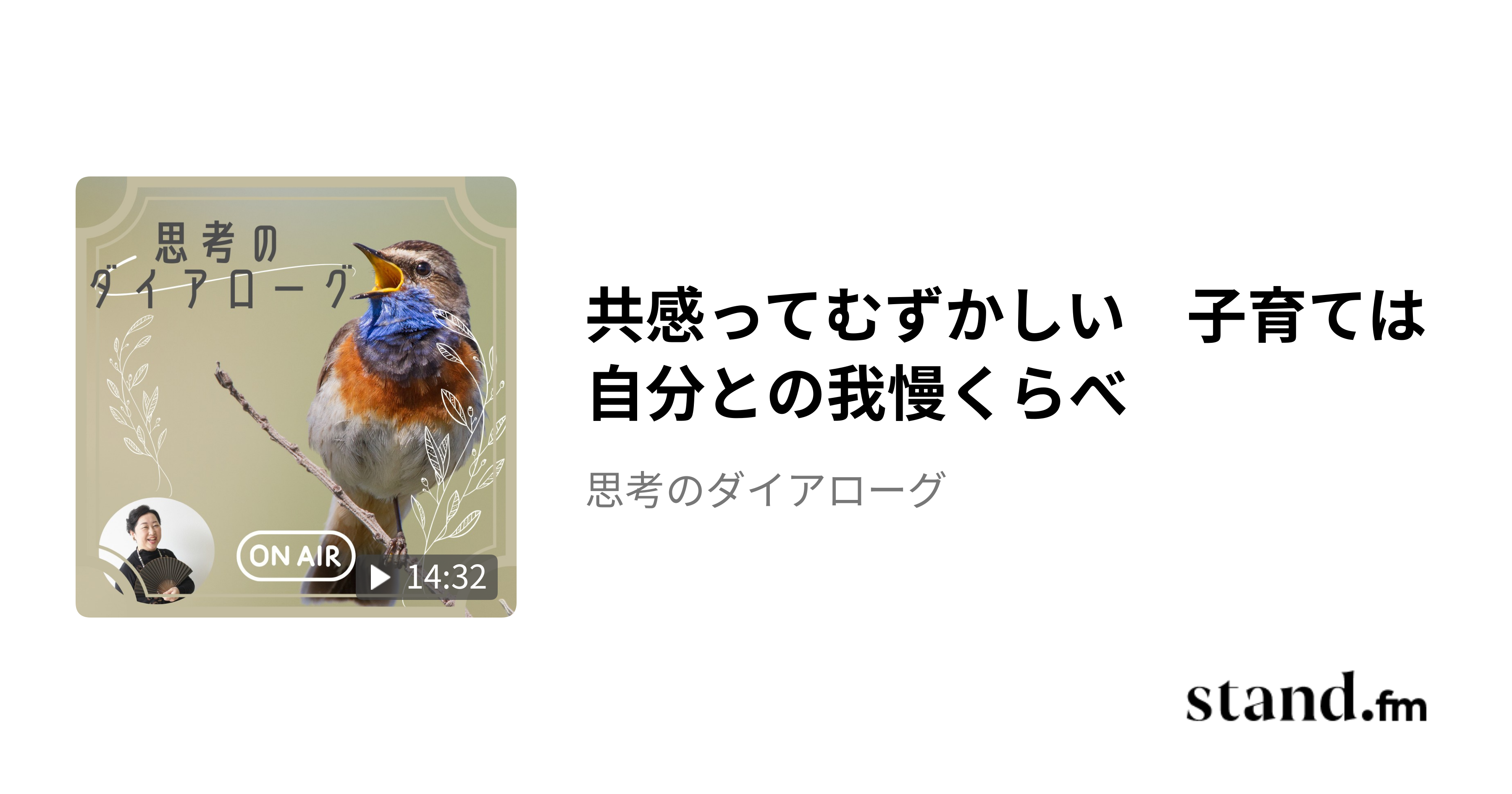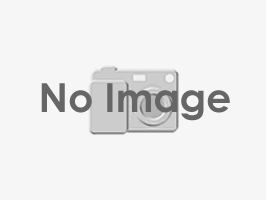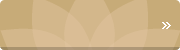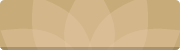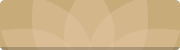家族・子育ての智慧
- 年末年始に家族が集まったら考えたい、家族会議と相続の話
- 子育て後の夫婦関係をよくするには
- 認知症の母の孤独とわたしの後悔
- これがワタシ的「空の巣症候群」
- 「最後の子育て」と向き合う日 見守る勇気と任せる愛情
- 夫婦が円満に暮らすヒント お買い物編
- 「あれ・これ・それ」で話す退職夫との毎日
-
夫が家にいる日々に、慣れるまでと慣れてからの話
- 家族に「ウザい」って言われないお父さんの秘密
- 共感ってむずかしい 子育ては自分との我慢くらべ
年末年始に家族が集まったら考えたい、家族会議と相続の話

今日はもう、八王子が本気出してきました。
曇り空の下、うちの“断熱材が入っていない恐ろしい家”は、もはや江戸時代。
廊下はアイスリンク、踏み出すたびに足裏が「ひゃっ…」ってなります。
ねこの肉球まで冷たくて、抱き上げたらピンクが濃い。
結局、コタツに吸い込まれていきました。正しい判断です。
そんな寒さの中で、年が明けましたね。
皆さま、どんなお正月でしたか。
人は、一緒にいられる時間が決まっているのかもしれない
うちの息子たち、二人とも一人暮らしを始めて半年ほど。
やっと自立してくれて「ほっとした〜」なんて言いながら過ごしてきたんですけれど、
年末年始に二人が帰ってきたら、やっぱりほっとする種類が違うんですよ。
二階に息子たちが寝てる。
それだけで私は安心して、ぐっすり眠れます。
「母親ってこういう生き物なんだなぁ」って、しみじみ感じました。
離れて暮らしていても、頭の片隅にずっとあるんですよ。
ちゃんとご飯食べてるかな、とか。
仕事で車に乗る長男は、事故を起こさないかな、とか。
次男は人間関係に繊細な子だから、職場でやられてないかな、とか。
近くにいれば、表情や声のトーンでわかることがある。
それが安心材料になるわけです。
だから、帰ってきてくれると嬉しいし、ほっとする。
ただ、ここからが複雑です。
集まるのは嬉しい。でも、お母さんは疲れる
息子たちが帰ってきたら、私は張り切るんです。
野菜を食べさせなきゃ、肉も食べさせなきゃ。
お腹いっぱいにして、あったかくして、元気に帰してやらねば!と考えてシャカリキです。
普段は、夫と私と妹の三人暮らし。
50代60代がちょこっと食べる生活だから、料理も“ちゃちゃっと2品で終わり”で十分なんです。
でも息子たちがいると、エンジンがフル回転。常にMAX。
最初の一日は、幸せなんですよ。
「嬉しい!元気でよかった!食べな!食べな!」って。
でも二日目くらいから、気持ちは変わらないんだけれど、ちょっと億劫さが出てきてしまいました。
「……ちょっと待って?私、疲れてない?」って。
これがね、なんとも言えない。
嬉しいのに、疲れてる。
幸せなのに、しんどい。
そして私は気づくわけです。
“してあげたい”という欲が、自分の安寧を軽く飛び越える瞬間があるってことに。
これ、母親あるあるだと思うんですけど、
自分の体力より、気持ちが先に走るんですよね。
「どうせ3日くらいしかいないし」って思うと、さらにアクセル踏んでしまいますし、止まらないんですよ。
年末年始やお盆は、家族が集まる貴重な時間
人って、その人と一緒に過ごす時間が、
どこかで“決まっている”のかもしれないなって思うことがあります。
寿命があるから、というのもそうなんだけど。
子どもと過ごす時間って、濃密な時期があるじゃないですか。
妊娠して、生まれて、育てて、20年。
手を抜きたくても抜けない。
苦しいし辛いのに、嬉しさも楽しさも濃い。
あの頃の時間は、感情も思いもぎゅうぎゅうに詰まってる。
でも子どもが大人になったら、
親と一緒にいる時間より、外で生きる時間のほうが長くなる。
すると私には、こう見えてくるんです。
「この子たちと一緒にいられる時間って、もうそんなに多くない」って。
だから年末年始やお盆みたいに、家族が集まれる時間は、
ただワイワイ笑うだけでも十分に大事な時間です。
絆を確かめるって、必要ですものね。
でも今回は、もう一つ。
「集まったからこそできたこと」がありました。
家族が集まったときこそ、“家族会議”
息子たちを送る前に、焼肉に行ったんですよ。
最近見つけちゃった、すっごく美味しい焼肉屋さん。
八王子に来た人には連れて行きたいくらいの店。
夫が正月だからと予約してくれて、四人で食べてたら、
なぜか流れで“家族会議”っぽくなりました。
うちは、夫の妹(私にしたら小姑ですね)も同居しているので、
家で四人だけになる時間って、実はほとんどないんです。
だから、こういう外の場で4人になれたことは結構レアです。
話題は、家と土地とお墓。相続のこと。
夫が亡くなったらどうなるか。
私が先に倒れたらどうするか。
保険や資産の管理はどこにあるか、みたいな現実の話。
息子たちが学生の頃には聞けなかったことです。
でも社会人になった今なら、息子たちも“現実”として受け取れる。
結婚するなら、相手の人とどう話し合うべきか、ということも含めて考える材料になるかもしれませんしね。
私は昔、お金と借金で実家が揉めた経験があるので、
家族がお金で壊れる怖さも見てきました。
だから息子たちには、特に強く伝えたいことがあります。
兄弟だけは、仲良く。
なんでも話せる関係でいてほしい。
信じ合っていてほしい。
結婚したら奥さんが一番大事になるでしょう。
それは当然だし、そうしてほしい。私も嫁ですし同じ立場でしたから、彼らにも夫と同じように奥さんを大事にしてほしいのです。
その上で、兄弟の絆が薄れてしまうと、
後から苦しくなるなることがある。
それだけは避けてほしいと思っているんです。
こういう話って、普段なかなかできないんですよね。
集まるのが年末年始やお盆くらいになってくると、
あとは結婚式か葬式でしか会わない、みたいな話になりがちで。
だからこそ、“集まれるときに話しておく”が、とても大事なんだなと思いました。
そして、いつもの日常
息子たちを送って、
また夫と妹との“いつもの生活”に戻ったとき。
私は少し、ほっとしました。
ああ、これが私の常(つね)なんだなって。
淡々と日々が流れていく、この感じ。
賑やかな晴れの日が終わって、日常が戻ってくる安心感。
でも同時に、思いました。
次も同じように集まれるとは限らない。
同じように笑えるとも限らない。
だから、やっぱり一期一会なんですよね。
集まる時間は、笑って、少しだけ現実の話もしてみよう
年末年始やお盆は、
家族が集まるだけで価値がある時間です。
愛情を確かめる時間。絆を確かめる時間。
でも、せっかく集まったなら。
笑って過ごすだけじゃなくて、
「もし何かあったとき、どうする?」
その気持ちや考えを少しでも共有しておくのは、
家族にとって、実は大事で必要な準備なのかもしれません。
人は、一緒にいられる時間が決まっているのかもしれない。
だからこそ、集まれた日に、
あたたかい話も、現実の話も、両方できたらいいですよね。
それが、残された人の“困った時の指南書”にもなるかもしれないし、
生きている今の私たちの“安心”にもつながるんだと思います。
記事を読んでくださって ありがとうございます
子育て後の夫婦関係をよくするには

昨日、夫と一緒にブドウ狩りに行ってきました。我が家は高尾山まで20分ほど。八王子の中でも少し涼しい場所なので、秋の訪れを敏感に感じます。最近では高尾からトンボが降りてきて、風も急にひんやりしてきました。
私はフルーツが大好きなのですが、腎臓の状態もあり、いつか自由に食べられなくなるかもしれないという思いがどこかにあります。だから「今この瞬間を思い切り味わいたい!」という気持ちが強く、フルーツ狩りは私にとって特別なイベントなのです。
夫もそれをよく知っていて、春はイチゴ狩り、夏はブルーベリー狩りと、いつも楽しそうな場所を探して連れて行ってくれます。
今回訪れたのは埼玉県狭山市の農園。八王子のすぐ隣なので、車であっという間に到着します。細い道を曲がると視界いっぱいに広がるブドウ棚。紙袋に包まれた房が、ずらーっとさがっていて、足を踏み入れた瞬間にふわっとワインのような甘い香りが漂ってきました。
農園では4種類のブドウが収穫できるとのこと。幹に貼られた色付きテープを目印にして種類を判別する仕組みです。夫が一番楽しみにしていたシャインマスカットを探し、巨峰や「シナノスマイル」という珍しい品種も収穫しました。
摘みたてのシャインマスカットは、冷えていないのに果汁が口いっぱいに弾けるほどジューシー。巨峰は渋みと酸味が絶妙で、やっぱり王道の美味しさ。そして初めて食べたシナノスマイルは、巨峰の風味を残しつつも濃厚でまろやか。思わず「この味、クセになる!」と心の中でつぶやいてしまいました。
棚の下は葉が日差しを遮ってくれるので、秋風が心地よく通り抜けます。夫は背が高いので少しかがみながら歩き、私は「低くてラッキー!」なんて笑い合いながら、ブドウ棚の下を散策しました。
子育てを終えて、夫婦二人の時間へ
結婚してすぐに妊娠、年子で二人の息子が生まれた我が家は、長い間「父と母」としての日々を駆け抜けてきました。気づけば、夫婦というより「子育て共同体」。自分たちだけの関係を振り返る余裕もなく、20年以上が過ぎていました。
そして今、息子たちが独立し、家には夫婦二人だけ。逃げ場のない一対一の関係になったとき、あらためて「夫婦として心地よくいられる関係を築く」ことが大切だと感じます。
ご相談を受けるお仕事をしていると、時に私と同世代の方に、夫婦の夜の夜の営みがないんです、というお話を聞きます。それがないことが悪いことというか、愛情の循環がないように感じるからでしょうか。なんとかしたいと言われることがあるんですよね。私たちは完全なセックスレス夫婦ですが、私自身はそれを寂しいとは思いません。何かが足りないとも思いません。夫は「言葉で愛を伝える」タイプではありませんが、フルーツ狩りの計画を立ててくれる行動が、私には愛情そのものに感じられるのです。
車を運転して、行き先を探して、私が喜びそうな体験を一生懸命考えてくれる。その優しさと思いやりが、私にとっては何よりの「愛のシャワー」。私は、精一杯「ありがとう」と笑顔で返しますし、楽しみにしている気持ちや想いを言葉にして夫に伝えます。これでお互いに愛の循環があると感じられているから、私には十分なのです。
思いやりが循環する関係
夫婦は長く一緒にいるからこそ、感謝を伝えるのをつい忘れてしまいがちです。「分かってくれて当たり前」ではなく、「あなたがいてくれて嬉しい」「これがすごく楽しかった」と、言葉にして伝えることが大切なんだと、最近よく思います。
男性は、自分がしたことが相手に喜んでもらえることで、自分の存在価値を実感するのだそうです。だからこそ、私たち女性が素直に「ありがとう」を伝えることが、パートナーシップを支える大きな力になるだと思います。
昨日のブドウ狩りは、ただの外出ではなく、夫婦としての小さな冒険でした。笑い合いながら過ごす時間の積み重ねが、きっとこれからの私たちを育てていくのだと思います。
日常からほんの少し離れるだけで、思いがけない喜びが見つかるかもしれません。それが夫婦の様々な形を作ることになるなんてことも、あるかもしれません。
認知症の母の孤独とわたしの後悔

お盆が終わりました。小さなお子さんがいる方は、夏休みのほうがかえって忙しく、バタバタしていたのではないでしょうか。私の家はというと、子どもたちも独立し、夫と二人。次男もこの夏から一人暮らしを始め、長男が一日だけ顔を出してくれました。仕事の合間に少しおしゃべりをして帰っていきましたが、それでも嬉しいものです。
私は実家が栃木なので、この時期に帰省しました。母は施設に入っており、普段なかなか会えないので、お盆のタイミングで面会に行けることはありがたいことです。
久しぶりに会った母は、思っていたより元気そうでした。手の硬縮が進み、爪で手を傷つけないようにタオルを握らせてもらっていましたが、顔つきは穏やかで、髪も整っていて清潔感がありました。施設の方々の丁寧なケアに感謝しています。
その日は、私と夫、弟、妹、それに甥っ子も一緒に面会しました。母を囲んで昔話をしたり、息子の近況を伝えたりして、賑やかな時間になりました。
帰り際、普段は受け身の母が、自分の右手をすっと上げて「バイバイ」としてくれました。驚きと同時に胸が熱くなりました。ちゃんと「また来るね」という言葉が届いている、その気持ちが伝わってきた瞬間でした。
母の人生と、寂しさ
面会を終えて、妹の家でおしゃべりをしていた時、弟が「母さんはすごい寂しがりなんだと思う。だから子どもに粘着するし、依存していたのかもしれない。あの頃はまだ甘えがあってそれをわかってあげることができなかったことを後悔している」というのです。母の人生を振り返ると、孤独や寂しさと長く付き合ってきた人だったのだと感じます。父を戦争で亡くし、母親とも幼くして離れて暮らし、祖父母に育てられました。結婚してからも、愛されながらも満たされきらない部分があったのでしょう。だからこそ、私たち子どもに強く寄りかかるところがありました。
若い頃の私たちは、その母の「寂しい」というサインを理解できず、うっとうしく感じたこともありました。けれども今、認知症で反応が少なくなった母を前にすると、むしろ穏やかに受けとめられる自分がいます。母の不器用な愛情や、伝えられなかった寂しさを想像できるようになったのは、時間を経て私自身が親になり、また子どもたちの成長を見てきたからなのかもしれません。
息子たちの姿を見ても、親子関係の不思議さを思います。長男はすっかり大人になり、私を気づかい、自然に優しさを言葉や行動で表してくれます。次男はまだ素直に感謝を口にするのが照れくさい様子で、その子どもらしさが私には可愛くもあり、少し心配でもあります。
母に対して素直に寄り添えなかったあの頃を思うと、息子たちが私に優しさを見せてくれることは、救いのようにも感じます。人はみんな未熟さを抱えて生きていて、後悔のない親子関係なんてありません。でも、後から気づき、補い合い、許し合えることが、きっと大切なのだと思います。弟は後悔を口にしていましたが、それはわたしも同じで、それがわかるようになったのは歳をとったということなのかもしれません。
帰省の道中は夫と二人でビジネスホテルに泊まり、ちょっとした旅行気分も味わいました。仏壇に手を合わせ、食事をし、甥っ子が切ってくれたスイカを皆で食べた時間も、良い思い出になりました。
介護をしている方も、今まさに苦しさの中にいる方も、あるいは看取りを終えて自分を取り戻そうとしている方も、それぞれに違う時間を過ごしていると思います。でもきっと共通して言えるのは、「完璧な親子関係なんかない」ということ。だからこそ、完璧を目指さず、後悔することも含めて、今できることをやり尽くしたいと思いました。
#お盆の記録
#親子関係
#介護と向き合う
#母との時間
#家族の絆
#親の気持ち子の気持ち
#不器用な愛情
#寂しさとともに
これがワタシ的「空の巣症候群」

八王子は真夏の陽気です。
ここ数日は毎日ゲリラ豪雨が降るようになりました。
つい先日、夕食の支度中キッチンの小窓越しに「ピカッ」と閃光が。雷ですよ。あ、これは来るなって、直感的にわかって身構えていると、頭ではわかってるのに、「ドーンッ!!」ってきたときには、もう体がビクッと震えました。
うちのすぐ近くの無人販売所に落ちたらしいんですよ。もうびっくり。すぐに消防車も来て、サイレンの音が聞こえてました。
さて、そんな日常の中、わが家もちょっとした転機を迎えました。次男が、とうとう一人暮らしを始めたんです。
長男は就職してすぐに家を出たんですが、次男はしばらく通勤していて。でもやっぱり遠いんですよね。ということで、ついに引っ越すことに。いろいろ荷物を詰めて、車で運んで、夫も手伝ってくれました。
でね、面白いんですよ。長男のときは自分でチャチャッと準備して、友達の車に積んでスッと出ていったのに、次男は直前になって「明日引っ越すから車出して」って。もうちょっと早く言ってよ!って話ですよ。
引っ越し前は心配の方が強かったんですけど、送り出したあと、ふと気づいたんですよね。
あれ、ちょっと楽かも。
寂しさはもちろんあるけれど、開放感も同時にある。
ご飯も、夫と私と義理妹のためだけならシンプルでいいし、送り迎えもいらないし、時間の制約がないことも、連絡を待つこともない。
最近はSNSで「娘が幼稚園に行きはじめて、空の巣症候群です」って投稿を見かけたりするんですが、それ違うから!ってツッコミましたね。
だって、帰ってくるじゃない、幼稚園から。まだ親元にいるでしょう?
たぶんそのお母さんはずっと一緒にいたのに、幼稚園に行って離れることが寂しいって言いたかったんでしょうね。気持ちはわかるけれど。
空の巣症候群は、子どもが完全に親元を離れて自分の人生を歩み出したときに親が感じる「喪失感・孤独感・虚無感」。そしてその気持ちが溢れてしまって、無気力になったり元気がなくなることを言うのではないでしょうか。
私も今、そのまっただなかにいます。寂しいけれど、同じくらい嬉しい。
何だか、やっとひと段落ついたなぁって。
とりあえず自立してくれたよ。ここまで来たんだ。私、よくやったよね、って、ちょっと自分を褒めたくなりました。
こういう感情って、経験しないとわからないものですね。実際に送り出してみて、はじめて湧き上がる感情や思いがある。
だからきっと、こういう「親の寂しさ」も、「あのときの私ならわかるよ」って誰かに寄り添える日が来るのかもしれません。自分で体験したからこそ、それが私の経験値(智慧)ですから。
「最後の子育て」と向き合う日 見守る勇気と任せる愛情

先日、息子の新生活に向けた買い物に付き添ってきました。
長男はすでに一人暮らしを始めていて、今回引っ越すのは次男。都心の職場に通いやすい場所へと、ようやく住まいを決めたようです。
次男は感覚的にとても繊細な子で、人混みや騒音が苦手。毎日の満員電車も、彼にとってはかなりの負担だったのだろうと思います。
彼は昔から音に敏感で、ヘッドフォンを常に手放せません。通勤中も音を遮断することで自分を守っていたようです。そんな日々を経て、ついに「自分の暮らし」を整える決心をした彼に、親として少しホッとする思いがありました。
さて、その引っ越しに伴って、生活用品を揃えに家電量販店へ行くことに。
冷蔵庫と洗濯機を選ぶために足を運んだのですが、いやはや…。決まらないんです。
予算、性能、デザイン、納期……。何を優先するかで彼の頭の中は大渋滞。最終的には3時間近くかけてようやく決めることができました。
その姿を見ながら、私はできるだけ口を出さず、ただそばにいました。
つい「私だったらすぐ決められるのに」と思ってしまうのですが、それを言わないのが“子育て”なんですよね。
自分で考えて、選んで、決める。そして、選んだ結果を自分で引き受ける。
この一連の流れを経験することでしか、人は育たない。これは頭でわかっていても、親として実践するのはなかなか大変です。でも、やっぱり、親が代わりに決めてしまったらダメなんですよね。失敗しても、遠回りしても、自分で決めることが何よりの経験値になる。
その晩、帰り際に息子がぽつりと「長い時間つきあわせちゃってごめんね。ありがとう」と言いました。驚きました。彼は普段、そういった言葉をあまり口にするタイプではないのです。でも、その一言に、きっと彼なりの「気づき」と「思いやり」があったのだと感じました。
子育てって、最後まで“我慢”と“見守り”なんですね。
自分でやってしまえば簡単なことも、あえてやらせる。
それが親としての責任であり、覚悟なのだと、改めて実感しました。
そして、これはきっと「最後の子育て」なのかもしれないなと思いました。
もちろん、子どもがいくつになっても、親子の関係が終わることはありません。でも、「自分で決めて、自分で生きていく」ための練習期間としての子育ては、少しずつ終わりを迎えていくんですね。
私たちが次の世代にできることは、
「代わりにやること」ではなく、「そっと支えること」。
その人が自分の足で立てるように、必要なときに手を貸す“サポート”であるべきだと、私は思っています。
子育てをしている方、
お孫さんを見守る立場の方、
あるいは後輩を育てるお仕事をしている方
誰かを育てるということに関わるすべての方へ。
「助ける(ヘルプ)」と「支える(サポート)」は、似て非なるものです。
そして、「我慢して見守ること」こそが、愛情の深さなのかもしれません。
夫婦が円満に暮らすヒント お買い物編

今日は、ちょっとした夫婦の日常の一コマをテーマにお話ししようと思います。
先日私の誕生日だったので、以前から欲しかったヨーグルトメーカーを夫におねだりして買ってもらいました。
1リットルの牛乳パックをそのまま差し込んで、ポチッとボタンを押せば、翌朝にはヨーグルトができている。なんて素敵!と、嬉々としてヨーグルト生活というか、発酵食品作りを楽しむようになりました。
甘酒を作ったり、塩麹に挑戦したり、いろいろ楽しくやっているわけですが、事件(?)はそんなある日に起きました。
ヨーグルト作りには牛乳と種菌となるヨーグルトが必要です。
買い物担当の主人にお願いしていたのですが、ある日、買ってきてくれた牛乳とヨーグルトで作ったものが、なんだかシャバシャバしてる。
あれ?おかしいな?
冷やせば固まるかな?と思っても、やっぱりシャバシャバ。
「あれー?なんか今回はちょっと違う感じだね」
と言いながら、半分食べたあたりで、ふと気づく。
牛乳パックをよく見ると
『乳飲料』
……牛乳じゃなかった!
裏の成分表示には「牛乳50%」の文字。
そりゃ固まらないわけだ、と納得。
私は子どもの頃から買い物や料理をしていたので、こういう表示を自然と確認する習慣があるんですけど、主人はそういう表示をあまり見慣れていない。
もしかしたら安かったから選んだのかもしれないし、パッケージも似てるから間違えるのも仕方ない。でも、このまま黙っていたら、また間違えてしまうかもしれません。
言い方ひとつで、未来が変わる
さて、ここで皆さんにお聞きしたい。
「なんでこれ牛乳じゃないのよ!ヨーグルト固まらなかったじゃない!」って、言いたくなりませんか?
でも、私は思いました。
これって、言い方を間違えたら
「俺が悪いってこと?」
「もう買い物行かない!」
なんて展開もありえますよね。
だから、こう言いました。
「ねぇパパ、前に買ってきてくれた牛乳で作ったヨーグルト、なんかちょっとシャバシャバしてたよね。でね、パック見たら『乳飲料』って書いてあったの。私も気づかなくて、半分食べちゃったんだけど、成分見たら牛乳50%ってなってたの。だから今回はちゃんと固まらなかったのかもーって。いい実験ができたわ!」
そしたら主人、「あぁ、そうかぁ」って納得してくれて、次に買ってきてくれたのはちゃんと“牛乳”でした。
率直さと、思いやりのバランス
思ったことを素直に言えるのは、とても大切なことです。
でも、「どう言うか」を少し工夫するだけで、お互い気持ちよく暮らせる。日々のちょっとしたことだからこそ、「率直さ」が「雑で乱暴」になってはもったいないですよね。
夫婦でも親子でも、家族って、近しいからこそ甘えも出るし、率直な言葉になりやすい。でも、その関係性を大切に育てるには、ちょっとのユーモアと、ちょっとの気遣いが必要なんだなって、あらためて感じた出来事でした。
ということで、今日の教訓は──
ヨーグルトを固めたかったら、乳飲料ではなく牛乳を!
そして、
長く一緒にいる人にこそ思いやりと率直さを持とう!
ということで、心地よい毎日を過ごすには、ちょっとした緊張感が必要かもねってお話でした。
記事を読んでくださって ありがとうございます
「あれ・これ・それ」で話す退職夫との毎日

今回は、私たち夫婦の会話をめぐるちょっとした日常のズレ──その中にある「感覚タイプの違い」についてお話してみたいと思います。
優位感覚の違いがすれ違いの原因に?
人は誰しも五感(視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚)を持って生活していますが、その中でもよく使う傾向のある感覚を「利き感覚」「優位感覚」といいます。NLP(神経言語プログラミング)では、主に「視覚タイプ」「聴覚タイプ」「体感覚(感覚)タイプ」の3つに分類されます。
私は典型的な「視覚タイプ」。物事を絵や映像で捉えることが得意で、言葉にも正確さや明確さを求めがちです。反対に、私の夫は「体感覚タイプ」。感覚や雰囲気、空気感を重視するため、言葉が曖昧だったり、指示語(あれ、それ、ここなど)がやたら多かったりします。
この優位感覚の違いが、なかなかに面白い(というか、若い頃はけっこうイライラしましたが)すれ違いを生むのです。
あれってどれ? それって何? 夫の「感覚語」に翻弄される日々
たとえば休日のドライブ中。「お昼どうする?」と私が聞くと、夫は「あそこ行こうよ、ほら前に話した新しい店」などと言います。「あそこってどこ?」と聞くと、「ほら、あの道路沿いの…」と続く。
店名も場所も具体的に出てこない夫の言葉に、私は毎度モヤモヤ。記憶の中から“新しくできたかもしれないお店”を総動員して、「あのカフェ?」「あの洋食屋さん?」と当てにいく、まるで連想ゲーム。
視覚タイプの私は「具体的な情報」がないとイメージできません。でも夫は、「体感」で捉えているから、本人の中でははっきり「そこ」が存在しているのです。悪気はない。でも伝わらない。このズレが、日常のあちこちにあります。
コミュニケーションは、慣れとあきらめと、少しの敬意
洗濯洗剤の話でもそうでした。私が「いつもの粉石鹸、もうなくなっちゃったから買いに行きたい」と言うと、「ほら、あれだよ、前買ってきたとこで売ってたやつだよ」と夫。
だから、それがどこなんだってば……とツッコミたくなる気持ちを、ぐっと飲み込んで「もしかしてカインズ?」「ああ、それだ!」──このやり取りも、もはや夫婦の定番です。
以前はイライラもしました。でも今は「この人は、この感覚で世界を捉えている」と思えるようになりました。なれもあるかもしれませんが、そのままを受け止めることが私自身のため、楽な関係をつくっているように思います。
これは諦めではなく、尊重。自分が変わる方が早い、と気づいたからです。年を重ねるごとに、イライラするエネルギーも惜しくなってきますしね。
梅の実と暮らしの感覚、そして成熟ということ
そんな日々の中で、我が家の梅の木が今年は豊作。夫がせっせと梅を収穫してくれたおかげで、私は毎日せっせと瓶詰め作業。梅シロップに蜂蜜漬け、らっきょう酢を使ったやさしい梅漬け──保存食づくりに精を出しています。
夫の「取りすぎ」には思うところもありますが、それもまた暮らしの一部。完全に“社会的肩書”を脱ぎ捨てた彼が、感覚のままに動き、関わってくれていることに、私はある種の安心感を覚えるのです。
違う感覚を持つ相手と、どう付き合っていくか。
それは、私たちが日常で何度も繰り返していく「小さな理解」の積み重ね。そして、自分の枠の外に、そっと手を伸ばすことでもあります。
感覚の違いで起きるすれ違いを、ユーモラスに、そして誠実に捉えることができたとき、私たちはまた一歩、成熟に近づけるのかもしれません。
今日も、ちがいを面白がる一日になりますように。
夫が家にいる日々に、慣れるまでと慣れてからの話

今年の初め、我が家の夫が定年退職しました。
世の奥様方がよく言うように、
「いやー、毎日家にいるとねぇ……」というアレ、
例にもれず、我が家にもやってきました。
昭和男児らしく、朝から晩までテレビを見ている夫。
朝のワイドショーに始まって再放送のドラマやクッキング番組、スポーツ中継まで、私には何が楽しいのか、さっぱりわからない。
でももう会社に行かなくていいのだから、どうぞご自由にってなもんです。
存分に自由を満喫する夫。
私には仕事部屋があるので、そこにこもってセッションしたりブログ書いたり、
家にいてもずっと顔を合わせているとイライラすることもあるでしょうが、その点は助かります。
家にいるからこそ、実際に距離感がとても大事。
今までは、私ひとり。
お昼ごはんなんて適当に、
お茶漬けとか、昨夜の残り物でささっと済ませていました。
でも、夫がいるとね……
なんとなく、何か作らなきゃいけない気がして、妙にソワソワ。
「存在がちょっと面倒くさい」なんて思ってしまうのはいけない事と思いつつも、そう感じてしまうのは止められません。
だから私は、
「うん、夫がいるのをめんどくさいと感じてるのよね」とそこは認めてしまいます。
あとはこの気持ちをどうするか。
ところが数ヶ月もすると、不思議なもので、お互いだいぶ順応してきました。
今では普通に、
「今日は残り物でいいよね?」
「うん、お茶漬け最高。」
なんて、気楽なやりとりだできるようになりました。
最初はこんなこと言ったらイラつかれるかもと思いましたが
実際やってみると思ったよりあっさり受け入れてもらえました。
そして、もうひとつ、気づいたこと。
夫、やたらと優しいんです。
もともと無口で穏やかな人でしたが、現役時代はそれなりに社会の波にもまれて、イライラしたり、ピリピリしたり、
剣呑な雰囲気をまとっていることも、正直ありました。
それが、今はノーストレス生活のおかげで、びっくりするくらい、心もまるっと丸くなっております。
お昼ごはんを作ってくれたり、「平日空いてるから、どこか行く?」なんて、誘ってくれたり。
私がコロナで寝込んだときなんて、家事も食事も完璧に引き受けてくれて、私は安心して布団にくるまることができました。
改めて思いました。
社会で責任ある仕事を持つというのは、素晴らしいことだけれど、同時に、心を削るようなストレスと隣り合わせなんだな、と。
退職したからこそ見えた、夫の素顔。
きっと、これが本来の彼なんだろうなぁ、と思うのです。
家族に「ウザい」って言われないお父さんの秘密

我が家の夫は、いわゆる無口なタイプです。
口数が少なくて、冗談を飛ばすようなこともあまりないのですが、どこか、あたたかい。
私が体調を崩したり、
気分が沈んでいたりすると、
そっと気遣ってくれる。「大丈夫?」と、ほんのひと言添えてくれたり、
帰り道に私の好物を買ってきてくれたり。彼なりの「励まし」なのだと思います。
そういう主人の姿を、
息子たちはずっと見てきました。
だからなのか、彼らも私にとても優しいんです。
「大丈夫? 今日は無理しなくていいよ」
なんて言葉をかけてくれたり、
お気に入りのベーコンポテトパイをそっと差し入れてくれたり。
ほんのささやかなことだけど、なんともいえないあたたかい気持ちになります。
父親が子どもに信頼されるために何をしたらいいのか——
いい父親になるためにどうしたらいいのか?
なんてご相談もよくされます。
いろいろな答えがあると思いますが、私は
「子どもが大切に思っている母親と父親がどう接しているか」
が、その大きな鍵になるんじゃないかと感じています。
子どもって、よく見ているんです
言葉よりも、行動や表情や、態度の積み重ねを。
お母さんに優しく接しているお父さんのことを、
子どもはどこか誇らしく思っているのではないでしょうか。
母を大切にする父の姿が、
そのまま「家族を大切にする人なんだ」という信頼に、つながっているのでしょう。
もちろん、父と子が直接たくさん会話をしたり、
一緒に遊んだりする時間も大切です。
でも、案外見落とされがちなのが、
「母である妻への接し方」という静かなメッセージ。
その日々の在り方が、子どもの心に「お父さんは信じられる人なんだ」
という安心感を育てていくんじゃないかなと思うのです。
愛情って、目に見えなくても、ちゃんと伝わるものなんですね。
そしてそれは、子どもの優しさや思いやりとして、
次の世代にもそっと受け継がれていくのかもしれません。
思っていただけでは伝わりません。
言葉だけでも不甲斐ないもの。
思いと言葉と態度(行動)全てで大切なものを大切にしていると示してください。
世のお父さんたち、恥ずかしがらずにやってみてください。
家族を支えるお父さんだからこそ、愛の表現者になってくださいね。
必ず家族はあなたのもとに一致団結していくことでしょう。
共感ってむずかしい 子育ては自分との我慢くらべ

息子が会社でパワハラを受けてたお話は、以前書いたかと思うのですが、まぁ会社の人事はそう変わらないわけでまた似たような事が起きたのですよ。
やっぱり落ち込みますよね。前回は私もあれこれ心配で(なにせ毎日ため息混じりに会社に行くし、電車通勤だから飛び込んじゃったらどうしようとか無駄に妄想したりして)あぁしたらとかこうしたらとか、いろいろアドバイスみたいなことを言ったりしてしまったんですよ。
そうしたら息子に
「お母さん、(いまだに彼らは私をこう呼ぶ)僕はただ共感して欲しいだけなんだ!!」
と言われてしまった。。。
そうだよね。
私は仕事では人の相談を受ける立場だし、占い師歴も長いから共感は基本中の基本で、仕事ではそれなりにできていると思うのだか、さて自分の子供のこととなるとそうはいかない。
傷ついてほしくないし、悲しませたくないし、この苦しみから少しでも早く離脱してほしい!という守りたい欲が暴走してしまって、まぁクソバイスが止まらないわけです。情けない話、息子にダメ出しを食らったんですよ。
本当に申しわけなく、ハッとした私はとにかく謝りました。
「ごめんね。お母さんショウさんに苦しんでほしくなくてつまらんアドバイスみたいなことをしてしまった。そうだよね。つらいんだもんね。ごめんね。」
それから数ヶ月後、また似たような事が起こりました。
今回はもう共感しかしませんでした。
「しょうさんはよくやってる。お母さんは知ってるよ。頑張ってる。大丈夫」
そう言って背中を何度かなでると、そのまま出掛けて行きました。
いくつになっても息子は私の中で小さい頃のままで、守りたい存在なんですよいね。でもいつかは自分で困難をなんとかする力や方法を身につけてほしい。そのためには、ただ守るだけではなくて、見守る必要もあるわけです。もう我慢ですよ。言いたくなったり、やってあげたくなることをグッと堪えて、見守ることの辛さと言ったら、やってしまった方がなんぼも楽です。でもそれが一番やっちゃダメなやつ。
本当に子育ては我慢の連続なんですよね。