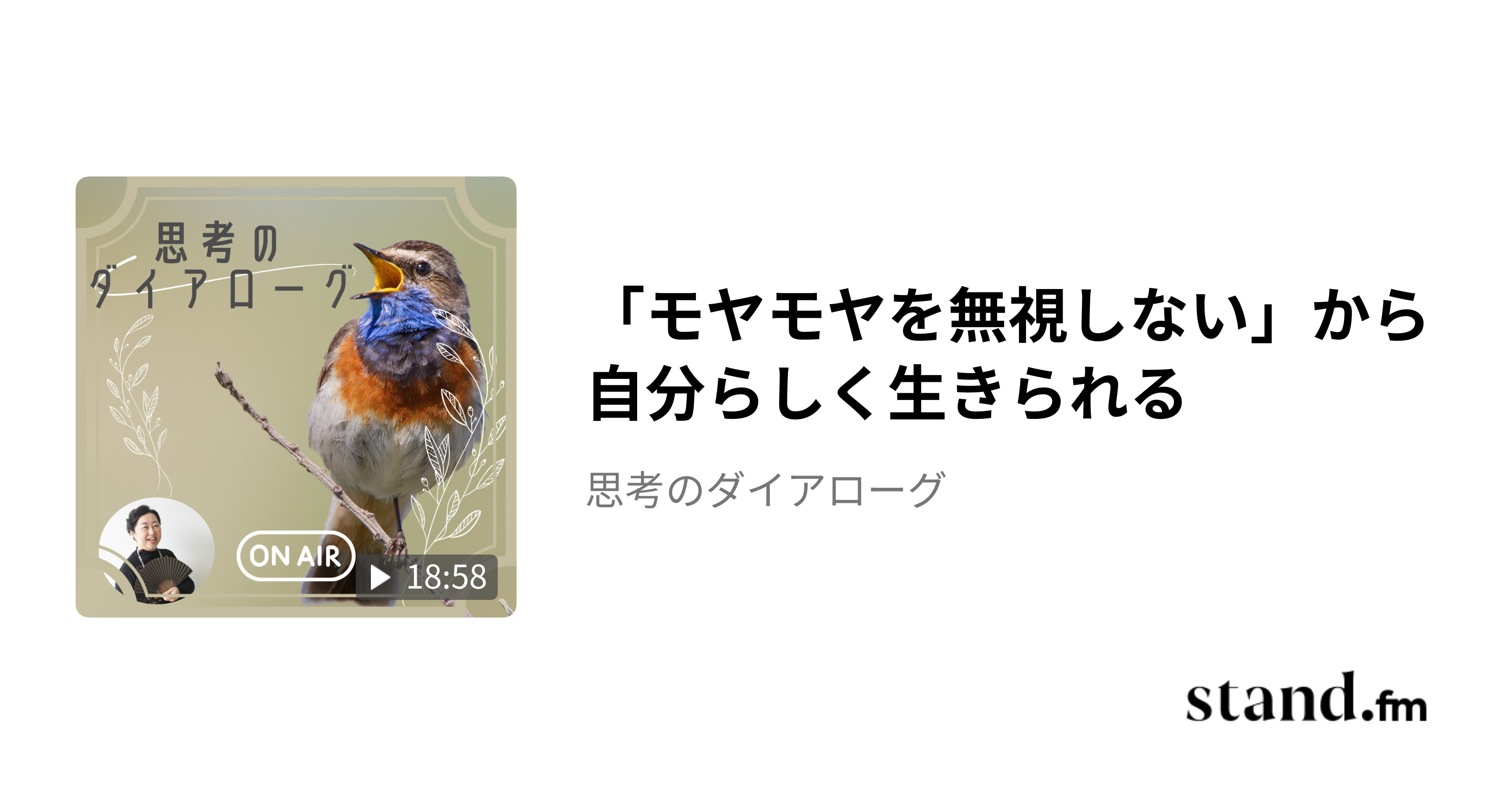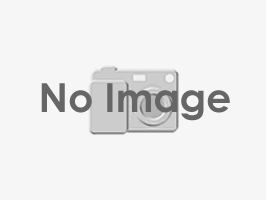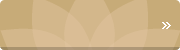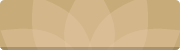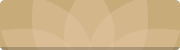雑感の智慧
読みやすい記事はちょっとした思いやりでできている

私は文章を書くときに、いつも気にかけていることがあります。
それは、「読みやすさ」。
パソコンで文章を打ち込むとき、
変換キーを押せば、いろんな漢字がぱっと出てきますよね。
普段、話し言葉ではよく使うけれど、
漢字にしてしまうと急に読みづらくなる言葉も、意外と多いものです。
これは、変換ありきで文章を打っていると、
つい見逃しがちなことだなぁと、最近改めて感じることがありました。
たとえば、「お咎め」。
(おとがめ)と読むこの言葉、
先日、あるブログで漢字表記で出てきたのですが、
私はふと立ち止まってしまいました。
「これ、なんて読むんだっけ?」
すぐに調べて「ああ、そうだった」と思い出したのですが、
そこそこ本を読む私でも、迷ってしまう瞬間があるんだなぁと、苦笑い。
もちろん、これは私の知識不足と言われれば、それまでです。
でも、人に読んでもらうための文章であるならば、
「一瞬でもつまずかせない工夫」は、とても大事なことだと思います。
もし私なら、
きっと「お咎め」とは書かずに、
ひらがなで「おとがめ」と表記するでしょうね。
私が良く使う「拘り(こだわり)」なんかも、そうですね。
漢字で書いた方が意味が引き締まる場面もあれば、
逆に、読み飛ばされたり、硬く感じられたりすることもある。
文語と口語。
文字と声。
その違いを意識しながら、どちらがふさわしいかを、
その都度、選んで表現したいと思います。
文章は、誰かに届けるものです。
「わかりやすさ」や「読みやすさ」は、
書き手から読み手への、思いやりだと、私は思うのです。
読みにくさも、もちろん時には表現の一部になり得ます。
でも、それは意図して選ぶものであって、無意識に押し付けるものではないと思います。
最近はAIを使用して文章を書かれる方も多いでしょう。
それが悪いことだとは思いません。
文章を整理したり、まとめたり、AIにサポートしてもらうことで新しい切り口の表現が生まれることもあると思うからです。
ただこの読みやすさや、自分らしい語り口になっているかは、最後ちゃんと出来上がった文章を読んで、手直しすることは大切ではないでしょうか。
自分が発信する内容が、自分らしくなかったら上手く書けていても、面白くはないと思うし、読み手にはそれがちゃんと感じられるものです。
読みやすさは思いやりですし、自分らしさは自分へのリスペクトです。
文章を書くうえで、私はこれらを忘れないようにしていきたいと思います。
「モヤモヤを無視しない」から自分らしく生きられる

最近個人経営のお店がどんどん閉まっていて
チェーン店ばかりになっている中で
新しくオープンしたお気に入りのお店。
夫と何度かランチどきにうかがって、
オープンキッチンだし
お値段もお手頃で
セットに私の大好きな茶碗蒸しがついているのも
お気に入りポイント。
でも、先日。SNSで見かけたある投稿に、
心がざわついてしまいました。
それは、某お笑い芸人出身の著名人
(仮に「N氏」とします)のアカウント。
彼が手がけた作品「●●ル」(※伏字)
のチケットを50枚購入すると、
本人が直接お礼に伺うというキャンペーンをしていて、
そのお店が、まさにそれに参加していたのです。
店主さんとスタッフらしき人たちが、
満面の笑みでN氏と一緒に並んでいる写真。
それを見た瞬間、
胸の奥に、もやもやとした感情が広がってしまいました。
正直に言うと、
私はN氏のビジネスのやり方に、
かねてから違和感を抱いていました。
「応援」や「夢」を看板に掲げながら、
その裏で、
「これって本当に必要なことなんだろうか」
「誰かの無理な善意を、利用していないだろうか」
そんなふうに感じる場面が、
何度もあったからです。
そして『●●ル』という作品についても、
個人的には、あまり心に響かなかったというのが
本当のところだったりして。
そんな背景があったからこそ、
お気に入りのお店が、
その世界観に嬉々として加わっている姿を見るのは、
思った以上にこたえるものがありました。
まるで、
大好きだった友人が、
自分とは相容れない何かに心酔してしまったのを
知ったときのような。
そんな、勝手な寂しさ。
冷静に考えれば
お店の味にも、
値段にも、何も関係ない。
もちろん店主さんにも、
自由に応援する権利がある。
それでも、
心は理屈通りにはいかないものです。
好きだったからこそ、
勝手に裏切られたような気持ちになってしまいました。
「好き」と「信じる」は、似て非なるもの。
似ているからこそ
心が勝手に勘違いを起こしてしまったのかもしれません。
誰かを、何かを、好きになった瞬間に、
無意識に
「この人は、私と同じ、もしくは似た価値観だろう」
と自分なりの信頼を重ねてしまう。
それが、違う方向を向いていると知ったとき、
自分でも驚くほど、心は脆くなってしまう。
つまらない、
小さなことと言えなくもない。
気にしなくてもいいし
わざわざネガティブな気持ちで
不愉快にならなくてもいいもかもしれません。
しかし、私は小さな違和感を、
「たいしたことない」とごまかしたくないのです。
心に生まれたモヤモヤを、なかったことにしたくない。
なぜなら、
このネガかもしれないこのモヤモヤが
私自身が何を大切にしているのか、
何に違和感を覚えるのか、
どんな価値観を選んで行きたいのか
その“本音”を教えてくれる、
かけがえのないサインなのかもしれないと思うからです。
好きだったものにがっかりするのは、悲しいことです。
でも、悲しさを感じられるのは、
素直に自分の感情を感じている証拠ですし
それが自分の心に誠実に生きようとしている証なのではないかとも思うのです。
心が「違う」と感じる時、
私は、ちゃんとそれを受け止める。
なぜなら、
自分の心に嘘をつき
大袈裟かもしれませんが裏切るようなことに慣れてしまったら、
いつか、大切なものを見失ってしまうかもしれないと思うから。
小さな違和感やモヤモヤを無視せず、
「これは違う」と思った自分をちゃんと見つめる。
これも自分軸を確認する作業だったりしなやかに、
生きるのに必要なことかもしれません。
こだわるところそこじゃないんだよなぁ(水素水をお客に出してしまうお店への不信感)

鴨南蛮そばが好きです。温かいおつゆに噛むたびにじゅわっと鴨のあぶらの旨味が広がってそこに葱の香ばしさが合わさって。最後に蕎麦の香りがふわっと追いかけてくる感じが、たまらないなぁと毎回しみじみ思う。
そんな鴨そばを出すお店が、最寄り駅の近くにあるのを知ったのは、つい最近のこと。「いつか夫を誘っていってみよう」と思っていたお店です。SNSもやっていて、店主さんが蕎麦へのこだわりや産地の話を投稿していて、それも好感を持って眺めていたんです。
ところが、ある日目にした投稿に、ふと心が引っかかってしまいました。
「当店では、お水にもこだわっています。“水素水”をお出ししております」
……水素水。
ああ、そっちか、と。
「水素水」と聞いた途端、心が遠のいてしまいました。好きな人には申し訳ないんですけど、どうにもその言葉には「ん?」と思ってしまうのです。
もちろん、水にこだわること自体は理解できます。料理に使う水は、素材の味を引き立てる大切な要素ですから。でも、「水素水」というワードになると、怪しさの方が先んじてしまいます。だって、水素ですよ。水素分子はとても小さくて、まぁ水素が溶け込んだ水を缶とかペットボトルに詰めたとしても飲む頃には全部飛んじゃってますよ。水素水ってただの水を飲んでいるのと変わりませんからね。
興味のある方は、現役の科学者の方々がわかりやすく解説している動画もあります。
少し怪しげなビジュアルで始まりますが、中身はとても信頼できる内容です。こちらからご覧いただけます。
視聴者の期待に応えて、水素水をブッ叩く!!!!
私が躊躇するのは、そのお店が信じていることへの違和感というより、「わたしがこの店に感じていた“確かさ”みたいなものは、少し幻想だったのかな?」と寂しくなってしまう、そのズレの方なんです。
ああ、もったいないなぁ。鴨そば、おいしいんだろうなぁ。でも今の私は、その湯気の向こう側にうっすらと「水素水」が浮かんで見えてしまって、なんとなく足が向かなくなってしまう。
これはもう好みの問題なんでしょう。信じているものが違うと、少しだけ距離が生まれるのは、食べ物に限らず、どんなことでもあるものですから。