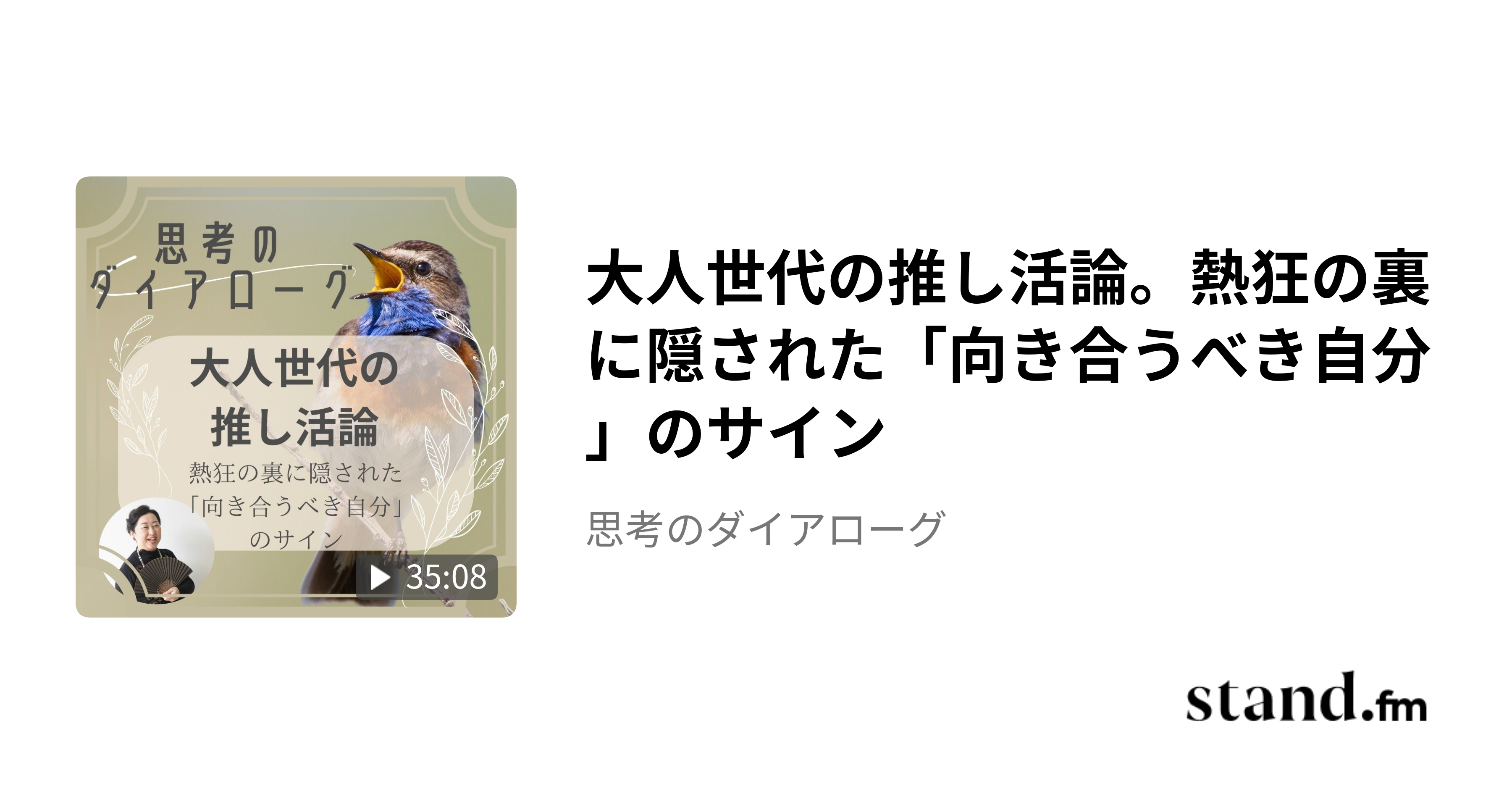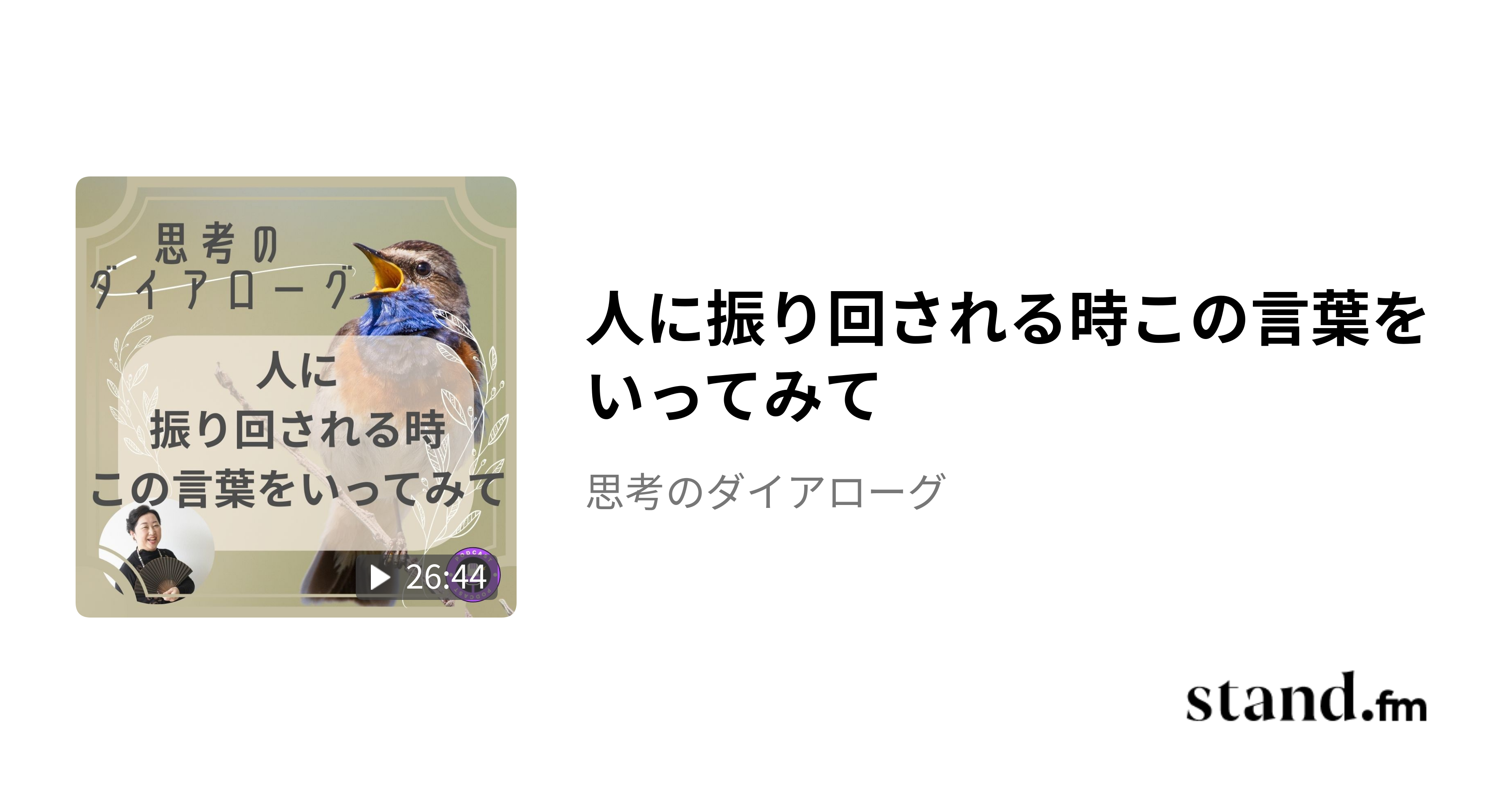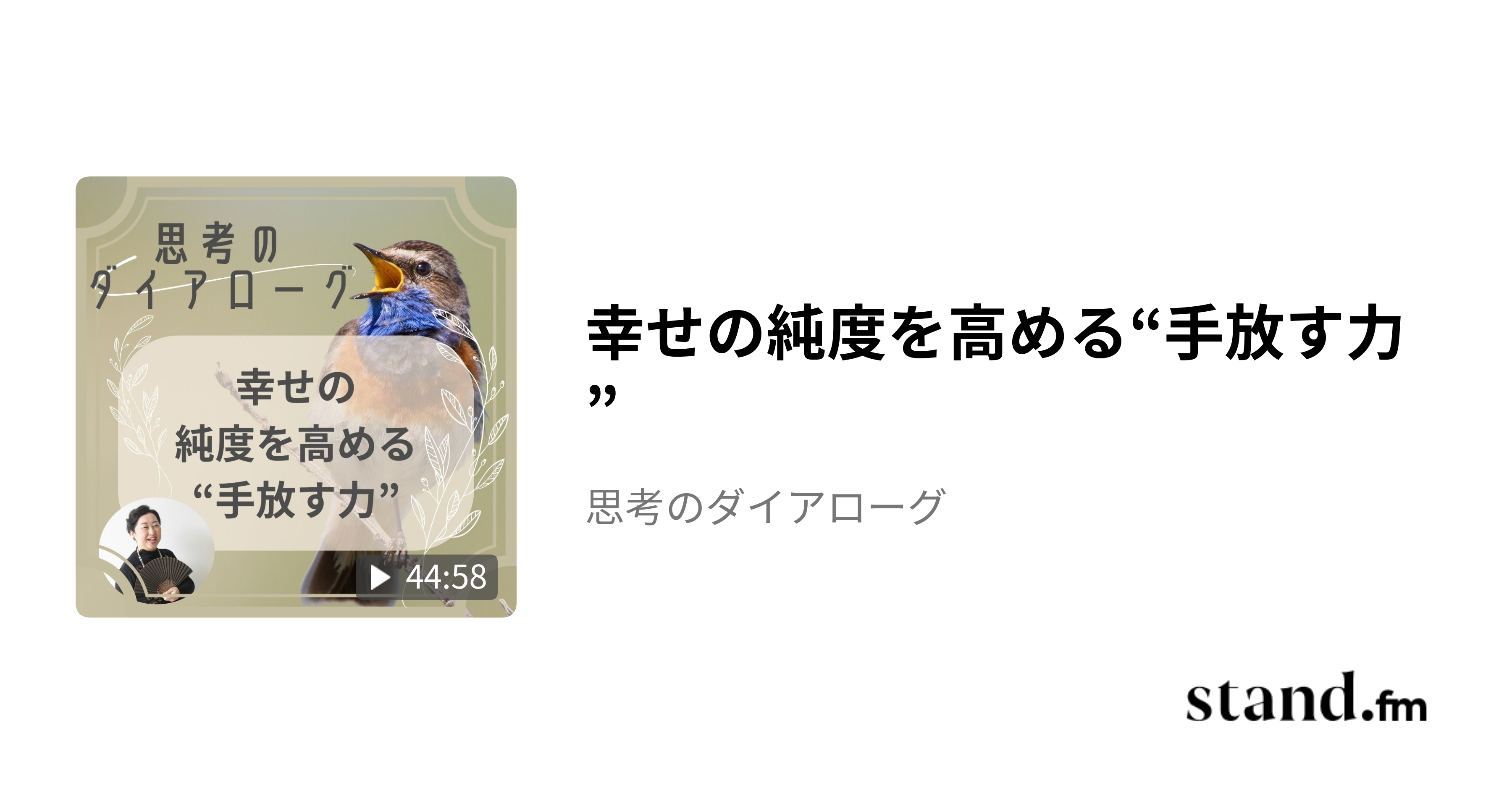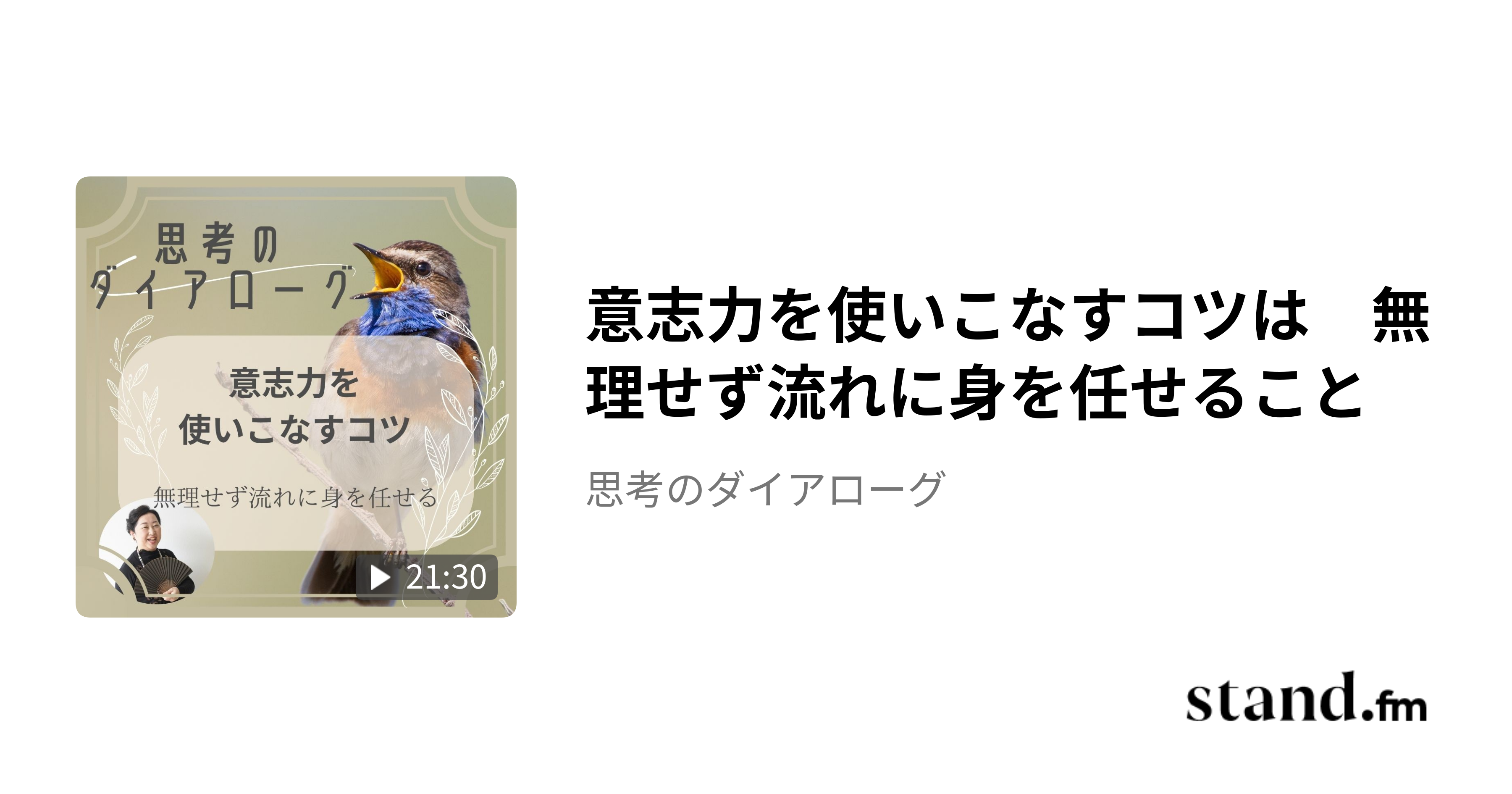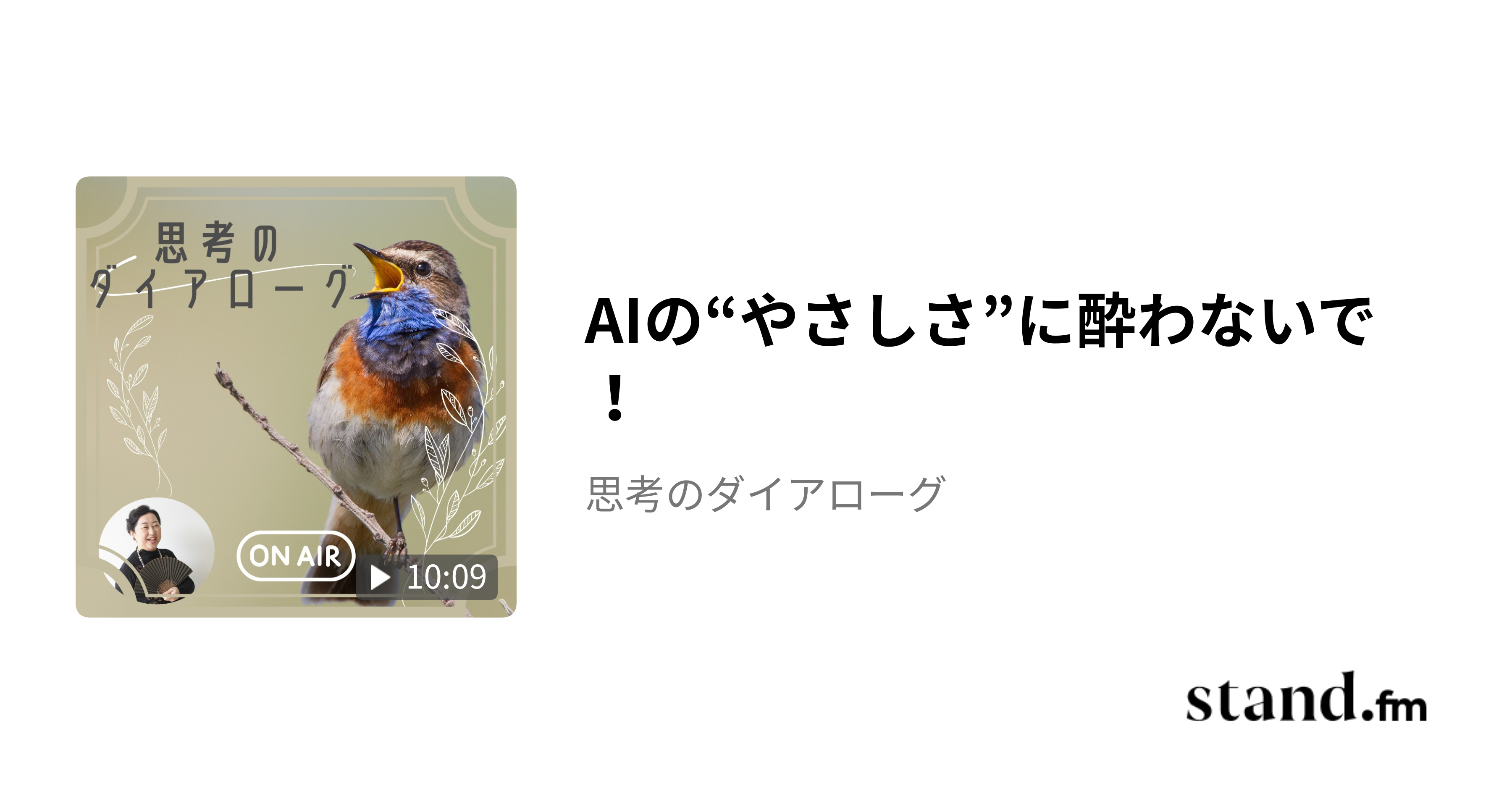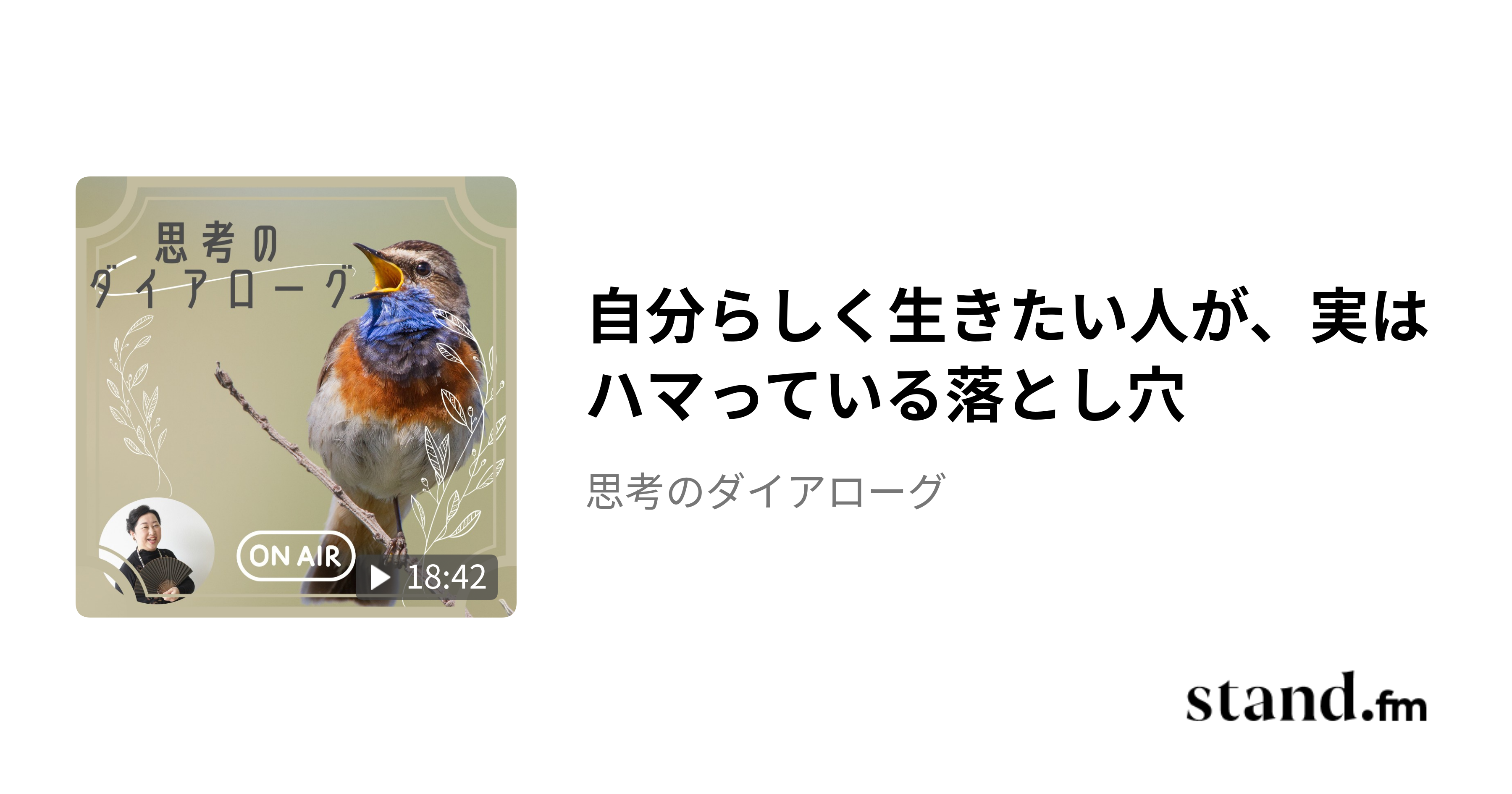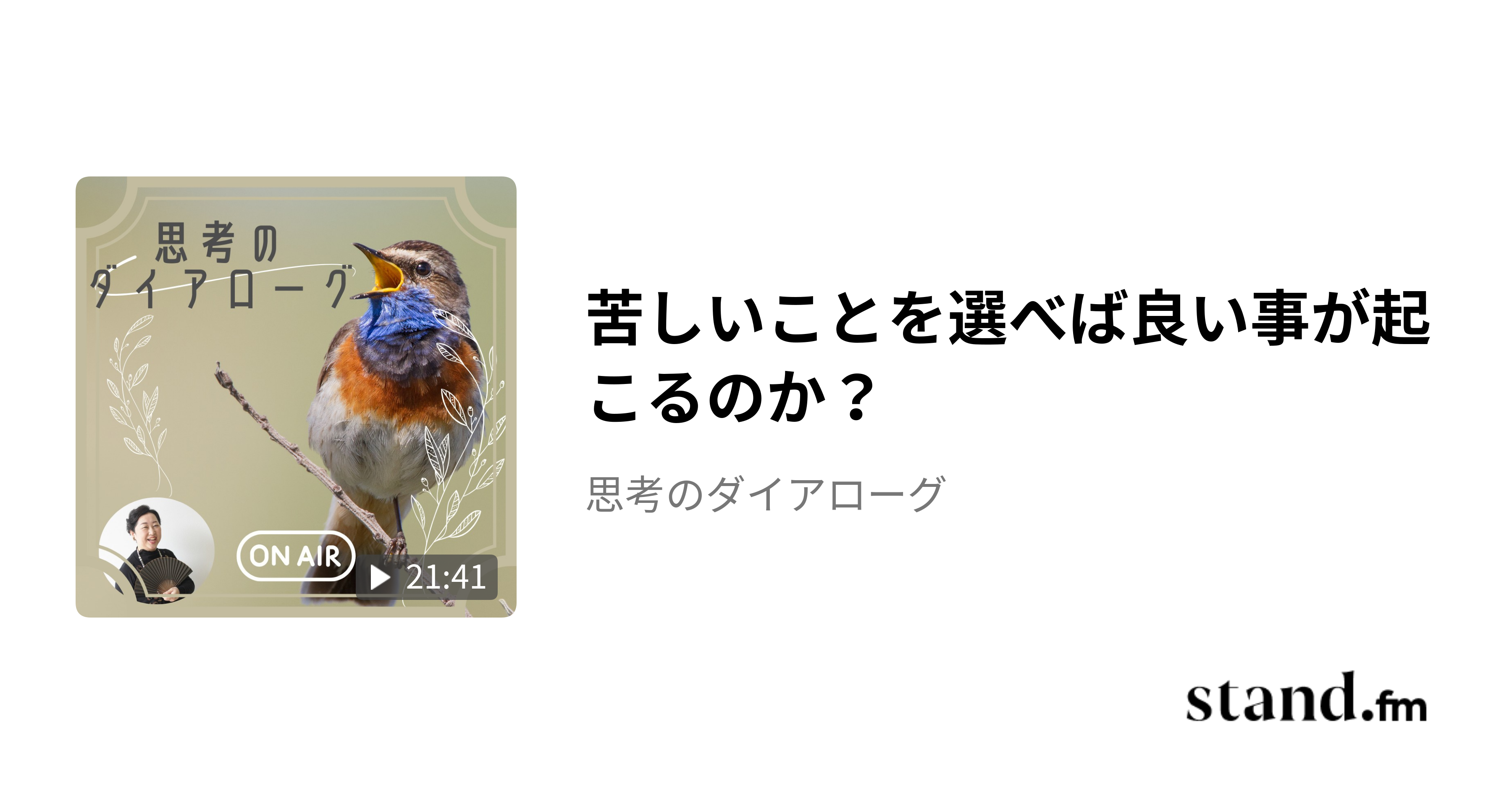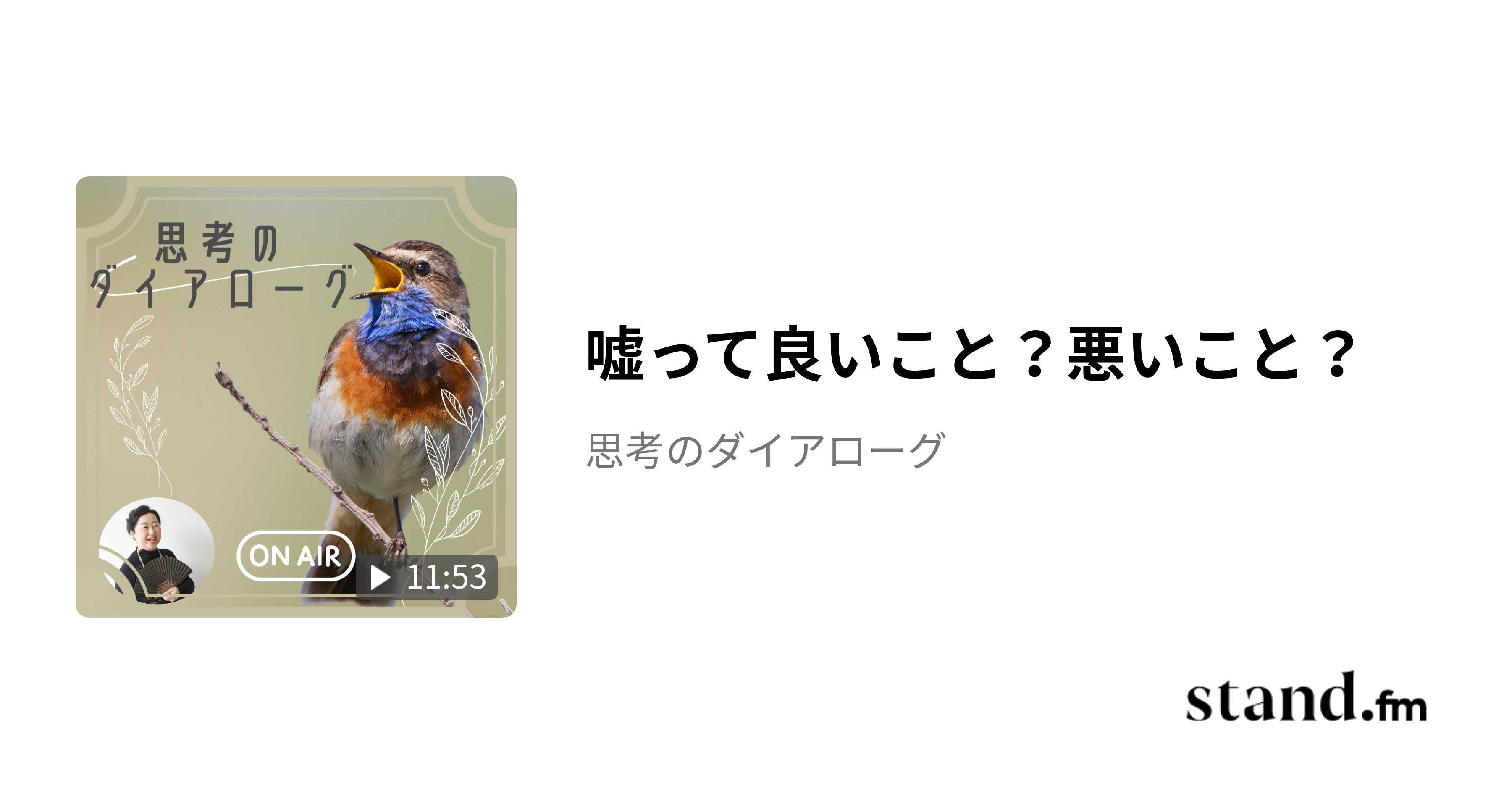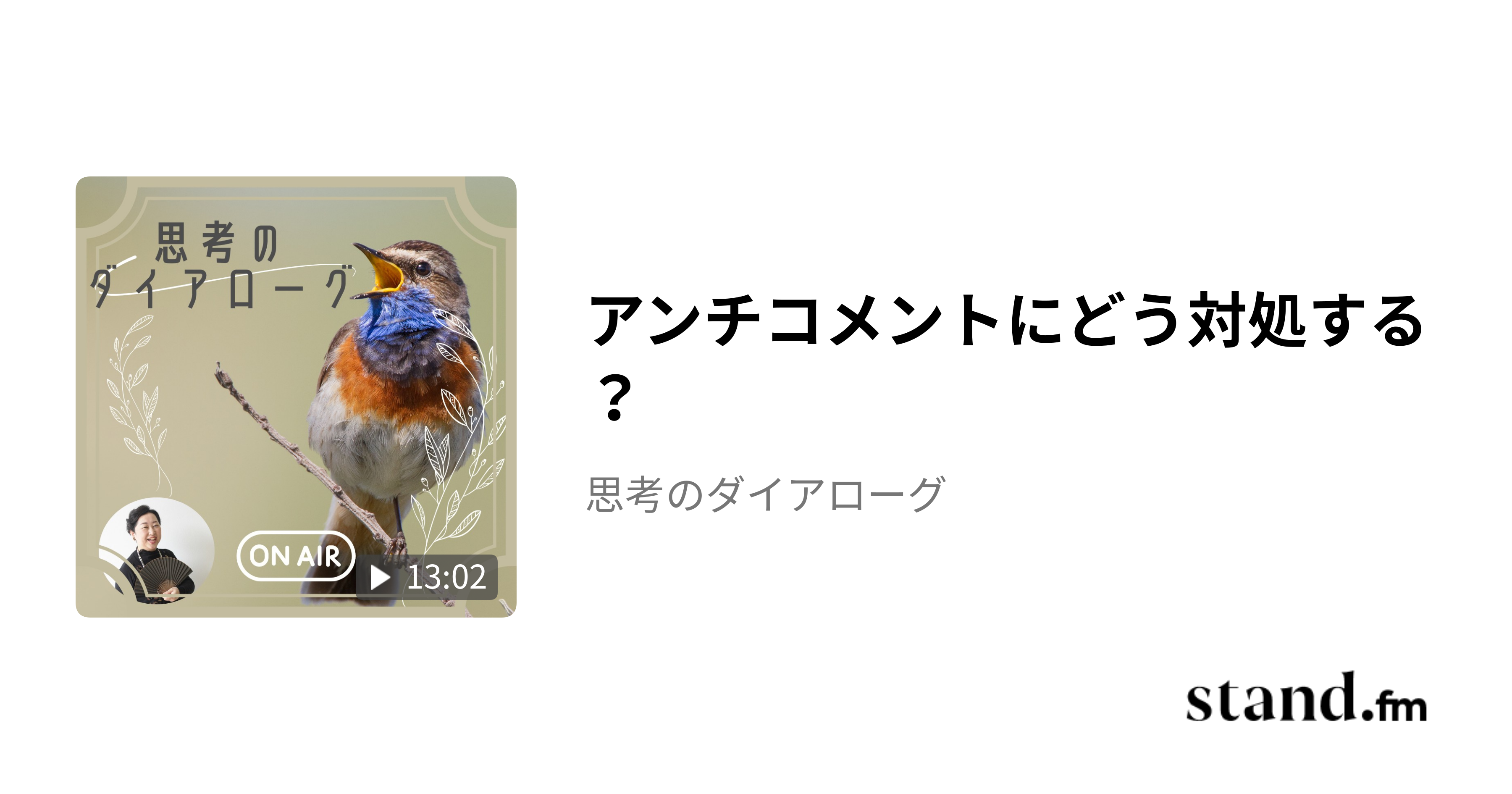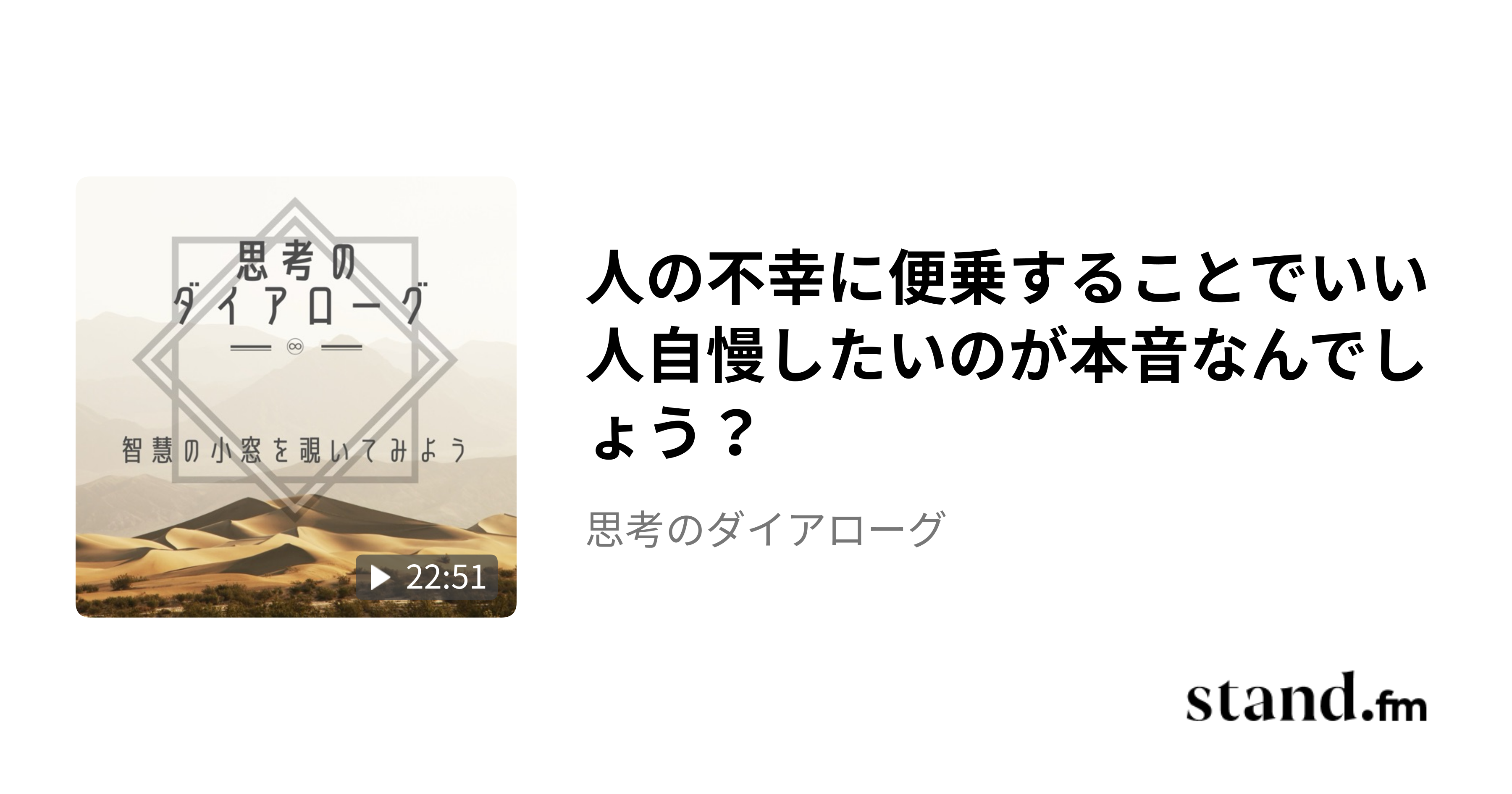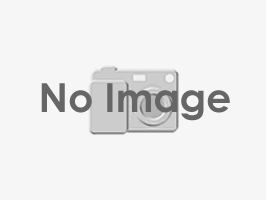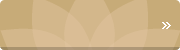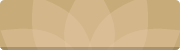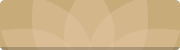思考の智慧
- 大人世代の推し活論 熱狂の裏に隠された「向き合うべき自分」のサイン
- 他人軸になりやすい人には是非この言葉を使ってほしいと思います。
- 幸せの純度を高める“手放す力”
- 意志力を使いこなすコツは 無理せず流れに身を任せること
- AIの“やさしさ”に酔わないで!本当の痛みと向き合う勇気
- 自分らしく生きたい人が、実はハマっている落とし穴
- 苦しいことを選べば良い事が起こるのか?
- 嘘って良いこと?悪いこと?
- アンチコメントにどう対処する?
- 人の不幸に便乗することでいい人自慢したいのが本音なんでしょう?
大人世代の推し活論 熱狂の裏に隠された「向き合うべき自分」のサイン

皆さんは今、夢中になっている「推し」がいますか? 最近では、特定のアイドルや俳優だけでなく、政治家である高市総理の持ち物や行動に注目が集まる「サナ活」のような現象も起きるほど、世の中は「推し活」があふれています。
誰かを応援し、そのエネルギーを自分の糧にする。それは、とても素晴らしいことです。しかし、その「熱量」が度を越しているとしたら、そこには意外な心のメカニズムが隠れているかもしれません。
今日は、「推し活と自己逃避」、そして「自分の人生を楽園にするための問題解決」についてお話しします。
若い頃の「真似ぶ」と、大人の「執着」の違い
若い頃の憧れや推し活には、大きな意味があります。 未熟な時期に、素敵な誰かを「真似る(学ぶ)」ことで、自分にないものを吸収し、自己を形成していくプロセスの一部であると考えられるからです。
しかし、ある程度の年齢を重ね、自立した大人が「異常なほどの熱量」で推し活に没頭し、資産や時間を注ぎ込み続けているとしたら…。少しだけ立ち止まって、自分に問いかけてみてほしいのです。
「私は今、何かの問題から目を逸らすために、この世界に逃げ込んでいないだろうか?」
「甘くホットな世界」は、自分を腐らせることもある
推し活の世界は心地よく、ワクワクに満ちています。日常生活に辛いことや、見たくない問題がある時、そこは最高の「避難所」になります。
命に関わるような危機なら、全力で逃げることも正解です。 しかし、本来向き合うべき自分の課題。例えば「人間関係のトラブルや、生きづらさの根源」から逃げ続けるために推し活を利用しているとしたら、その「甘い世界」は、徐々にあなた自身の成長を止めてしまうかもしれません。
刺激がないと元気が出ない状態は、自分を甘やかしているサインなのかもしれません。 本当に幸せな状態とは、刺激に頼らなくても、日々を淡々と、清々しく、安心感の中で生きられることだと私は考えています。皆さんはどう思いますか?
10年かかった「思い変え」を、半年で。
私自身、かつては非常に頑固で、自分の問題から目を逸らして生きていました。その結果、一番大切にしたい子どもたちにまで悪影響を与えていたことに気づいた時、激しい後悔と恥ずかしさに襲われました。
そこから10年。自分自身の思考の癖と向き合い、「地獄のような現実を、思考一つで楽園に変えるメソッド(思い変え)」を構築してきました。
向き合う作業は、正直に言ってつらく、苦しいものです。 自分の「恥部」や「見たくない部分」をさらけ出す必要があるからです。 しかし、そこを乗り越えて自分を律し、問題を解決し始めると、驚くほどまわりの世界がうまく回り出します。
嫌な人が周りからいなくなる
物事がスムーズに解決する
必要とされ、愛されている実感が持てる
私が10年かけてたどり着いたこの境地を、在処塾では「1対1の個別セッション」を通じて、約半年で身につけられるようお伝えしています。
あなたの人生の主役は、あなた自身
推し活が悪いわけではありません。余白として楽しめるなら、それは素敵な趣味です。 でも、もし「何かに依存しないと立っていられない」と感じているのなら、一度自分自身と向き合う勇気を持ってみませんか?
自分の問題を解決できるのは、世界で唯一、あなただけです。 もし、一人で向き合うのが難しいと感じたら、ぜひ一度お話ししましょう。あなたが「自分自身の人生」という最高の楽園を歩き出すお手伝いをさせていただきます。
体験会のお知らせ
自分の本当の問題がどこにあるのか、一度整理してみませんか? 在処塾では、個別の体験会を実施しています。 「今の自分を変えたい」「清々しい毎日を過ごしたい」という方は、ぜひ詳細をチェックしてみてください。
他人軸になりやすい人には是非この言葉を使ってほしいと思います。

みなさんご機嫌いかがですか。今日は「他人の言動に振り回されやすい」と感じる方へ、“魔法のひと言”をお届けします。結論から言うと、その言葉は——「あなたはそう思うのね。」たったこれだけです。冷たく突き放すのではなく、相手の意見を尊重しつつ、ほどよい距離を作る言葉です。事実と解釈をいったん切り分け、「では私はどうしたい?」と自分にピントを戻すスイッチにもなります。
日本人は空気を読むのが上手ですよね。渋谷のスクランブル交差点でぶつからないのは、互いの気配を読みながら「私はこっちへ行きます」という意思を同時に出しているから。意思の輪郭が弱いと、他人のベクトルに飲み込まれてしまいます。うまく人を避けることができず、ぶつかってしまうかもしれません。空気を読む優しさと、自分の意思を示す強さを両立するからこそ、スクランブル交差点でうまく道路を渡り切ることもできます。これを人間関係に重ねてみると、優しさと強さを持ちつつ、自分と他人とを切り分けることで思考を整理しやすくするとうまくやっていけるのですが、その時に使えるのが「あなたはそう思うのね」なんです。
例えば差し入れで「お好きなものどうぞ」と言われたら、最初に自分の好きなものを取ってみる。これはワガママではなく、意思表示。あなたの好みが見えると、相手も配慮の的が分かり、距離感が整います。これは「私はこう思う」であり、相手に対しての助け舟でもあるということです。
人間関係には“3:4:3(さしみ)の法則”があると私は思っています。十人いれば三人はあなたが好き、四人はどちらでもない、三人は苦手。それで十分。全員に好かれようとするほど、心はすり減ります。好みは相手の自由であり、あなたの自由でもあります。だからこそ相手の領域を尊重しつつ、自分の領域を守るために「あなたはそう思うのね」。その一言が、やさしく線を引いてくれます。
先回りして何でもやってあげるのは、一見やさしさに見えて、相手の学びを奪うこともあります。「あなたはそう思うのね」は課題の分離のはじめの一歩。相手の課題は相手に返し、自分の責任範囲に丁寧に集中すること。言い換えるなら、「そう感じていらっしゃるんですね。私はこうします」「ご希望は理解しました。今日はAを先に進めますね」と、相手を否定せずに自分の方針を静かに置く——この姿勢です。
人に振り回されて疲れてしまったら、「あなたはそう思うのね。」といってみてください。行ってみるとそれは行動になり、思っていること(思考)と行動が一致します。そこから変化がはじまるのです。まずは他人に振り回されないこと。自分の生き方の手綱を、人に持たせてはいけません。
幸せの純度を高める“手放す力”

私たちが日々の暮らしのなかで抱えているもの
それは「物」だけでなく、思考の癖やこだわり、安心への執着など、目に見えないものまで含まれています。
今日は自分が抱える様々なものを「手放す」ということについて、お話してみようと思います。
■なぜ手放すのが怖いのか
人は本能的に、変化に不安を感じます。
なぜなら「いつも通り」であることは安全の証だからです。
今まで問題なく生きてこられた経験があるわけですから、そんな安心できる環境を手放すことはなかなか難しいことは、容易の想像できます。
でも、両手に何かをぎゅっと掴んでしまっていたら、新しいものが目の前に来ても受け取ることができません。新しいチャンスや出会いを得るには、何かをいったん手放す必要があるのです。
ただ、そのときに私たちが感じるのは、不安や恐怖。
「これを手放したらもう戻ってこないのではないか」「今の安心を失ってしまうのではないか」――そんな思いが、手を固く閉じさせてしまいます。
■手放すことは消えることではない
でも実は、「手放す=消えてなくなる」ではないのです。
一度掴んだ経験や感覚は、必ず自分の中に残っています。イメージとしては、自分のまわりにふわふわ漂っている感じ。必要なら、また掴み直すこともできるのです。
だからこそ大事なのは、「自分が主体で選べる」こと。
掴むのも、手放すのも、自分の意思で決められる状態こそが自由です。
こだわりに振り回されているとき、私たちはそれに支配されているのかもしれません。でも主体性を取り戻せば、「今は掴まない」という選択肢も持つことができますよね。
■幸せの純度を高めるために
変わることは面倒くさいし、勇気も努力も必要です。
「まあ、このままでいいか」と思えば、人は流されるままでも生きていけます。でも、それは自分の幸せや充実を小さくしてしまうことでもあるのではないでしょうか。
幸せの量、というとちょっと違うかな。量というよりも、その質・純度を高めていくこと。
「昨日よりも少し軽やかに」「前よりも少し自由に」――そんな感覚を得るためにこそ、手放すという知恵が役に立つのだと思います。
手放すことで空いた手に、新しい可能性を迎え入れる。
あるいは、何も持たずにただ軽やかに歩いてみる。
そのどちらもが、自分を自由にする方法です。
■自分軸で選ぶということ
大切なのは、周りの価値観や「こうすべき」という思い込みに縛られず、自分の軸で選ぶこと。
そのうえで、周りへの想像力や思いやりも忘れない。
「手放す」とは、自己成長のための挑戦であると同時に、自分を縛る鎖から解放される行為でもあります。
たとえ一度手放したあとに掴み直したとしても、それはその時点での自分が選んだ答え。経験した分だけ、次の選択はより豊かになるはずです。
手放すことは、一番簡単に思えて、一番難しいこと。
けれど、いざやってみると「あれ、こんなものだったのか」と笑えるくらいに軽やかさをもたらすこともあります。
だからこそ、怖がりすぎずに一度やってみてほしいのです。
その選択こそが、自分自身を自由にし、幸せの純度を高めていく一歩になるのですから。
せっかく生きているなら、チャレンジしてみませんか?
違っていたりしっくりこなかったら戻るという選択をすればいいだけです。
記事を読んでくださって ありがとうございます
意志力を使いこなすコツは 無理せず流れに身を任せること

本日のお話は、「意志力」というテーマでお届けします。皆さんは意志力という言葉をどんなふうに捉えていますか?
意志力とは、何かを成し遂げるために自分の考えをコントロールし、行動に移す力だと思う方が多いかもしれません。でも実は、意志力って、私たちが強くコントロールしようとすればするほど、なかなかその本当の力が発揮できないことがあるんです。今日はその理由をお話ししながら、実際に私がどうやって意志力を使っているかをご紹介したいと思います。
■「意志力」と「力を入れすぎる」こと
私自身、もともとはとても強い意志を持つタイプでした。効率的に物事を進めようとしたり、目標を達成しようとすると、ついつい「こうなればいいのに」「ああなればいいのに」と思ってしまう。
すると自然に「もっと頑張らなければ」「どうしてもこうしたい!」という気持ちが湧いてきます。しかし、こうした気持ちを強く持ちすぎると、実は逆効果になってしまうことがあるんです。つまり、力を入れすぎてしまうと、余計にうまくいかない。
■過密スケジュールと私の意志力の使い方
先日、私のスケジュールはかなり過密で、まるで意志力が試されるかのような日がありました。午前中に3時間のセッションがあり、その後すぐに大学病院でCT検査を受ける予定が入っていたんです。しかも病院は少し遠く、混雑する時間帯だったので、余裕を持って行かなければならないというプレッシャーがありました。
こんな時、私はつい「セッションを早く終わらせよう」「少しでも余裕を作らなきゃ」なんて考えてしまいがちです。しかし、そんな気持ちが湧くと、「あぁ自分都合でどうにかしたいという気持ちになっちゃってるなぁ。コントロールしようとしている」と思うようにしています。そしてそんな時にこそ私は「なるようになる」と自分に言い聞かせます。「いろいろ考えたところで、結局は流れに任せるしかない」と。結局、何も無理に変えようとせず、セッションをする事にしました。
■思わぬ展開:突発的な出来事
そんなこんなでセッションが始まってしばらくして、突然、クライアントさんのスマホがなりました。「保育園からで、子どもが具合が悪くてすぐに迎えに行かなきゃいけない」とのこと。その瞬間、「あ、こういうことか!」と思いました。もし私がセッションを早く切り上げていたとしても、結果的に同じことが起きたかもしれませんが、結局セッションを30分早く終了する事になり、クライアントさんは自宅にいたことでスムーズにお子さんをお迎えに行けたようですし、私も時間に余裕を持って、受診に向かうことができました。
このように、何もかもが「ちょうど良いタイミングで」うまく収まったわけです。これも一つの示唆です。何かをコントロールしようとすることが逆に空回りしてしまうことがあるけれど、何もしないでお任せすることで、結果的に必要なものが最適なタイミングでやってくる、ということです。
■思考の力:お任せすることの大切さ
「なるようになる」「大丈夫」と心を落ち着けてお任せする。私はこの考えを生活の中でよく実践しています。例えば、混んでいるお店や駐車場で、普段なら焦ってしまう状況でも、「大丈夫、すぐに空くはず」と考えます。実際、驚くことに、目の前の駐車場が急に空いたり、席が空いたりすることがよくあります。
こうしたことが偶然だとしても、私はその「ちょうど良さ」に感謝するようにしています。この「お任せする」力こそが、意志力の真髄なのかもしれません。焦らず、力を抜いて、物事を流れに任せることで、結果として自分にとってちょうど良いものがやってくるのです。
■手放しと感謝の力
意志力とはりきんで物事を成し遂げることではなく、むしろ「手放し」「お任せ」といった柔軟さが重要なのだと私は感じています。力を抜いて、できることをしてあとは流れに身を任せる。その結果、予期せぬ良いことが起きることもあります。この「手放す」ことは、私が実践しているトレーニングの一つで、日々の中で意識的に行っています。
■意志力と柔軟さの関係
意志力を強く持つことは重要ですが、あまりにも固執してしまうと、逆に自分自身を苦しめることになります。むしろ、柔軟に考え、状況に応じてお任せすることで、物事がスムーズに進むことが多いという実感があります。私にとって、意志力は「頑張る」「無理をする」ことではなく、必要な時に適切に力を抜き、流れに身を任せることなのではないかと思うのです。
今日は、私自身の体験を通して意志力の使い方をお話ししました。意志力を正しく使うことで、物事はスムーズに進み、予期しない素晴らしい結果が得られることもあるんですよ。大切なのは、柔軟さを持ち、流れに身を任せること。これを実践することで、毎日の生活がより楽になり、気持ちも楽に過ごせるようになります。
AIの“やさしさ”に酔わないで!本当の痛みと向き合う勇気

私たちのまわりには、AIを友達のように使う人がどんどん増えているように感じます。
相談をすると、まるで心を読んでいるかのように共感し、励ましてくれる──
そんな“優しさ”をAIに見出している人も少なくないでしょう。
でも、そこで立ち止まって考えてみませんか?その「心」は、本当に存在するものなのでしょうか。
AIに心はない。
これは誰もが知っている事実です
。AIが発する共感や励ましの言葉は、膨大なデータの集積から導かれた「表現のひとつ」にすぎません。にもかかわらず、私たちはその言葉を目にした瞬間、「ああ、わかってくれている」と感じ、「元気づけられた」と思ってしまう。人形や車、ぬいぐるみに名前をつけて話しかけるのと同じように、AIという「無機物」に魂があるかのように扱ってしまうのは、人間の想像力が「ないもの」を勝手に補完しようとするからではないでしょうか。
しかし、この想像力こそが、私たちの人間関係においてもっとも大切な「思いやり」の源なのだと思います。
相手の気持ちを想像し、配慮を生み出す能力は、まさに想像力なしには成り立ちません。
だからこそ、AIが放つ「やさしい言葉」に触れてホッとする瞬間もあるけれど、それはあくまで“対症療法”であって、心の奥底にある問題を解決するものではないのです。
私が思うに、「心がある」とは、身体を持ち、そのフィジカルを通して体験や経験を重ねること。痛みを知り、笑い、迷い、立ち上がる──そうした積み重ねが、いわゆる“魂”を育むのではないでしょうか。私たちはまさに身体と魂のハイブリッドであり、その実感こそが「生きている実感」につながります。けれど、AIに励まされ、わずかな安心を手に入れたとしても、自分自身の深い感情や無意識のクセを変えるには至りません。
では、AIとはどう付き合えばいいのか?
私たちには、AIをツールとして賢く使いながら、同時に一定の距離感と客観的な視点を保つ必要があります。
- AIの言葉に救われる自分を否定せず、あぁそうかと受け止める
- それが「情報の表現」であることを忘れず、依存しすぎない
- 本当に向き合うべきは、自分自身の身体感覚や体験から湧き上がる声であることを意識する
AIに慰められてホッとしたその後、
「これで私は本当に癒やされているのか?」
「心の芯(真)の部分に、ちゃんと届いているのだろうか?」
と自問してみてください。
AIのやさしさを享受しつつ、私たちが本当に大切にすべきは、自分の身体を通して感じる「痛み」や「喜び」という、ほかでもない自分自身の声です。AIと適度な距離を取りながら、自分の心に耳を澄ませる習慣こそが、真の変化を生み出す第一歩になるでしょう。
自分らしく生きたい人が、実はハマっている落とし穴

「自分らしく生きる」とか「本当の自分を取り戻す」という言葉を、
いろんな場面で目にします。
SNSでも、本でも、セミナーでも
「自分らしさ」がキーワードになっていて、
まるでそれを見つけることが“人生の正解”のように語られる。
それ自体は自分を知ってラクに生きるためには必要なことですから、大事なことです。
しかし、まるで、「自分らしさ」を探すことがゴールで、
それを見つけさえすれば人生はうまくいく、と語られることに私は違和感を感じてしまいます。
実際には、そんなふうに「自分らしさ」を取り戻した(ように感じた)あと、
ぽっかりと空白のような感覚にとまどう人が増えているように感じます。
「あれ? 自分らしくなったはずなのに、なんか物足りない」
「本当の自分を見つけたはずなのに、前より寂しい気がする」
もしかしたら、「自分らしさを探すこと」が“目的そのもの”になってしまっているのではないか?
目的を果たして、安心したもののその自分らしさをどう扱って良いか戸惑っているようにも感じます。
本当は、「自分らしくあること」って、何かを“するための土台”であって、
それ自体がゴールじゃないはずです。
でも、「私はこれでいいんだ」っていう安心感を得た瞬間、
その次に何をしていいかわからなくなる。
それは、自分らしさを見つけたのではなく、
「自分らしく見せる」ための役割に新しくハマってしまっただけなのかもしれません。
自分らしさは、守るものでも、飾るものでもなく、
日々、何を選び、どう在るかの“手ざわり”のようなもの。
自分軸の判断基準であり
毎日を心地よく過ごすためにあるものではないでしょうか。
今日の選択に納得しているか。
ちいさな違和感をごまかしていないか。
人と比べず、自分と対話しているか。
そういう積み重ねが、自分らしさを形成し私になっていく。
「自分を取り戻す」って、
どこかに置いてきた自分を探し出して、
取り戻して、
元通りの姿に戻ることじゃなくて、
これからを生きる自分を、新たに“育てていく”ことなのかもしれません。
“自分らしさ”が声高に語られるようになった今だからこそ、その言葉に踊らされてはなりません。
「自分らしさ」がわかったからといって
キラキラしたまわりから羨ましがられる生き方ができるわけでも
自己肯定感が爆上がりして毎日ハッピーになるわけでもありません。
その後自分らしくあり続けることが何よりも重要で
それはもっと静かで、もっと地味で、もっと、地に足のついた営みなのです。
「自分らしさ」を見定めたあなたは
「自分らしく生きる」スタートに立っただけのことです。
これから寿命が尽きるまであなたらしく生き続けられるのです。
こんな面白いことはないではありませんか。
苦しいことを選べば良い事が起こるのか?

「苦しい方を選んだ方が成長するよ」とか
「楽な道ばかり選んでたらダメになるよ」とか
聞いたことありませんか?
基本性格が真面目だったり、言われたことを素直に受け止めるタイプの人は、
“苦しい=正しい”みたいな謎の思い込みが、がっちり思考に入り込んじゃってたりする。
で、選択肢が出てくるたび、
「どっちが苦しいか」で選んでいくわけですが、それしていると無意識はちゃんと苦しい方を選んでいるあなた自身が「苦しみたいのね」と勘違いしていく。
それを続けてたら、
まぁ〜しんどいよね。単純に、疲れる。消耗する。ちゃんと苦しい世界で生きていくことになる。
そもそもね、
「苦しさ」って、それ自体は目的じゃないはずなんですよ。
「その苦しさの先に、自分にとって意味がある何かがあるかどうか」
これが本来の問いのはず。
でも気づくと、「あっちの方が苦しいからこっちを選ぶ」っていう
苦行マインドが目的化してて、
選択の軸がズレてるんじゃないかと。
苦しいことを選ぶ=すごい、えらい、偉人
みたいなものは、間違いなく幻想です。
それよりも、
「自分にとって必要かどうか」で選ぶことの方が、今の自分にちょうどいい、納得できる選択になるんじゃないでしょうか。
時には楽な方が“必要な道”ってこともあるし、
逆に、しんどくても「今はやっとくべき」って感じることもある。
だから、選ぶ基準を“苦しさ”にしない。
そうするとだいぶ心が楽になって、それ自体がほら「楽園思考」ですよ。
もちろん、人は苦しみから学ぶこともあるし、
痛みを通してしか見えない景色ってのもある。
だけど、それは「苦しみを選んだから報われた」わけじゃなくて、
「その出来事を、自分なりに意味づけして乗り越えた」からこそ、
何かを得られたんだと思うのです。
もし今、あなたが「苦しい方を選ばなきゃ」って思ってるなら
「その苦しみ、本当に今の私に必要?」って問いかけてみてください。
苦しみそのものがご褒美を連れてくるわけじゃない。
必要なことを、必要なだけ、やる。
それで、ちゃんと道は開けていきます。
嘘って良いこと?悪いこと?

4月1日です。
こうして一年があっという間にすぎていくのですね。
エイプリルフールは嘘をついてもいい人いうことで、今日ばかりはさまざまな情報を疑いの目で見る頻度も上がりそうです。
人と関わる中で最も大切なことは「ラポール」だと言われます。相手と信頼関係を結ぶことですが、そうするためには正直さは必要なわけですが、正直すぎても人を傷つけてしまう事がありますよね。過ぎたるは及ばざるが如しで、どんなこともちょうど良いがあるものです。
嘘をつくというよりも、相手を思いやるからこその真っ正直ではない、優しい嘘や方便があって良い時もあるということです。
人とうまくやるのは距離感も、付き合い方もいろいろです。どんなこともうまくやれる「これだ!」という方法はありません。あれやこれやを試して、ちょうど良いことを見つけるしかありません。
嘘をつくのは良いことでも、悪いことでもなく、その得度きでよくもなるし悪くもなるということでしかないのかもしれません。
アンチコメントにどう対処する?

最近の配信は音声とブログを主に発信しています。
気軽に、ストレスなく発信できるのは今は音声配信が一番しっくりきているので、しばらくはこれで行こうかと思っています。
私の配信する内容は、毎日の出来事から何か感じたことや考えたことなのですが、実際アナリティクスを見ると政治的な内容の配信が一番再生してもらえているようなんですよね。
これって、他の配信者さんもそうらしくて、政治的なことを発信すると聞いてはもらえるけれどもアンチコメントも増えてしまうらしい。
私にもご丁寧にアンチコメントを書いてくださる方がいて、それを見つけた時には「あぁ再生数が伸びているんだな」と思うんです。
私も公開で配しているからには、相当キレている時以外は(あまりありませんが)丁寧な言葉とか、極端な批判などは避けているので、アンチコメントを書こうと思う人はあまりいないんじゃないかと思うんです。それでも分母が多くなると、自然と私の波動関数外の人にも届いてしまってコメント書きたくなっちゃう人が出てきてしまうのかもしれません。やっぱり人間は動物の生体的な集団というより、ハチとかアリとかの昆虫の生態(社会)形態に似ているのでしょうね。
アンチコメントも自分が不愉快に感じるのはなぜかとか、必要なことしか起きないとか、逆に考える必要はあるのかなど、知恵のもとになる考えを巡らすことで自分のためになっているなと考えてしまうのもありかと思います。
人の不幸に便乗することでいい人自慢したいのが本音なんでしょう?

ドライブ中にラジオから聞こえてきたのが、救急車を設計してる?つくっているという人の話で、
「以前救急車を作る仕事をしていたが、救急車を見るたびに誰かが具合が悪かったり、命の危険がある時に出動しているんだよなと思ったら、あまり喜べなかった」みたいなコメントを読んでいて、ちょっとモヤっとしたんです。
救急車は人の命を助けるための車なわけで、それって基本的には良いことだし、その車を作っている事は悪いこと?悪いことしてるって感じてしまうのは、百歩譲っていいとして、なんでそう考えるかなって。
ラジヲで読まれるコメントとして、普通ではない逆張りのコメントとして書いてきたのかもしれないけれど、それにしてもアマノジャクですよね。
自分は人の不幸で飯食ってるみたいな言い方は、謙遜しているようで実はそんなことまで考えている私ってすごいでしょって、聞こえてしまうんですよ。
それって被害者ドラマしてるなって思います。
被害者ドラマをしている人って、自分がこんな可哀想なことになっているのはあなたのせいですよって、相手に罪悪感を抱かせることでエネルギーを奪っているんですよ。そしてそれを無自覚にやっているのがなんとも厄介。
そういうことをする人が身近にいると、付き合っていると疲れてしまいますよね。
なんにせよ、コントロールドラマと呼ばれるそれは、自分もやらない、配役されそうになってもそれにはに習いのが一番です。ここでも自分軸を試されますね。
お互いに相手に寄りかからずに、お互いが助け合える距離感で付き合うのが一難心地が良いように思います。