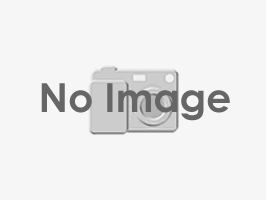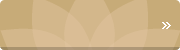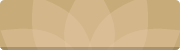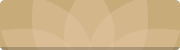思考の智慧
- 理解しようとするから苦しいんだよ 〜理解ではなく「受け止める」
- あれ、これ、それで話ができるのは「感覚」優位だからかも
- 結果を求めすぎるのは「視覚」が優位だからかも
- 鋼のメンタルは自分軸でつくる
- メンタルタフネスに必要な「鈍感力」と「忘却力」
- 「触って嗅いで味わって」 五感が心を癒す
- 気持ちが伝わる唯一の方法
- 直感を信じる難しさ
- 智慧を使い倒せ!
- 不機嫌ハラスメントに負けるな!
理解しようとするから苦しいんだよ 〜理解ではなく「受け止める」

多様性と違いを認めること 〜理解ではなく「受け止める」ことの大切さ〜
私たちは日々、さまざまな人と関わりながら生きています。文化や価値観、人生経験が異なる人たちと接する中で、「多様性を認める」ことの重要性がよく語られます。しかし、他者の違いを本当に「理解する」ことは可能なのでしょうか? 今日は、「理解する」ことの限界と、「受け止める」ことの大切さについてお話ししたいと思います。
多様性を認めるということ
人はそれぞれ異なる環境で育ち、異なる経験をし、異なる価値観を持っています。世界を見渡せば、文化や言語、生活習慣などの違いは無限に存在します。そうした背景の違いを踏まえたとき、当然ながら「人はそれぞれ違う」ということが前提になるはずです。
この「違いを認める」という考え方は非常に重要です。自分と他者の感じ方や考え方が異なることを理解し、その違いを尊重することこそが、共存や調和の第一歩になります。
しかし、多くの人が「違いを認める」=「相手を理解すること」だと考えがちです。相手を理解しようと努力すること自体は決して悪いことではありません。むしろ自然な行動です。ただし、ここに大きな落とし穴があるのです。
理解しようとすると苦しくなる理由
私自身、「理解しようとすること」は必ずしも必要ではないと考えています。なぜなら、完全に他者を理解することはほぼ不可能だからです。
人はみな、異なる人生を歩み、異なる価値観や感じ方を持っています。それを100%理解しようとすると、「なんで理解できないんだろう」「なぜあの人はあんな行動を取るんだろう」と苦しくなってしまいます。理解できない自分を責めたり、逆に相手を責めたりすることもあるでしょう。
でも、そもそも他者を完全に理解することなどできるはずがないのです。「理解しよう」と無理に努力して苦しくなるくらいなら、「理解しなくていい」と思うことが大事です。
「理解するのは無理」と思うと冷たく聞こえるかもしれませんが、実はそうではありません。理解しなくても良いからこそ、もっと自然に相手と接することができるようになるのです。
「理解する」ではなく「受け止める」
では、理解できない他者とどうやって関係を築いていけば良いのでしょうか? その答えが「受け止める」という姿勢にあると思います。
「理解しよう」とするのではなく、「ああ、そういう考え方もあるのね」と受け止めるだけで良いのです。
- 自分とは違う考え方を知る
- 同意しなくても「そういう感じ方をする人もいる」と認める
- 「違う」という事実をそのまま受け入れる
これだけで、他者との関係がぐっと楽になります。「理解しなくていい」と思えば、無理に共感しようと頑張る必要もなく、相手に対して寛容になれるのです。
「理解する」のではなく「共感する」
ここで大切なのが、「理解」と「共感」は違うということです。
「理解」は「相手の思考や感情を自分のものとして理解しようとすること」
「共感」は「自分とは違うけれど、そう感じるのも自然だと認めること」
「わかる、わかる」と言うことは時に傲慢になりかねません。実際には自分が経験していない感覚を「わかる」と言うのは難しいからです。
でも、「ああ、そうなんだね」と受け止めることはできます。同意できなくても、「あなたはそう感じているんだね」と受け入れることはできるのです。これこそが「共感」だと思います。
「小さな袋」に分けて考える
他者の価値観や考え方をすべて自分の中に取り込む必要はありません。むしろ、個々の違いを「小さな袋」に分けて持っておけば良いのです。
- ある人はこう考える
- 別の人はこう感じる
- 自分はこう思う
これらを一つ一つ分けて、必要に応じてその袋を開いて確認すれば良いのです。無理に混ぜ合わせて「同じように理解しよう」としなくても良いのです。
「理解する」のではなく、「受け止める」。
「わかる」ではなく、「そうなのね」。
このシンプルなスタンスが、他者との関係をスムーズにし、結果的に自分自身も楽になるのではないでしょうか。
多様性を認めることは、「他者を理解する」ことではなく、「他者の違いを受け止める」ことにあると思います。理解できなくてもいい、わからなくてもいい。ただ「ああ、そうなのね」と受け止めるだけで、他者との関係は自然に良好になるでしょう。
「理解しよう」と無理に努力するのをやめ、「受け止める」姿勢を持つこと。これが、多様性を認めるための第一歩になるのではないでしょうか。
あれ、これ、それで話ができるのは「感覚」優位だからかも

「あー、ほらあれとって」と、主人がよく言います。
私は(あれって何だよ!)と思いながら
「あれって何?」と聞き返します。
それでもあれだよ、あれ!と言いつづける夫。。
もう毎日がそんな感じで、私は優位特性 視覚タイプなので(あれ)では何だかわからないので具体的に何かと言って欲しいのに、感覚タイプの主人は(俺の中ではアレと言ったら〇〇なのに何でわからないんだよ!)と、彼は彼で私がツーカーでないことにイラついていました。
こういうことが毎日のように起こると、ちゃんと夫婦関係が悪くなって、以前はもう一緒にいられないと本気で考えることもありました。
でも今は、あれこれな主人の言い方は、彼の脳の利き感覚が私と違うからだとわかっているので、イライラするより(仕方がないなぁ付き合うか)な感覚で話すようになりました。解放された気分です。
これらのタイプを優位特性というのですが、自分と相手の脳の利き感覚が違うから、考え方や大事なものが違うので話が食い違ってしまってコミュニケーションがうまくいかないことがあります。これを知ってから、話がうまく伝わらなくても、相手を責めるようなことはなくなりました。逆に、相手のタイプに合わせて受け答えができるようになって、イライラも減りました。
このタイプ分析の講座を久しぶりに開きます。
これは営業のクロージングや、家族や友人とのコミュニケーション、子育てにも有効です。ぜひおいでください。
オンライン講座なので、お家で受講できます。
*開催日時
2023年3月8日(土)11:00〜13:00 残4席 ←クリックしてすぐにお申し込み
2023年3月17日(月)11:00〜13:00 残1席 ←クリックしてすぐにお申し込み
*参加費
8,500円(税込)
結果を求めすぎるのは「視覚」が優位だからかも

話が長くて、結論もオチもない人っていますよね。
私はついついそういう人と話をしていると
「で、何が言いたいの?」
と言いたくなってしまいます。
以前は言っていたかもしれません。
しかし、今は違います
話が長くて、結論もオチもない人は、脳の利き感覚が「聴覚タイプ」の人。
で、「何が言いたいの?」と思ってしまう私は「視覚タイプ」。
経過や手順よりも、結果に重きを置くタイプです。
これらのタイプを優位特性というのですが、自分と相手の脳の利き感覚が違うから、考え方や大事なものが違うので話が食い違ってしまってコミュニケーションがうまくいかないことがあります。これを知ってから、話がうまく伝わらなくても、相手を責めるようなことはなくなりました。逆に、相手のタイプに合わせて受け答えができるようになって、イライラも減りました。
このタイプ分析の講座を久しぶりに開きます。
これは営業のクロージングや、家族や友人とのコミュニケーション、子育てにも有効です。ぜひおいでください。
オンライン講座なので、お家で受講できます。
*開催日時
2023年3月8日(土)11:00〜13:00 残4席 ←クリックしてすぐにお申し込み
2023年3月17日(月)11:00〜13:00 残1席 ←クリックしてすぐにお申し込み
*参加費
8,500円(税込)
鋼のメンタルは自分軸でつくる

日曜日には兵庫県知事選挙が行われます。
メット上ではなかなかの盛り上がりで、関東では報道があまりされていませんが組織票と無党派の接戦になっているようです。
今回のことはマスコミの印象操作に踊らされた面があり、今の時代の情報の取捨選択の難しさを考えさせられました。
先知事が辞職ではなく失職を選んだことや、人事局長がなぜ氏を選ぶほど追い詰められたのかなど、不自然なことはあって、その違和感を信じることが大事だったのだと考えさせられました。
やっぱり直感は大事です。
今回の動画は
元兵庫県知事斎藤氏の鋼のメンタルは、どうして作られたのか?
について語りました、
メンタルタフネスに必要な「鈍感力」と「忘却力」

ただいま絶賛報道中の「おねだり知事」の百条委員会のやりとりを見て、気づいたことをお話しします。
そもそも私はパワハラも、視察先でお土産を要求するのも公僕である知事のすることか?との疑問もありますが、それよりも「公益通報」がしっかりと機能しなかったことの方が問題ではないかと思っています。
知事の言動が度をこしていて、周りの役職の人たちが仕事の不透明感や、やりにくさを抱えていていたための内部告発だったわけです。その人が自死を決意するにいったことは如何ともしがたく、これをこのままにしては公正さを保つことの意味すら有耶無耶にされてしまいかねません。
百条委員会ではそこのところをもっと突っ込んではっきりさせていただきたいと思っています。
それとは別に、あの知事の受け答えからなんとメンタルが強い火地なんだろうかとの印象を受けました。彼がしたことややっていることは置いていいたとして、あのねっbタルのタフぶりは「メンタルタフネス」を超えた「メンタルモンスター」と言われても仕方がないかもしれません。
そもそも思いやりや気配りができる人こそ、周りのことを気遣うあまり考えすぎて他人軸になりがちで、だからこそ不安をかき集めてしまって心が病みがちであることは否めません。
そんなおり、彼のように事実と感情を切り分けることで自分の心を守ることもある意味防御としてはありなのかもしれません。周りに鈍感であること。つまり「鈍感力」を持つということです。
そして苦しみや不安を忘れる力「忘却力」これも毎日を過ごす中で、未来を今として生きなければならない私たちには、必要なものです。
不安や悲しみはうまくいかなかった記憶に紐づく感情で、それがあるから危険から自分を守ることができると言えます。しかし、そればかり気にしすぎていると前に進むことができなくなることもあり、停滞を招きます。進化していくことができなくなってしまうかもしれないのです、そんな時に忘れる時ことは必要な機能です。
「鈍感であること」も「忘れること」も、一見悪い事、弱みに見えますが、これらも必要だからある機能であり、使っていくことでタフに萎えたり、進化できたりするのかもしれません。これも思いかえです。
「メンタルモンスター」になってしまうと、自分勝手で守ることが攻撃に変化することしらあります。こうなってはいけないのですが「タフ」であることは自分に多くの耐性をつけ、より良い道を選択して集中力でそれを成し遂げることができるかもしれません。
自分軸のある「メンタルタフネス」を身につけてくださいね。
「触って嗅いで味わって」 五感が心を癒す

私たちの日常生活の中で、どうしても見過ごされがちな「五感」の重要性に目を向けてみましょう。日々の忙しさやストレスに押しつぶされそうになると、どうしても頭の中で悩みが大きくなり、周りの世界が見えなくなってしまうことがあります。そんな時こそ、五感を使って自分でストレスをコントロールしてみましょう。
五感とは何か?
まずは五感について考えてみましょう。
五感とは、「視覚」「聴覚」「触覚」「嗅覚」「味覚」の5つの感覚のことを指します。これらの感覚は、私たちが日常生活を送る上で欠かせないものであり、それぞれが私たちの脳に重要な情報を届けています。
普段は、特に視覚や聴覚が優先的に使われます。見ること、聞くことから最も多くの情報を得ているからです。しかし、それ以外の触覚・嗅覚・味覚は、主な情報(視覚・聴覚)に付随する情報として、私たちの脳の中でのネットワークの隙間や曖昧さの追加情報として使われています。それらが私たちの経験値から得られて直感を後押ししていると考えられるのです。情報量としては少ないかもしれませんが間違いなく必要で、それらを無視することは完成を蔑ろにすることのほかなりません。
五感を活用してストレスを緩和する方法
1. 触覚を意識する
触覚を活用する方法としては、例えばマッサージがあります。人の手で触れられることにより、手の温度や圧力を感じることで、触覚が刺激されます。この感覚に意識を集中することで、リラックス効果が得られるのです。また、眠るときのシーツや枕の肌触りも感触を楽しむことも効果的です。寝る前に、柔らかさや冷たさなど、触感に集中してみてください。
2. 嗅覚を取り入れる
嗅覚も私たちの感情や記憶に深く結びついています。お気に入りの香りを使ったアロマテラピーや、お気に入りの場所の香りを思い出すことで、心が安らぐことがあります。特に疲れた時には、リラックスできる香りを取り入れてみると良いでしょう。
3. 味覚を楽しむ
味覚は、五感の中でも特に複雑で感覚が豊かです。食事をゆっくりと楽しむことで、味覚をフルに活用することができます。食べ物の舌触りや味、香りに集中し、じっくりと味わうことで、心身共にリフレッシュできるでしょう。
五感と記憶の結びつき
五感は、私たちの記憶とも密接に関わっています。例えば、特定の匂いが昔の出来事や人物を思い出させることがあります。これは、五感が記憶と深く結びついている証拠です。五感を通じて過去の良い記憶を呼び起こすことで、現在の自分を癒すこともあるかもしれません。
五感を活用することで、日常生活の中で感じるストレスを緩和し、心地よい時間を過ごすことができます。視覚や聴覚に頼りがちな日常ですが、時には触覚、嗅覚、味覚に意識を向け、自分自身を癒す時間を大切にしてください。それが、ストレスを解消し、心身共に健やかな毎日を送るための鍵となるでしょう。
以上、五感を通じて自分を癒す方法についてお話ししました。皆さんもぜひ、日々の生活の中で五感を意識してみてください。
気持ちが伝わる唯一の方法

今日はなぜ自分の気持ちが相手に伝わらないのかというお話しです。
私たちはしばしばコミュニケーションを取り、話を聞いたり、相談に乗ったりします。その際に「こうしたほうがいい」「ああしたほうがいい」といったアドバイスをすることがありますよね。しかし、その気持ちや本意が相手にうまく伝わらないことがあります。その原因について考えてみたいと思います。
まず、私たちが他人に対して自分の気持ちを伝えようとする時、何が大事かというと「私の気持ち」が非常に重要です。多くの人が自分の感情や気持ちを誤解している場合が多いのです
。例えば、夫がうつ病を患っている場合を考えてみましょう。夫に対して「病院に行って治療を受けてほしい」と思うのは、心配しているからです。しかし、その心配の気持ちがうまく伝わらないことがあります。それはなぜか。
「どうして心配なのか」がわかっていないからです。
多くの場合、私たちは「あなたのために」と言って理屈や論理で相手を説得しようとします。しかし、人は必ずしも理屈や論理だけでは動かされません。特に、うつ病のような心の病気の場合、本人には病院に行くこと自体が大きなハードルとなることがあります。病院に行くことのコストや待ち時間、精神科に通うことへの抵抗感など、さまざまな理由があるのです。
このような場合、重要なのは相手に自分の気持ち、つまり「心配しているから」「大切に思っているから」という感情をきちんと伝えることです。「病院に行ってほしい、なぜならあなたのことが心配で大切だから」ということを伝えることで、相手もその気持ちを受け取りやすくな流のでは無いでしょうか。
感情や気持ちは振動するものです。私たちの心や感情は、素粒子のように震え、周囲に影響を与えます。この振動をしっかりと相手に伝えるためには、言葉や行動を通じて具体的に表現することが必要です。口に出して、具体的に「あなたのことが大切だから心配している」と伝えることで、相手にその震えが伝わります。
直感を信じる難しさ

こんにちは、皆さん。
今日は「直感を信じるって難しいよね」というお話をしたいと思います。
つい先日、我が家のドライヤーが壊れました。その日の夜は、髪の毛を乾かすことができず、サーキュレーターでなんとか生乾き状態にするという困った状況になりました。
実は、ドライヤーが壊れそうだな、怪しいな、と思ったのは2日前の夜だったのです。「なんだか嫌な予感」これって直感だったのかもしれません。いつもと違う音や風かなんとなく弱い感じ??その違和感から、もしかしたら壊れるかもしれないと感じました。
皆さんもこんな経験、ありませんか?「これ壊れそうだな」と思ったら本当に壊れてしまったり、なくなってしまったりすること。これは、目に見える形ではないものの、いつもと違う何かを感じ取り、それが壊れる兆しとなっていることがあるのです。私もその時、直感を信じて新しいドライヤーを用意しておけばよかったのですが、流してしまったんですよね。「まだ大丈夫だろう」と思ってしまったのです。
これは、直感を信じる難しさを表しています。感じ取った違和感を無視してしまい、結果的に困った状況になることがあります。私も過去に何度か同じような経験をしており、そのたびに「次は直感を信じよう」と思うのですが、なかなかうまくいかないものです。
直感というのは、ただのスピリチュアルなものではありません。私たちが体験し、経験したことから得られる知恵の積み重ねなのです。その直感を信じきれなかったということは、今までの経験や知恵をうまく活かせていなかったということになります。直感は、経験の高濃度から生まれるものなので、それを信じて行動することが大切なのです。
もちろん、直感を100%信じるのも危険です。勘違いすることもありますからね。そのため、直感を信じることと疑うことのバランスが重要です。しかし、直感を鍛えていくことは、考える時間を短縮し、失敗を避ける手助けになります。
皆さんもご自身の直感をどこまで信じ切れるか考えてみてください。直感を信じて動くことは難しいかもしれませんが、大切なことだと思うのです。
ところで、今日は雨が降っています。前足を持っている方は気圧の変化で辛いかもしれません。お大事にしてくださいね。お薬をしっかり飲んで、治療に努めましょう。
それでは、本日は以上です。また次回お会いしましょう。
智慧を使い倒せ!
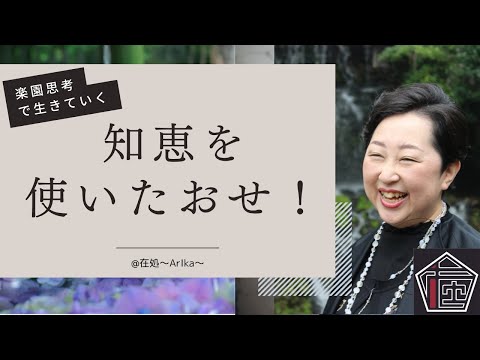
自分の特性を知り、生かすことの重要性
今日は「自分が知っていることをしっかり使いこなしていますか?」というテーマでお話しします。
私が思うに、自分を知ることが、自分自身が生きやすくなるための第一歩です。なぜなら、どんなに状況や相手が変わっても、自分の対応や行動は自分自身が決めるものだからです。選択して決める時、それらを自分らしくやれているのかどうか?それは自分がどんな人間で、何を考え何を選びやすいか。逆に言えば何を選ばないかを知っていることが必要です。
皆さん、衝動的に行動することはありませんか?突然の出来事に対して、パッと思いついたことをすぐに実行に移すことがありますよね。しかし、感情に任せた行動や過去の成功体験に頼るだけでは、今の状況に適応できないこともあります。経験を基にした行動は確かに自分自身ですが、それだけではうまくいかないこともあります。
そのため、自分の考え方や行動のパターンを知ることが重要です。自分の強みや弱み、得意なことや苦手なことを理解することで、より良い選択ができるようになります。
例えば、私は「見るのが得意な脳」(優位特性でいうと視覚タイプ)を持っています。視覚優位の私は物事を映像で記憶することが多いですし、物事の過程よりも結果を重視しがちです。また、「ウェルスダイナミクス」という診断では「トレーダー」という特性を持っています。これは、世の中の流れや傾向を見極めることが得意なタイプです。こうした特性を知っていると、自分の行動をより効果的にコントロールできます。
さらに、自分の好きなものや嫌いなものを把握することも、自分を知る一環です。私はホラー映画が好きで、人間の怖さを描いた作品に引かれます。また、情報が大好きで、星座占いや診断結果も興味深く見ています。こうした自分の好みや傾向を知ることで、自分の行動や選択がより理解しやすくなります。
しかし、多くの人はこうした診断結果を知って満足してしまい、それを活かせていないことが多いようです。それでは自己満足に過ぎません。診断結果や占いの結果を、自分の生活や仕事にどう活かすかを考え、何か揉んだ鵜が起きた時には自分で解決するのにそれらの知恵を総動員してみてはどうでしょう。
私は自分の考え方や行動のパターンを知ることで、問題が起きたときに冷静に対処できるようになりました。自分の認知の歪みや癖を理解し、相手の立場や考え方も考慮することで、より建設的な対話ができるようになります。これにより、視野が広がり、世界がより豊かに見えるようになります。
自分の持っている情報や知識を大切にするだけでなく、それを積極的に使いこなすことに意味があるのです。情報や知識は道具です。それを使わなければ意味がありません。持っているだけではなく、それを実際に使って、自分の生活や仕事に役立てましょう。
もし、自分の持っている情報をどう使うか分からない場合は、専門家に相談するのも一つの手です。私はそうしたアドバイスをするのが得意ですので、ぜひセッションに来ていただければと思います。一緒に考え、より良い方向に進むためのサポートをします。
自分の特性や情報を使いこなすことで、もっと楽しく生きられるようになります。この世界を楽園だと思うためには、自分の考え方や行動が大きな影響を与えます。自分の人生を楽しく、豊かにするために、持っている情報や知識をどんどん使いましょう。
不機嫌ハラスメントに負けるな!
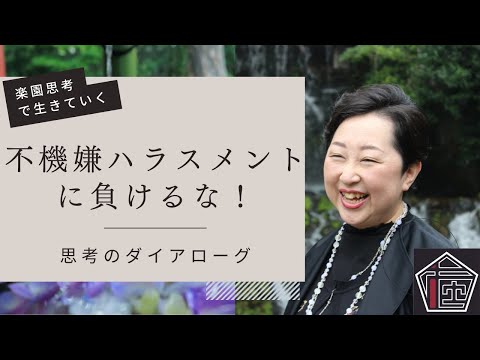
不機嫌ハラスメントとは何か?
ニュースで「不機嫌ハラスメント」について耳にしました。世の中にはさまざまなハラスメントが存在しますが、この新たなハラスメントはどのようなものなのでしょうか?
簡単に言うと、不機嫌な態度や雰囲気を周囲に撒き散らすことで、他人に気を使わせたり、行動を変えさせたりする行為を指すようです。
ニュースのコメンテーターの方がおっしゃっていたのは、会社での例を挙げると、上司や同僚が不機嫌になると、周囲の人々は「今声をかけない方が良いかもしれない」と思って報告や相談を控えてしまうことがありますよね。これが続くと、職場のコミュニケーションが悪化して、組織全体に悪影響を及ぼす可能性もあるというのです。
自分の感情をコントロールすること
私たちの日常生活の中で、不機嫌な態度を取ってしまうことは誰にでもあります。しかし、自分の感情をコントロールすることができなければなりません。「自分のご機嫌は自分で取る」という考え方を聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。それが大切なのです。不機嫌な気持ちを他人に押し付けるのではなく、自分自身で解決する努力が求められます。
また、不機嫌な気持ちを感じた時は、その感情を表に出す前に一度立ち止まって考えることが大切です。例えば、「本当に今この気持ちを表現する必要があるのか?」と自問自答することで、感情的な反応を避けることができます。それでも感情が抑えきれない場合は、相手に適切な形で伝える工夫が必要です。
健全なコミュニケーションを目指して
不機嫌ハラスメントを避けるためには、健全なコミュニケーションが不可欠です。自分の気持ちに正直であることはもちろんですが、その正直な気持ちをうまく相手に伝える方法を模索して欲しいのです。
例えば、相手が不機嫌な態度を取っている時は、「どうかしましたか?調子が悪いのですか?」と優しく問いかけることで、直接的な対立を避けながら問題の本質に近づくことができ巣かもしれません。
また、自分の感情を伝える際も、否定的な言葉を避け、相手の立場に立った表現を心がけることが重要です。例えば、「あなたの態度が不愉快です」と断定するのではなく、「最近、何か心配事があるのですか?何か手伝えることがあれば教えてください」と言うことで、対話の機会を作り出すことができます。
不機嫌ハラスメントは、日常生活の中で誰もが経験しうる問題です。しかし、自分の感情を適切にコントロールし、他人に対する配慮を持つことで、これを防ぐことができます。また、もし不機嫌な態度を取ってしまった場合は、謝罪し、その経験から学ぶことが大切です。健全なコミュニケーションを通じて、より良い人間関係を築いていきましょう。
この記事が、皆さんの振り返りや日常のコミュニケーションの改善に役立てば幸いです。それではまた次回お会いしましょう。