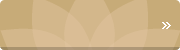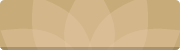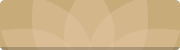理解しようとするから苦しいんだよ 〜理解ではなく「受け止める」

多様性と違いを認めること 〜理解ではなく「受け止める」ことの大切さ〜
私たちは日々、さまざまな人と関わりながら生きています。文化や価値観、人生経験が異なる人たちと接する中で、「多様性を認める」ことの重要性がよく語られます。しかし、他者の違いを本当に「理解する」ことは可能なのでしょうか? 今日は、「理解する」ことの限界と、「受け止める」ことの大切さについてお話ししたいと思います。
多様性を認めるということ
人はそれぞれ異なる環境で育ち、異なる経験をし、異なる価値観を持っています。世界を見渡せば、文化や言語、生活習慣などの違いは無限に存在します。そうした背景の違いを踏まえたとき、当然ながら「人はそれぞれ違う」ということが前提になるはずです。
この「違いを認める」という考え方は非常に重要です。自分と他者の感じ方や考え方が異なることを理解し、その違いを尊重することこそが、共存や調和の第一歩になります。
しかし、多くの人が「違いを認める」=「相手を理解すること」だと考えがちです。相手を理解しようと努力すること自体は決して悪いことではありません。むしろ自然な行動です。ただし、ここに大きな落とし穴があるのです。
理解しようとすると苦しくなる理由
私自身、「理解しようとすること」は必ずしも必要ではないと考えています。なぜなら、完全に他者を理解することはほぼ不可能だからです。
人はみな、異なる人生を歩み、異なる価値観や感じ方を持っています。それを100%理解しようとすると、「なんで理解できないんだろう」「なぜあの人はあんな行動を取るんだろう」と苦しくなってしまいます。理解できない自分を責めたり、逆に相手を責めたりすることもあるでしょう。
でも、そもそも他者を完全に理解することなどできるはずがないのです。「理解しよう」と無理に努力して苦しくなるくらいなら、「理解しなくていい」と思うことが大事です。
「理解するのは無理」と思うと冷たく聞こえるかもしれませんが、実はそうではありません。理解しなくても良いからこそ、もっと自然に相手と接することができるようになるのです。
「理解する」ではなく「受け止める」
では、理解できない他者とどうやって関係を築いていけば良いのでしょうか? その答えが「受け止める」という姿勢にあると思います。
「理解しよう」とするのではなく、「ああ、そういう考え方もあるのね」と受け止めるだけで良いのです。
- 自分とは違う考え方を知る
- 同意しなくても「そういう感じ方をする人もいる」と認める
- 「違う」という事実をそのまま受け入れる
これだけで、他者との関係がぐっと楽になります。「理解しなくていい」と思えば、無理に共感しようと頑張る必要もなく、相手に対して寛容になれるのです。
「理解する」のではなく「共感する」
ここで大切なのが、「理解」と「共感」は違うということです。
「理解」は「相手の思考や感情を自分のものとして理解しようとすること」
「共感」は「自分とは違うけれど、そう感じるのも自然だと認めること」
「わかる、わかる」と言うことは時に傲慢になりかねません。実際には自分が経験していない感覚を「わかる」と言うのは難しいからです。
でも、「ああ、そうなんだね」と受け止めることはできます。同意できなくても、「あなたはそう感じているんだね」と受け入れることはできるのです。これこそが「共感」だと思います。
「小さな袋」に分けて考える
他者の価値観や考え方をすべて自分の中に取り込む必要はありません。むしろ、個々の違いを「小さな袋」に分けて持っておけば良いのです。
- ある人はこう考える
- 別の人はこう感じる
- 自分はこう思う
これらを一つ一つ分けて、必要に応じてその袋を開いて確認すれば良いのです。無理に混ぜ合わせて「同じように理解しよう」としなくても良いのです。
「理解する」のではなく、「受け止める」。
「わかる」ではなく、「そうなのね」。
このシンプルなスタンスが、他者との関係をスムーズにし、結果的に自分自身も楽になるのではないでしょうか。
多様性を認めることは、「他者を理解する」ことではなく、「他者の違いを受け止める」ことにあると思います。理解できなくてもいい、わからなくてもいい。ただ「ああ、そうなのね」と受け止めるだけで、他者との関係は自然に良好になるでしょう。
「理解しよう」と無理に努力するのをやめ、「受け止める」姿勢を持つこと。これが、多様性を認めるための第一歩になるのではないでしょうか。
-
 嘘って良いこと?悪いこと?
4月1日です。こうして一年があっという間にすぎていくのですね。エイプリルフールは嘘をついてもいい人いうことで、
嘘って良いこと?悪いこと?
4月1日です。こうして一年があっという間にすぎていくのですね。エイプリルフールは嘘をついてもいい人いうことで、
-
 苦しいことを選べば良い事が起こるのか?
「苦しい方を選んだ方が成長するよ」とか「楽な道ばかり選んでたらダメになるよ」とか 聞いたことありませんか?基
苦しいことを選べば良い事が起こるのか?
「苦しい方を選んだ方が成長するよ」とか「楽な道ばかり選んでたらダメになるよ」とか 聞いたことありませんか?基
-
 自分らしく生きたい人が、実はハマっている落とし穴
自分らしく生きたい人が、実はハマっている落
自分らしく生きたい人が、実はハマっている落とし穴
自分らしく生きたい人が、実はハマっている落
-
 AIの“やさしさ”に酔わないで!本当の痛みと向き合う勇気
私たちのまわりには、AIを友達のように使う人がどんどん増えているように感じます。相談をすると、まるで心を読んで
AIの“やさしさ”に酔わないで!本当の痛みと向き合う勇気
私たちのまわりには、AIを友達のように使う人がどんどん増えているように感じます。相談をすると、まるで心を読んで
-
 意志力を使いこなすコツは 無理せず流れに身を任せること
本日のお話は、「意志力」というテーマでお届けします。皆さんは意志力という言葉をどんなふうに捉えていますか?意志
意志力を使いこなすコツは 無理せず流れに身を任せること
本日のお話は、「意志力」というテーマでお届けします。皆さんは意志力という言葉をどんなふうに捉えていますか?意志