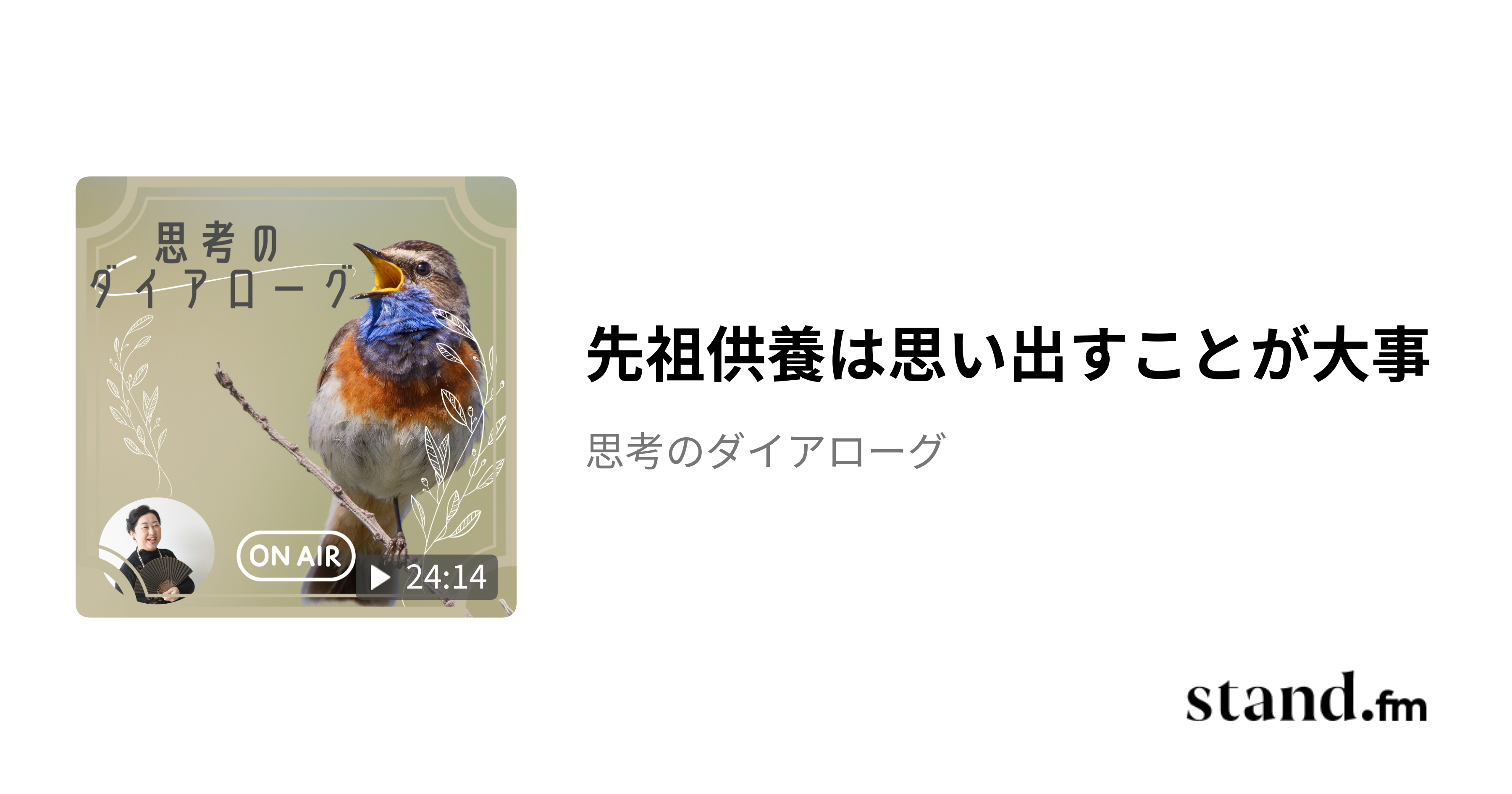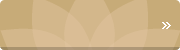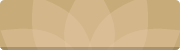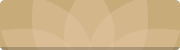お施餓鬼に参加 供養とは何か?

今日は、昨日参加してきた「お施餓鬼」の法要について、ちょっと語ってみようかなと思います。
我が家の菩提寺は八王子の山のほうにある禅宗のお寺です。毎年、7月にはお盆に「棚経(たなぎょう)」に来てくださっていたんですが、コロナ禍でそれも途絶えてしまいました。そんな中「お施餓鬼」の法要は変わらず続けてくださっていて、今年もお寺に行ってきました。
お施餓鬼ってなに?
「お施餓鬼(おせがき)」というのは、「この世のすべての餓鬼たちへの供養」です。餓鬼というのは仏教の六道のひとつで、飢えと渇きに苦しむ存在のこと。欲を満たそうとしても一瞬で消えてしまい、またすぐに飢えてしまう──そんな苦しみを抱えた存在とされます。
通常のお盆や法要は、自分の家のご先祖さまの供養ですが、お施餓鬼はもっと広く、縁もゆかりもない霊たち──苦しんでいるすべての存在への祈りなのです。
起源は、お釈迦さまの弟子「目連尊者(もくれんそんじゃ)」の伝説。母が餓鬼道に堕ちたのを見た目連さんが、お釈迦さまに相談し、「多くの僧侶に食物を施す法要を営みなさい」とのことで実際に法要を行ったところ、そのおかげで母が救われた、という話から来ています。だから、お施餓鬼は「大いなる施し」なんですね。
このお施餓鬼の行事、お寺に行くと、八王子市内の曹洞宗のいろんなお寺のお坊さんたちが集まって、十数人で一斉にお経を読んでくださるんです。
これがなかなか見応え、聞き応えがあります。ジャンジャン、ポクポクと鳴り物も響きわたって、正式な作法で丁寧にお経があげられる。
「こんなにたくさんのお坊さんが一緒に祈ってくれるなんて、すごいことだなあ」と思いながら、わたしは静かに手を合わせていました。もちろん、我が家のご先祖のための塔婆もたてましたが、それだけでなく、「今苦しんでいるかもしれない誰かのために」という祈りのかたちに、少し胸が熱くなりました。
供養とは、思い出すことなのかもしれない
わたしは供養とは、「亡くなった人を思い出すこと」なのではないかと思います。お墓参りに行ったり、お仏壇に手を合わせたりするとき、きっとみなさんも、その人のことをふと思い出すと思います。
「こんな人だったな」「あんな言葉をかけてくれたな」──そうやって、亡くなった方を思い出すことが、供養になるのではないでしょうか。
そしてその行為は、自分を大事にすることにもつながっている。
なぜならわたしたちは、無数のご先祖の命のリレーの果てに、今ここに生きているんです。自分ひとりでここに存在しているわけじゃありませんよね。
戸籍の話にも触れましたが、わたしたちは家族の、そして歴史の「末端」にいます。
ルーツを辿ると、知らなかった祖父母の人生が見えてきたりします。大家族だったり、子どもをたくさん育てたり──その積み重ねの果てに、今の自分がある。
文化や歴史というものは、簡単に絶やしてはいけないなと思います。
「今ここ」があるのは、過去があるから。私たちが今できることは、そのつながりを感じ、受け継いでいくことだと思いませんか。
お施餓鬼の法要に参加して、
「わたしにできることなんて小さいけれど、でも、手を合わせることはできる」
そういう優しさを持ち寄る場に参加できたことがありがたかったと思いました。
機会があったら、ぜひお寺の行事に足を運んでみてください。
面倒くさい、暑い、忙しい……いろんな理由はあります。でも、「そこに行くこと」でしか感じられないものも、あるはずです。
わたしたちは、つながりの中に生きている──そんなことを考えた、今年のお施餓鬼でした。
記事を読んでくださって ありがとうございます
-
 なぜ自民党に投票するのか? 〜天邪鬼な私が思うこと〜
本日のお話は「選挙」です。みなさん、参院選、行きましたか?我が家では「選挙は必ず行くもの」と決めていまして。先
なぜ自民党に投票するのか? 〜天邪鬼な私が思うこと〜
本日のお話は「選挙」です。みなさん、参院選、行きましたか?我が家では「選挙は必ず行くもの」と決めていまして。先
-
 石破総理が辞めない理由を心理的視点から考えてみた〜“言行不一致”は自己防御〜
参院選で自民・公明が過半数を割り込み、いよいよ政権への信任が揺らぎはじめているそんな中でも、石破総理は「辞任せ
石破総理が辞めない理由を心理的視点から考えてみた〜“言行不一致”は自己防御〜
参院選で自民・公明が過半数を割り込み、いよいよ政権への信任が揺らぎはじめているそんな中でも、石破総理は「辞任せ
-
 私が看護師を辞めたワケ
私が看護師を辞めたワケ - 思考のダイアロ
私が看護師を辞めたワケ
私が看護師を辞めたワケ - 思考のダイアロ
-
 ホスピタリティって何だろう?銀行窓口でカードを叩きつけられたらどうする
今日は八王子、珍しく曇り空。いやぁ、これがまた過ごしやすいのなんのって。太陽が隠れてくれているだけで、身体がふ
ホスピタリティって何だろう?銀行窓口でカードを叩きつけられたらどうする
今日は八王子、珍しく曇り空。いやぁ、これがまた過ごしやすいのなんのって。太陽が隠れてくれているだけで、身体がふ
-
 自分を変化させる勇気:ルック(見た目)は意志だ
ここ最近の私は、毎日せっせと国会中継を見ています。思想や感情は人それぞれ。しかし、丁寧に観察していると「政治
自分を変化させる勇気:ルック(見た目)は意志だ
ここ最近の私は、毎日せっせと国会中継を見ています。思想や感情は人それぞれ。しかし、丁寧に観察していると「政治