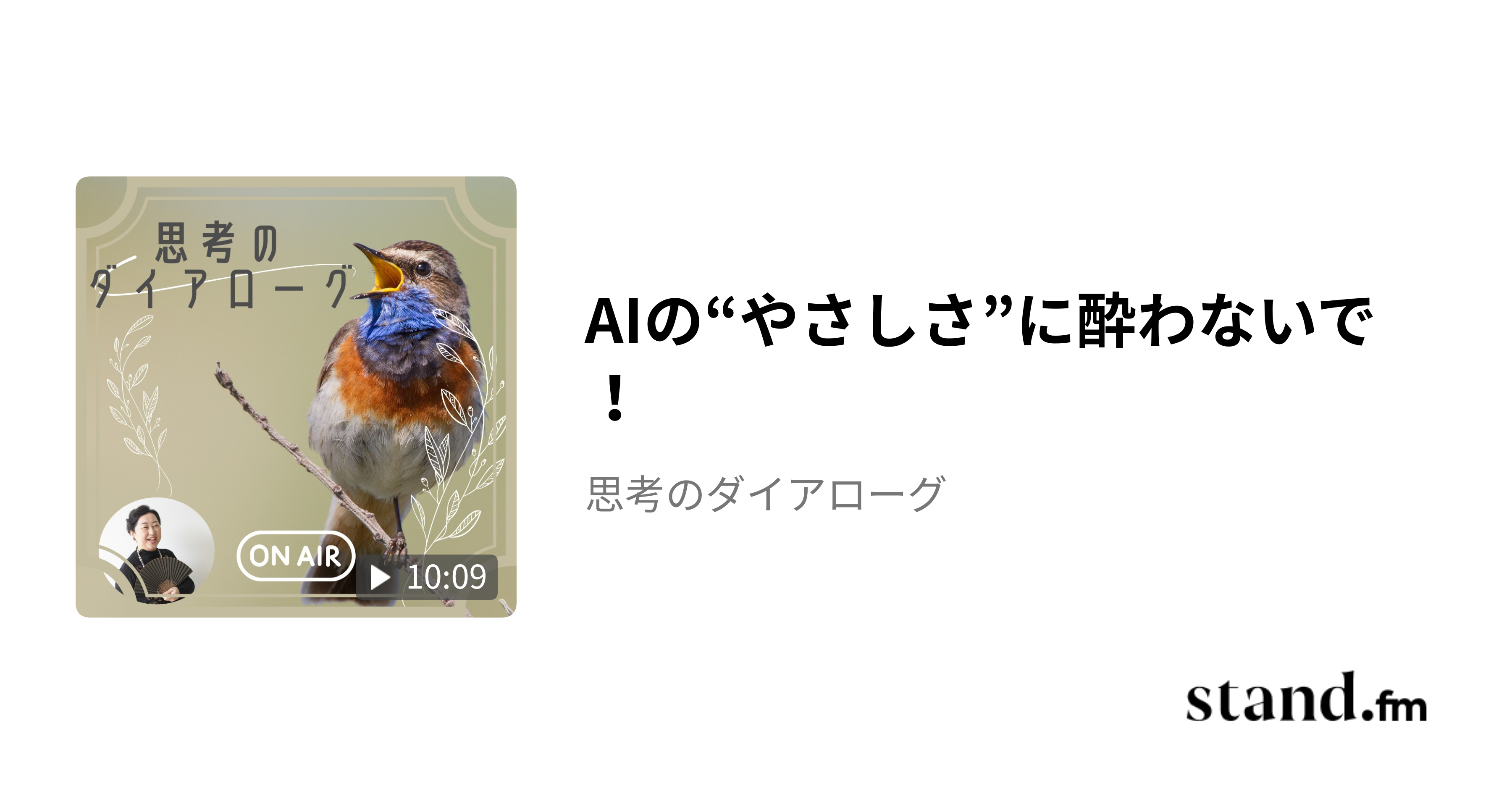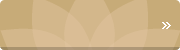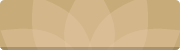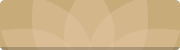AIの“やさしさ”に酔わないで!本当の痛みと向き合う勇気

私たちのまわりには、AIを友達のように使う人がどんどん増えているように感じます。
相談をすると、まるで心を読んでいるかのように共感し、励ましてくれる──
そんな“優しさ”をAIに見出している人も少なくないでしょう。
でも、そこで立ち止まって考えてみませんか?その「心」は、本当に存在するものなのでしょうか。
AIに心はない。
これは誰もが知っている事実です
。AIが発する共感や励ましの言葉は、膨大なデータの集積から導かれた「表現のひとつ」にすぎません。にもかかわらず、私たちはその言葉を目にした瞬間、「ああ、わかってくれている」と感じ、「元気づけられた」と思ってしまう。人形や車、ぬいぐるみに名前をつけて話しかけるのと同じように、AIという「無機物」に魂があるかのように扱ってしまうのは、人間の想像力が「ないもの」を勝手に補完しようとするからではないでしょうか。
しかし、この想像力こそが、私たちの人間関係においてもっとも大切な「思いやり」の源なのだと思います。
相手の気持ちを想像し、配慮を生み出す能力は、まさに想像力なしには成り立ちません。
だからこそ、AIが放つ「やさしい言葉」に触れてホッとする瞬間もあるけれど、それはあくまで“対症療法”であって、心の奥底にある問題を解決するものではないのです。
私が思うに、「心がある」とは、身体を持ち、そのフィジカルを通して体験や経験を重ねること。痛みを知り、笑い、迷い、立ち上がる──そうした積み重ねが、いわゆる“魂”を育むのではないでしょうか。私たちはまさに身体と魂のハイブリッドであり、その実感こそが「生きている実感」につながります。けれど、AIに励まされ、わずかな安心を手に入れたとしても、自分自身の深い感情や無意識のクセを変えるには至りません。
では、AIとはどう付き合えばいいのか?
私たちには、AIをツールとして賢く使いながら、同時に一定の距離感と客観的な視点を保つ必要があります。
- AIの言葉に救われる自分を否定せず、あぁそうかと受け止める
- それが「情報の表現」であることを忘れず、依存しすぎない
- 本当に向き合うべきは、自分自身の身体感覚や体験から湧き上がる声であることを意識する
AIに慰められてホッとしたその後、
「これで私は本当に癒やされているのか?」
「心の芯(真)の部分に、ちゃんと届いているのだろうか?」
と自問してみてください。
AIのやさしさを享受しつつ、私たちが本当に大切にすべきは、自分の身体を通して感じる「痛み」や「喜び」という、ほかでもない自分自身の声です。AIと適度な距離を取りながら、自分の心に耳を澄ませる習慣こそが、真の変化を生み出す第一歩になるでしょう。
-
 人の不幸に便乗することでいい人自慢したいのが本音なんでしょう?
ドライブ中にラジオから聞こえてきたのが、救急車を設計してる?つくっているという人の話で、「以前救急車を作る仕事
人の不幸に便乗することでいい人自慢したいのが本音なんでしょう?
ドライブ中にラジオから聞こえてきたのが、救急車を設計してる?つくっているという人の話で、「以前救急車を作る仕事
-
 アンチコメントにどう対処する?
最近の配信は音声とブログを主に発信しています。気軽に、ストレスなく発信できるのは今は音声配信が一番しっくりきて
アンチコメントにどう対処する?
最近の配信は音声とブログを主に発信しています。気軽に、ストレスなく発信できるのは今は音声配信が一番しっくりきて
-
 嘘って良いこと?悪いこと?
4月1日です。こうして一年があっという間にすぎていくのですね。エイプリルフールは嘘をついてもいい人いうことで、
嘘って良いこと?悪いこと?
4月1日です。こうして一年があっという間にすぎていくのですね。エイプリルフールは嘘をついてもいい人いうことで、
-
 苦しいことを選べば良い事が起こるのか?
「苦しい方を選んだ方が成長するよ」とか「楽な道ばかり選んでたらダメになるよ」とか 聞いたことありませんか?基
苦しいことを選べば良い事が起こるのか?
「苦しい方を選んだ方が成長するよ」とか「楽な道ばかり選んでたらダメになるよ」とか 聞いたことありませんか?基
-
 自分らしく生きたい人が、実はハマっている落とし穴
自分らしく生きたい人が、実はハマっている落
自分らしく生きたい人が、実はハマっている落とし穴
自分らしく生きたい人が、実はハマっている落