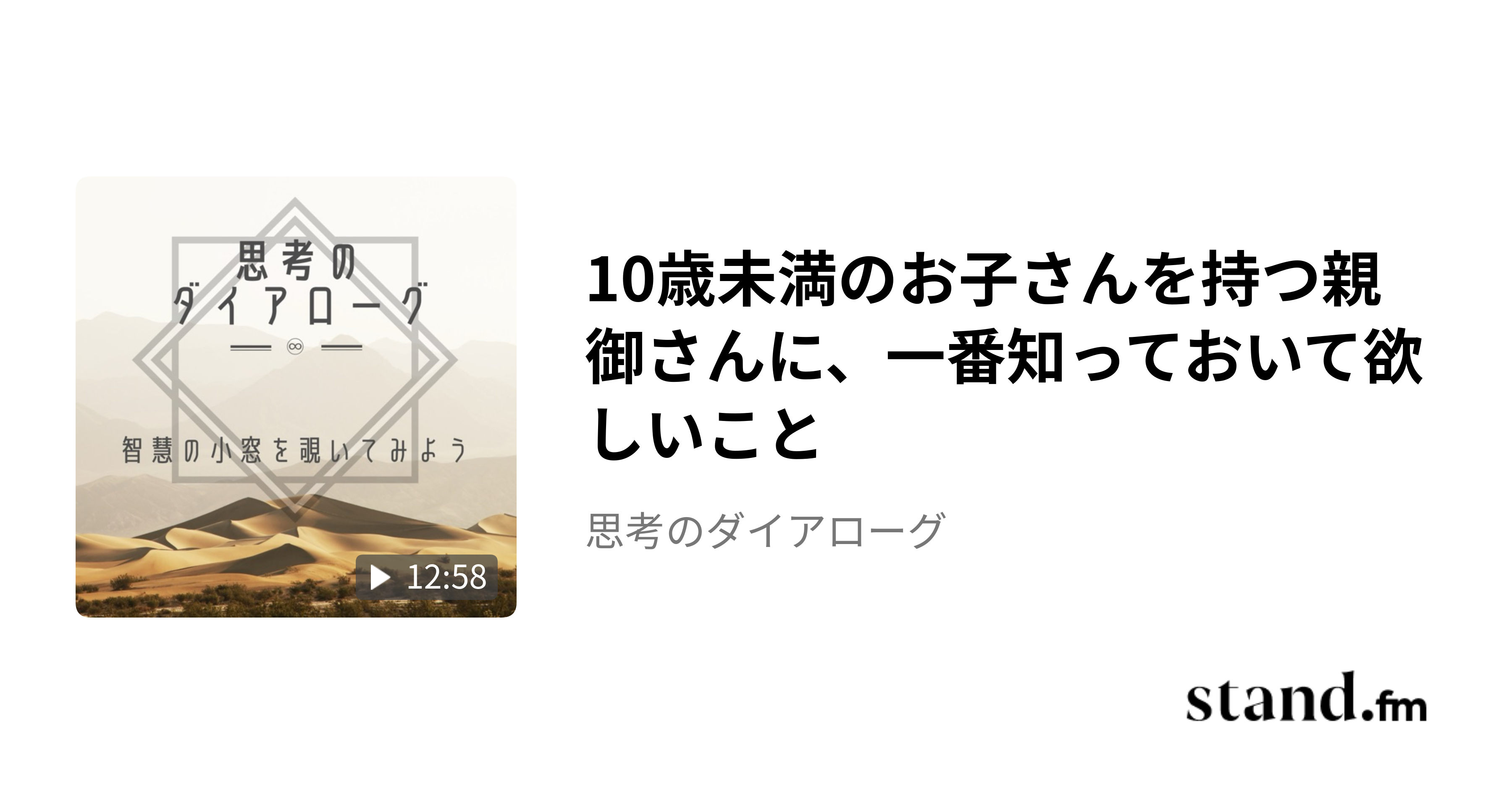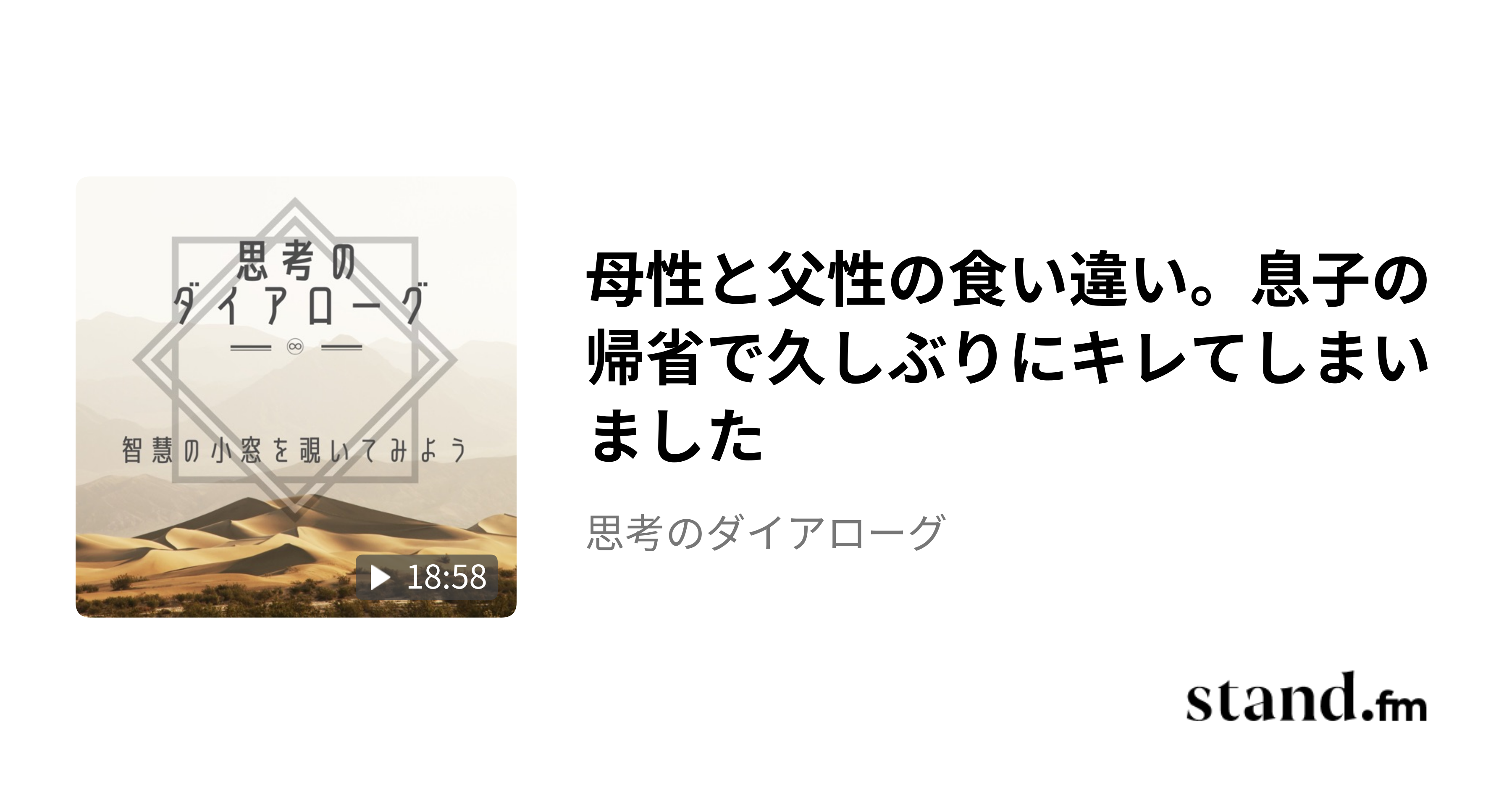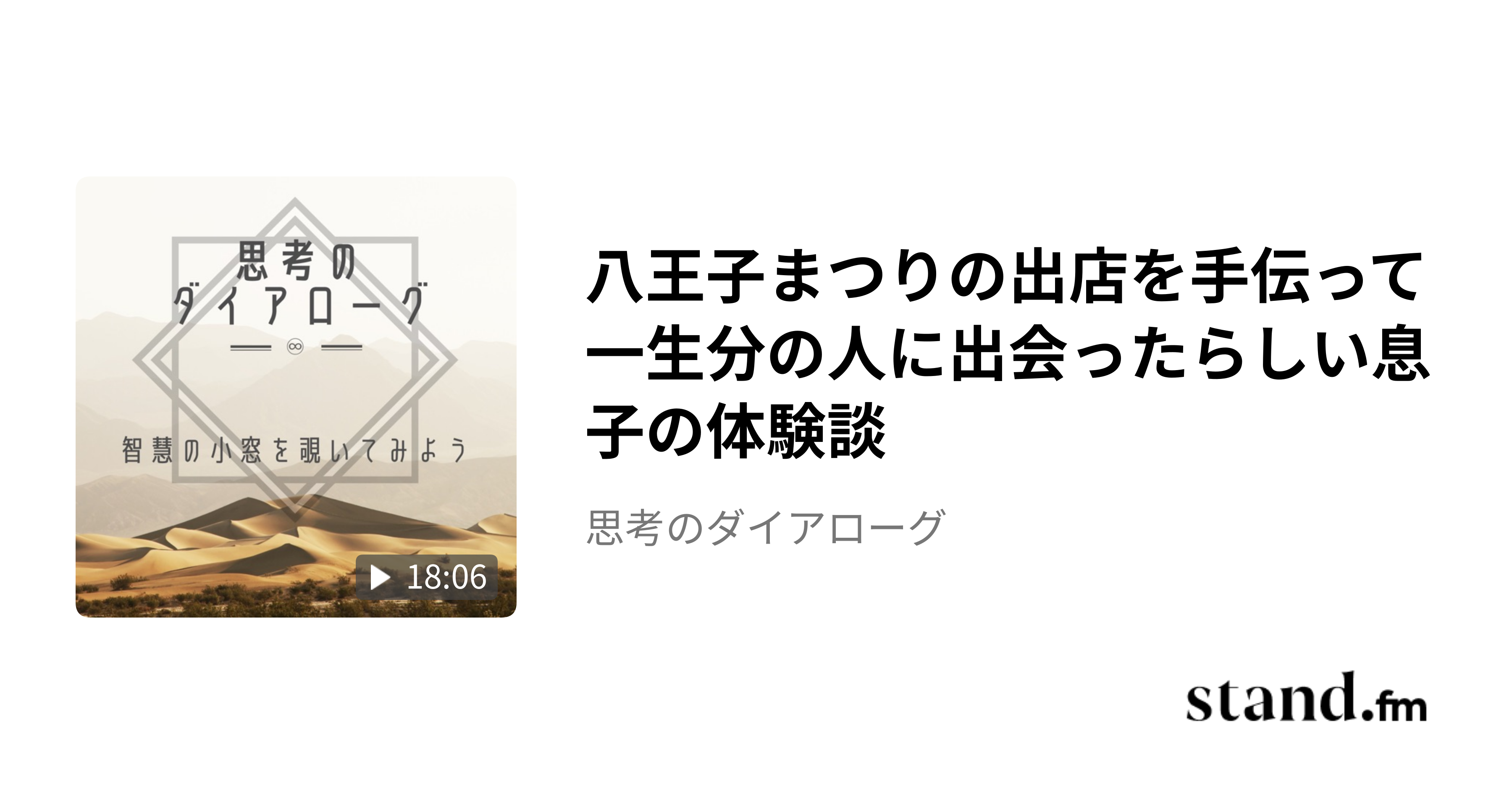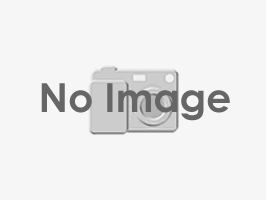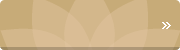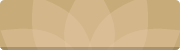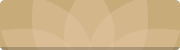家族・子育ての智慧
- 反抗期の男子はなぜあんなに攻撃力が高いのか
- 10歳未満のお子さんを持つ親御さんに、一番知っておいて欲しいこと
- 離婚でためされる 断捨離マインド
- 【ふたりの息子・子育て物語】 自己肯定感は褒めることだけではつくれない
- 「長生きしてね」にモヤッとしてしまうのはなぜか
- 待合室のテレビを消したママは自分勝手?自分軸?(自分軸をどう見極めるか)
- 勉強に必要なこと。まずは質より量。
- 母性と父性の食い違い。息子の帰省で久しぶりにキレてしまいました
- 八王子まつりの出店を手伝って一生分の人に出会ったらしい息子の体験談
- 母が特養に入所できてホッとしたお話
反抗期の男子はなぜあんなに攻撃力が高いのか

今日は思春期の男の子の子育てのお話をいたしましょう。
10歳をすぎると、男の子も第二次成長期を迎えます。この時彼らの身体はテストステロンが大量に出始めて、体を大人の男性らしいものに変えていきます。それと同時に体は大人じみてきますが、心の成長はというと男の子は女の子に比べてゆっくりなようで、まだまだ親に甘えたい、守ってもらいたいという思いがある一方で、もう大人なんだ、自分で決めてやってみたい、という自立心も芽生え始めます。
この大人のカラダと子どもの心のバランスがうまく取れないことの苛立ちが、彼らの攻撃的な言動に繋がっているように思えます。
それぞれの個性もあるかとは思いますが、思春期の反抗的な言動はホルモンのバランスがまだ取れていない事で起きているのかもしれないと思う事も、一つ大事なことかもしれません。
見た目は大人のように見えるでしょうが、心はまだまだ幼く、経験や体験もまだまだです。親はどうしても彼らに大人のような考えや行動を期待してしまいますが、それは重荷なのかもしれません。男の子の脳(心)はゆっくり成長していきます。そこで気にかけるべきは、彼らとの距離感です。子供扱いして、なんでも手助けするのではなく、少しずつ彼ら自身の任せていって、親は「どんな手伝いをしてほしいか言ってくれるかな?」と手を離していくことをしてみてください。
彼らの不安には信頼と愛でバックアップして、もし間違ったり失敗しても責め立てることよりも、そこから立ち上がって何が学べたかを伝えて、失敗を成長の糧にできるように手伝ってあげてください。
反抗はあくまでも両親は自分を愛していて、けっして裏切らないし自分を嫌いになんてならないという確信があるから起こることです。要は甘えているのかもしれませんね。そこを分かった上で、成長に必要な反抗期を乗り越えていきましょう。
10歳未満のお子さんを持つ親御さんに、一番知っておいて欲しいこと

今日のお話は子育てについて。
私も二人の息子を育てている時に、このことを知っていたら子供と関わるときにラクだったかもしれないなと感じていることです。
まず一つには子どもも生まれてきてから初めての体験ばかりなのと同じように、私たち親もお父さんお母さん一年生だということです。子供が生まれてから、もしくは妊娠してから始めて親になって、子どもと一緒に親子として成長していくのだということ。子どもも親である私たちもお互いに初めてのことばかりだけれど、がんばっていこうねという思いでいることもありかと思います。
もう一つには、特に10歳未満の子どもは「こども」という生き物だと思うこと。
人の子として生まれるわけですから、つい理屈で話をしてしまいがちですし、それでわからないとイライラしたりしてしまうこともあるでしょう。しかし、子どもは生まれてから少しずつ成長していくもので、まだまだ未熟なのです。人としての経験も知識もないのですから、一つ一つ教えていかなければなりません。成長しきった人のミニチュア版ではないのです。話してわかる事は少なく、理解できないのも当然です。そうであれば親が一緒にさまざまなことを体験していくことで、多くを得ていくのではないでしょうか。まだまだ未熟な「こども」という生き物なんだと思うことで、期待を寄せすぎることなく彼らを助けるためのさまざまなことができるのではないかと思うのです。
今そこにある子どもの姿をちゃんと見極めること。親はそこでどんな手助けやサポートができるのか、考えながら子育てはやっていくものなのかもしれません。
離婚でためされる 断捨離マインド

今日は「手放すこと」についてお話ししたいと思います。
物を手放すことと心の整理
数年前、断捨離が流行しましたね。これは物を手放すことを通じて心の整理をするという考え方の一例です。物には思いがあり、それを購入したり大切にしたりする背景には自分の価値観や生き方が反映されています。その物を捨てることで、自分の考え方や価値観、そして生き方まで整理できるというものです。
人間関係の整理と執着
例えば、親離れや子離れ、離婚、転職など、人と離れることや関係を整理することはしばしば必要になります。手放せないことが苦しみの原因となることが多いですが、その背景には強い執着があるのではないでしょうか。特に人との関係においては、相手に対する依存や執着が大きな要素となり、とても厄介です。
離婚の場合、金銭的な欲求も関わってきます。物質的なものの分配やお金に対する執着があると、離れることが難しくなることが多いのです。まずは、自分が何を優先すべきかを明確にし、それに基づいて手放すべきものを決めることが重要です。
私たちが生きていくためには金銭が必要です。離婚においては、慰謝料や養育費など、金銭的な問題が必ず出てきます。これらの問題は適切に解決する必要がありますが、相手に対する執着が強すぎると、これがなかなか進展しないことがあります。
大切なのは、まず自分の中で何が一番重要かを見極めることです。例えば、精神的な安定を最優先にするのであれば、金銭的な問題で揉めることなく、できるだけ早く離れることを優先すべきです。
心が傷つけば相手に謝ってもらいたいのは当然のことです。しかし現実の世界では謝罪をお金で解決せざるを得ない場合がほとんどです。仕方がありませんね。気持ちや心は目に見えるものではありませんから。
離婚における優先順位
離婚を考える方にとって一番大切なのは、自分にとって何が一番重要かを理解することです。精神的に一緒にいるのが辛いのであれば、離れることを最優先に考え、それを実現するために手放すことや物があるならそれを実行することをオススメします。
物事を手放して新しいものをつかむ
私たちの人生には限りがあります。何かを手に入れるためには、何かを手放さなければなりません。これは物理的な意味でも、精神的な意味でも同じです。握りしめているものを手放すことで、新しいものをつかむことができるのです。
手放すことは決して悪いことではありません。この世界のすべてのものは借りものと言われます。今あなたにとって本当に必要なものは何か?それを得るために何を手放すべきかを考えてみてください。執着を手放し、新しい幸せを見つけるための第一歩を踏み出しましょう。
【ふたりの息子・子育て物語】 自己肯定感は褒めることだけではつくれない

「ほめる子育て」っていいよね、と信じて
子どもに「えらいね!すごいね!」を連呼してはいませんか?
これとても危険です。
なぜなら ほめる時に、何かや誰かと比べてあなたは優秀だと言ってしまうと、子ども自身が様々なことを比べることで「良い」「悪い」という評価をしてしまうようになるからです。
私たちは毎日の出来事を脳の中で比較しながら、その時の状況に合わせて選択することで行動しています。
朝食を食べようか食べないか。
食べるならパンか、ご飯か。
コーヒーか紅茶か・・・などなど。
ありとあらゆるものを比較してはいるものの、物事には比較することのできないものがあることも事実です。そしてこの比較できないものが、人間らしさであったりします。
ですから、子育てをする時はとくにこの人間らしさを大切にして欲しいのです。
誰かと比べていいとか悪いとか、そんな価値観で物事を捉えていくと、子どもたちは何でも相対的な価値観を重要視していくようになります。誰かと比べてどうとかこうとかという価値観は、対象物が必要になりますから、何の根拠もなく「それでいいんだ」という自己肯定感を持つことがとても難しくなるのです。
現代を生きる人たち、とくに日本人は自己承認欲求が低く、自己肯定感を持つことができない人が多くいます。これは、魚座時代の競争して勝つことが重要視された価値観に毒されたからとも言えます。負ければ不幸で、それまでの努力などないのも同然。勝ち残らなければ人間じゃない!くらいの勢いです。
しかしこれからは水瓶座時代です。多様性を、それぞれの個性を認め合い、お互いの得意なところで補完し合う社会に変容していきます。その中で必要なのは「競争」ではなく「共創」です。
そこにはほめてほめられ、比べてどちらが優位でどちらが劣勢だなどという上下の関係を持つこと自体が、古い価値観となります。
そもそもほめることは、自分がちょっと上から目線でする行為ではないでしょうか。
私たちはこの世に生まれた時点で、性別も年齢も国籍も何もかも関係なく、一律この世で魂を磨く修行をする凡夫です。それこそ魂は平等なのです。
それなら、ほめること自体が相手を馬鹿にする行為であり、してはならないことではないでしょうか。
子どもにはほめるのではなく、お父さんお母さんの感情を伝えてあげて欲しいと思います。表面的な良い点数が取れたとか、何かで優勝したことを喜んで褒めそやすのではなく、もっと本質的なことを伝えてあげて欲しいのです。
良い成績を取ったなら
「勉強することに一生懸命努力した、あなたの力が素晴らしい。努力した姿を見られてお母さんは嬉しいわ」
マラソン大会で優勝したなら
「最初にゴールして気持ちがよかったかな?最後まで走り切れたことがあなたの自信になるといいな。」
心を、気持ちを伝えてください。
もっともっと深い本質を考えて感じて、言葉を紡いでください。
子どもの自己肯定感を育てるのは、安易な褒め言葉ではなく本質をついた愛情のこもった言葉です。
「長生きしてね」にモヤッとしてしまうのはなぜか

そろそろ敬老の日がやってきますね。歳をとった方を敬おうという祝日です。
よくおじいちゃんおばあちゃんに「長生きしてね」というと思うんですが、私これを聞くとなんだかモヤっとしてしまうんです。
別に長生きを望むということは、その人との関係がとても良くて少しでも長く一緒にいたいということなんでしょうけれど、それって若い人の言い分ですよね。
人にはそれぞれ寿命があって、人生があって、歳を重ねた人はそれなりになんやかんやと頑張ってきてここまできたんだと思います。歳をとると色々やれないことも多くなってきて、若い頃とは生き続けることが大変で苦しかったりもすると思うんです。
これって私が病気で、毎日が辛いって思うことが多いからだとは思うんですが、「長生きしてね」っていうのは、もしかしたら苦しみがもっと続くことを意味しているのかもしれないし、そういうことも想像できない人が普通はこういうこと言うんでしょ、みたいにしてかける言葉なきがしてしまいます。これがもやっとする原因かもしれません。
そんな人ばかりじゃないこともわかってはいるんですが、歳をとると長く生きると言うことは、私たちみたいに日々を過ごすこととはありようが違っていることもあると思うんです。苦しくて辛いかもしれない。ならなんて声をかけよう。
私なら未来じゃなくて、今の気持ちを伝えます。
「会えて嬉しいよ」ってね。音声配信ブログ 毎日更新しています
※こちらではフルバージョンのブログを聞くことができます
待合室のテレビを消したママは自分勝手?自分軸?(自分軸をどう見極めるか)

あるブログで拝見したママさんの行動。
ちょっと気になったので分析してみました。
病院の診察を待つお子さんたちが、待合室のテレビで流れるアニメを見ていたところ、後からやってきたあるお母さんがさも当たり前のようにテレビのリモコンをつかんでテレビを消してしまいます。急に画面が消えて「なんで消えちゃったの?」戸惑う子どもとお母さんたち。
受付の人がテレビをつけようとすると、先ほどのお母さんが「ウチでは子どもにアニメを見せないようにしているので、消したままにしてください」と。その言い方や物腰がとても上品で有無を言わせない雰囲気があって、そのままテレビは消したままになったとか。
このブログを書いたお母さんは、お子さんが普段はあまり見ないアニメを楽しみに病院に行っていたので見れないことを残念だと思ったそうですが、お話をしたり手遊びをしたりして時間を過ごしたそうです。
ここで私が気になったのは、テレビを消した上品なお母さんのこと。
このお母さんの行動は自分軸、自分勝手、他人軸のどれだと思いますか?
人に言われてテレビを消したわけではないので、他人軸ではありませんね。
ちゃんと子育ての方針があり、それを曲げずに行動してテレビを消しています。そこだけ見ると自分軸のように思えますね。
自分軸か自分勝手か見極めるにはまず「言動の一致」があるかないかを見る必要があります。
・言っていること(子どもにアニメを見せない子育てをしている)
・やっていること(テレビを消す)
・思っていること(アニメを見せない子育てをしているからここでも見せたくない)
一致してますね。
では自分軸かというと、もう一つ確認することがあります。
「思いやりがあるかどうか?」
待合室ではすでにアニメを見ている子どもたちがいて、アニメを見せることでおとなしく待つことができていたかもしれません。お母様たちも助かっていたかもしれませんね。しかしその人たちのことは考えずに、「自分(我が家)のルール」を押し付ける形で、テレビを消した。これは思いやりのない行動といえます。
「言動の一致」はあっても「思いやり」に欠けているので、このお母さんは自分勝手だといえます。
もう一つ私が気になったのは、この「自分(我が家)のルール」を押し付けたことです。
成長し社会に出れば、自分の思う通りにならないことはたくさんあります。だからこそ子どものうちは親が思う通りにしたいと思っていらっしゃるのかもしれませんが、そんな言動を見て子供は育ちます。周りに合わせすぎれば苦しいかもしれませんが、自分の思う通りにならないこともあるということは知っておく必要がありますし、そこでうまく合わせることができるような柔軟性を学ぶのも大切なことだと思うのです。いかがでしょうか。
音声配信ブログ 更新しています
※こちらではフルバージョンのブログを聞くことができます
勉強に必要なこと。まずは質より量。

夏休みも終わってお子さんたちも二学期が始まっていることと思います。
夏休みの宿題が終わったか?なんて、ヤキモキした親御さんたちもいたのではないでしょうか。
小学生のお子さんをお持ちのお母様方は毎日の宿題の丸つけや、音読に付き合ったり、九九の暗記を手伝ったり、結構大変なことと思います。
私が絶賛子育て真っ最中の頃は、宿題の丸つけなどまだ先生が見てくださっていたこともあって、親である私はフォローするくらいでしたから、今のお母さん方に比べたらまだ楽だったかもしれません。
さて親としては宿題や課題はちゃんとやってほしいでしょうし、やっていなければヤキモキして怒ったりなだめたり、もので釣ったりと色々した経験もあるでしょう。
しかし宿題や課題をやるのは誰でしょう?そしてやらないで困るのは誰ですか?
ここ大事なところです。
困るのは子ども自身であって、困ったり、恥をかいたりする経験も込みで彼らに味わってもらうことも大切かもしれません。課題の分離ですね。
親は子供の大事な経験を奪ってはなりません。
それでも気にしないお子さんもいるかもしれません。そうなるとかなり困りますね。
「なぜ勉強しなければならないのか」
この答えを親は持っていなければならないと思います。
親は子どもより長く生きていますから人生の先輩です。彼らのやっていることをすでに経験していることも多くあるでしょう。だからこそ「勉強しなさい」と言ってしまうのでしょうが、問題は「どうして」の部分です。頭ごなしにこうしろああしろと言われて、やれるものでしょうか。
子どもだって納得できなければそう言われても、聞くことはできないでしょう。
私は息子たちに勉強しろと言ったことがありません。
ただいまは無意味に思える計算や暗記は、大人になっていくときに自分のやりたいことが見つかるきっかけになるかもしれないし、生きていく楽しみにつながるんだよ、と話してきました。
勉強して色々覚えると、この世界のことがよくわかってくる。知るということはとても面白いし楽しいことだと、息子が興味を示すものがあればそれを使ってどんな面白さがあるか教えてきました。すると彼らは徐々に勝手に面白いことを発見して深掘りして、楽しむようになっていきました。
それと勉強とは綺麗事では済まされない部分もあります。
よく質の良い学びをしましょうという方もいらっしゃいますが、私はとにかく最初は「質より量」だと思います。
翔というのは勉強する時間を絶対的に取ることです。子どもの集中力は年齢プラス5分と言われています。10歳なら15分が限界ということ。ではその15分を休みを入れながら何度か繰り返せばいいわけです。
それと学校に行くことはただ椅子に座っているだけだったとしても、先生の話を聞きかいてあるものを読むことで無意識に知識に触れます。積極的に覚えようとしてくれれば一番良いのですが、そうでなくても知識に触れていることは重要です。ですから不登校の子はどうしても勉強の絶対量が減っている状態ですので、そういうお子さんには家庭やフリースクールでその時間を補う必要があるでしょう。
質の良い勉強は、土台である暗記などで覚えた知識がなければ叶いません。
どんなに素晴らしい設計図があったとしても、材料がないのに、いい家が立たないことと同じです。
まずは材料になる知識を覚えることが質の良い学びにつながります。
音声配信ブログ 更新しています
※こちらではフルバージョンのブログを聞くことができます
母性と父性の食い違い。息子の帰省で久しぶりにキレてしまいました

長男のユウさんがお盆に帰省してきた時のこと、私は彼とおしゃべりするのをとても楽しみにしているのですが、それに合わせて何かお腹いっぱいになるように食事を作ろうと考えていたわけです。
とりあえず私も母なので、何か私の味を食べさせていと思っていたのですが、主人にお買い物に行ってもらったところお惣菜をたくさん買ってきてくれたのです。
いつもはお惣菜を買ってきてもらうのは、おかずを作らなくて済むので大変助かることなのです。しかし今回は私の中でユウさんにご飯を作ってあげたいという気持ちがつよくあったので、主人は私への優しさで買ってきてくれたことは重々わかっているのですが、なんだかモヤモヤしてしまいました。
主人は父親としての父性があるのですが、私には母親としての母性があって、そこのところやっぱり違いがあるものです。
久しぶりに買ってきた息子に晴れの食事をさせたい主人の父性と、母の味を食べさせていと思ってしまった私の母性が食い違ってしまったのですよね。
お互いのコミュニケーション不足が招いたことなのですが、次回は「息子に私の味を食べさせたい」と夫にちゃんとはなあしてみようと思います。
そうすれば今回のようなモヤモヤは起きないかもしれません。
音声配信ブログ 更新しています
※こちらではフルバージョンのブログを聞くことができます
八王子まつりの出店を手伝って一生分の人に出会ったらしい息子の体験談

8月最初の週末、地元八王子では4年ぶりの八王子まつりが開かれました。
今までは60万人ほどの人出だったそうですが、今年はコロナ明けも手伝ってか90万人以上のひとがおいでになったそうです。
私は家でYouTubeで見ていましたが、いやぁすごい人でした。そしてマスクしている人もだいぶ少なくなっていましたね。
そんなお祭りに息子がお友達のおじいさんの出店のお手伝いで参戦してきたようです。
お祭り2日目、」昼の10時から22時までぶっ通しで焼きそばを売りまくったそうで、昼間は40度近い気温の中、帰ってきた時には全身焼きそばの匂いに包まれながら日焼けしてヘロヘロでした。
次の日昼まで休んで、全身筋肉痛だと言いながら
「ずっと接客していたけれど、いろんな人がいるよね。文句ばっかで自分勝手な人もいれば、気をつかって話しかけてくれたり労ってくれる人もいて、昨日一日で一生分の人に出会った感じ」
と話してくれました。
彼の仕事はデジタルのデザイン関係なので、普段はデスクワーク。人と関わるといっても、特定の人としか関わりません。彼の性質上、それはあってい流ということなのでなんの問題もないのですが、ここで接客という触れたことのない仕事をすることで、新しい発見や考えたこともあるようです。
気持ちよく仕事をするには、お互いの思いやりが必要なのではないか。お客とお店は対等であってお金払ったんだから気持ちの良いサービスをしてもらうのは当たり前なのではなく、そこには礼儀もある。僕はあいさつとか感謝とか、思いやりのある関わり方をされると嬉しかったから、自分もそうすると。
生きていれば生活していく中で誰もが多くの体験をするわけですが、その「体験」を「経験」とするには体験からの気づきから、そこで何を学び取ろうかという探究心と向上心が必要です。
ただ体験しただけに止めるのか、それともそれを経験にして知恵を得るのか。
ここは大きな境目と言えるでしょう。
体験から学ぶことは多いものです。
この夏新しい智慧はどれほどのものでしょうか。楽しみです。
音声配信ブログ 毎日更新しています
※こちらではフルバージョンのブログを聞くことができます
母が特養に入所できてホッとしたお話

今年の1月に有料老人ホームに入所した認知症の母ですが、今月ついに特養(特別養護老人ホーム)に転所できることになりました。
特別養護老人ホームとは
介護が必要な方に、介護サービスと生活の場を提供する公的な介護保険施設です。入居には条件があります。
メリット
- 費用が安い
- 24時間介護が受けられる 原則として終身にわたり入所できる
デメリット
- 民間企業に比べて倒産リスクが少ない
- 入居できるのが原則要介護3以上
- 入居できるまで時間がかかる
- 医療体制に限界がある
費用の面でも今までよりは助かるので安心しました
今までの施設では、具体的にいいますと
費用は大体1ヶ月15万から18万程度。
施設使用料と食費、診察費、車椅子レンタル代などです。
他にもオムツやパッド、ティッシュなど消耗品は持ち込みです。ここにも購入代がかかります。
私たちは3人兄弟ですから、三分割して毎月5、6万の出費でした。
これが特養になるとどうなるか。
今より費用がかからないようになると助かります。
それと基本的には終身にわたって入所できるということ。
母にしても生活環境がコロコロ変わるのは不安でしょうし、安全や安心面でもありがたいのです。
お引越しは弟と妹が特養の職員さんと一緒に車でパパッと済ませてくれました。
母はわかっているのかいないのか、それでも穏やかだったようです。
妹曰く、施設に行ったら職員に皆さんがにこやかに挨拶をしてくださったようです。今までの施設では、面会していても目があっても挨拶はなかったのだとか。。
マジか。。と思いましたが事実だったようで、
「こっちの施設の人が普通に挨拶してくれて、今までなにか足りない気がしていたんだけどあいさつだったんだね。」
なんて言っていました。
音声配信ブログ 更新しています
※こちらではフルバージョンのブログを聞くことができます