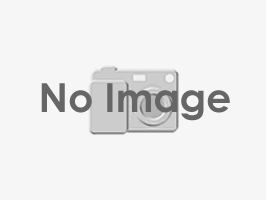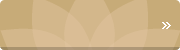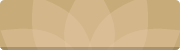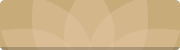思考の智慧
不機嫌ハラスメントに負けるな!
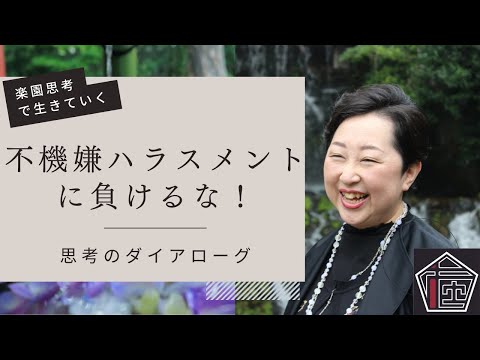
不機嫌ハラスメントとは何か?
ニュースで「不機嫌ハラスメント」について耳にしました。世の中にはさまざまなハラスメントが存在しますが、この新たなハラスメントはどのようなものなのでしょうか?
簡単に言うと、不機嫌な態度や雰囲気を周囲に撒き散らすことで、他人に気を使わせたり、行動を変えさせたりする行為を指すようです。
ニュースのコメンテーターの方がおっしゃっていたのは、会社での例を挙げると、上司や同僚が不機嫌になると、周囲の人々は「今声をかけない方が良いかもしれない」と思って報告や相談を控えてしまうことがありますよね。これが続くと、職場のコミュニケーションが悪化して、組織全体に悪影響を及ぼす可能性もあるというのです。
自分の感情をコントロールすること
私たちの日常生活の中で、不機嫌な態度を取ってしまうことは誰にでもあります。しかし、自分の感情をコントロールすることができなければなりません。「自分のご機嫌は自分で取る」という考え方を聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。それが大切なのです。不機嫌な気持ちを他人に押し付けるのではなく、自分自身で解決する努力が求められます。
また、不機嫌な気持ちを感じた時は、その感情を表に出す前に一度立ち止まって考えることが大切です。例えば、「本当に今この気持ちを表現する必要があるのか?」と自問自答することで、感情的な反応を避けることができます。それでも感情が抑えきれない場合は、相手に適切な形で伝える工夫が必要です。
健全なコミュニケーションを目指して
不機嫌ハラスメントを避けるためには、健全なコミュニケーションが不可欠です。自分の気持ちに正直であることはもちろんですが、その正直な気持ちをうまく相手に伝える方法を模索して欲しいのです。
例えば、相手が不機嫌な態度を取っている時は、「どうかしましたか?調子が悪いのですか?」と優しく問いかけることで、直接的な対立を避けながら問題の本質に近づくことができ巣かもしれません。
また、自分の感情を伝える際も、否定的な言葉を避け、相手の立場に立った表現を心がけることが重要です。例えば、「あなたの態度が不愉快です」と断定するのではなく、「最近、何か心配事があるのですか?何か手伝えることがあれば教えてください」と言うことで、対話の機会を作り出すことができます。
不機嫌ハラスメントは、日常生活の中で誰もが経験しうる問題です。しかし、自分の感情を適切にコントロールし、他人に対する配慮を持つことで、これを防ぐことができます。また、もし不機嫌な態度を取ってしまった場合は、謝罪し、その経験から学ぶことが大切です。健全なコミュニケーションを通じて、より良い人間関係を築いていきましょう。
この記事が、皆さんの振り返りや日常のコミュニケーションの改善に役立てば幸いです。それではまた次回お会いしましょう。
ドラマ「アンチヒーロー」に見る善悪と納得解

ドラマ「アンチヒーロー」最終回を観て考えたこと
TBSのドラマ「アンチヒーロー」が最終回を迎えました。私は主婦なので、リアルタイムで観ることは難しく、いつも翌日に動画配信サイトで楽しんでいます。今回も先ほど最終回を観終わり、ちょっと感想などを。
ドラマの最後の裁判シーンでは、主人公が朗々と語る場面がありました。検察側が証拠を隠蔽する中で、彼は過去の罪を背負いながらも真実を暴こうとします。その中で
「人は正義感でさまざまなことをジャッジするのが大好きだ。なぜならジャッジすることは気持ちがいいから」
「ジャッジする気持ちよさに酔いしれた結果 人はその道を踏み外すんだぞ」って。
現代のSNSやネット上で見られる「炎上」現象とも重なる部分がああると思いませんか?人々が善悪を判断し、他者を断罪することで自己正当化を図る。自分が気持ちよくなるためにどこかの誰かを悪だと(悪いと)断じる。身勝手だし、思いやりもないし、欲望一直線の自分勝手な振る舞いに思えます。
このドラマを観て感じたのは、善悪の判断がいかに曖昧で難しいかということです。歴史を学び、過去の誤りを認めることの重要性を改めて考えさせられました。人間は時代背景や経験に基づいて判断を下しますが、その判断が後に間違いとされることも多々あります。だからこそ、過去の過ちを認め、訂正していく柔軟性が求められるのです。
また、私たちは日々の生活の中で多くの判断をしています。その中で、厳しく自己を律することも必要ですが、曖昧さを許容する心の余裕も大切ではないでしょうか。ドラマの中で描かれる善悪の線引きは、私たちの生活にも通じるものがあります。すべてを白黒で決めつけるのではなく、グレーの部分だってあるじゃないですか。その曖昧さは不安定で落ち着かないかもしれませんが、それは間違いを犯すであろう人であれば持っていなければならないものかもしれません。そしてそんな曖昧な中で「自分の納得のいく答え(納得解)」を出すことが大切です。そしてそれは豊かな人生を送る鍵ではないでしょうか。
謙虚さに隠された傲慢さ(傍観者のドラマ)

傍観者のドラマとその巧妙なエネルギー戦略
コントロールドラマの4つ目、「傍観者」のドラマについて解説します。
一見すると傍観者はドラマに関わらない冷めた存在のように見えますが、実際は巧妙なテクニックを駆使してエネルギーを引き出しています。会社の会議や飲み会などで、何となく馴染まず、距離を置いているような人がいるのを想像してください。その人たちは自分のドラマを演じるためにそこにいます。
傍観者の特徴は、自分の意見を明らかにしないことです。会議で意見を求められても「特にありません」と答え、何か言いたげな雰囲気を醸し出しますが、結局いいません。
周囲に自分を神秘的で近づきがたい存在として印象付け、他者の注意を引くのが得意です。なぜそうするかといえば、批判を避けるためであり、距離を取ることで自身を守っています。彼らはトラウマや恐怖心から猜疑心を抱えていますが、自分の意見を持っていても責任を取りたくないために明らかにしません。結果、周囲の人々は「この人は何を考えているのだろう」と気にかけるようになります。これが傍観者の狙いであり、エネルギーを得る手段です。
傍観者は直接的な関与を避けながらも、周囲の注意を引き付け、エネルギーを奪うという巧妙な手法を持っています。自分は関与していないと見せかけながら、他者がエネルギーを向けることで満足感を得るのです。
自分の意見を曖昧にし、責任を取らないことで、相手をイライラさせ、注意を引き続けます。完全に無視されると怒りを感じるため、他者の気を引くことが重要なのです。自分が傍観者のドラマに巻き込まれていると感じたら、その舞台の役者ではなく舞台を降りて演出家にならなければなりません。ドラマに巻き込まれないようにするには客観的な視点に立つことが必要です。
自分の役割を理解し、舞台から降りることで、疲れやストレスを軽減できます。コントロースドラマを分析するための知恵を持ち、それを実践することで、日常生活での不愉快な出来事を減らすことができます。
もし一人での分析が難しい場合は、講座やセミナーに参加して実践的な知識を得るのも一つの方法です。オンラインで提供される講座では、資料を用いて実践的な学びを得ることができます。
このようにして、傍観者のドラマに巻き込まれないための方法を学び、自分の生活をより良いものにしていきましょう。
感情とコントロールドラマ講座を開催
コントロールドラマに関する講座を再開しますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。この知識を持つことで、人間関係がよりスムーズになり、相手の心理を理解する助けとなるでしょう。日常の中でコントロールドラマを意識し、より良い人間関係を築いていきましょう。
皆さんの毎日が少しでも楽しく、心地よく過ごせるように、そして豊かな人間関係を築けるように、お役に立てれば嬉しいです。ご参加、お待ちしております。
感情とコントロールドラマ講座
日時:6月29日(土)11時から13時
開催場所:zoomにて(オンライン開催)
参加費:在処塾生・修了生 7,500円
一般 8,500円
残席 3席
なんでやらなかったのと言われても(尋問者のドラマ)

コントロールドラマ:尋問者のドラマについて
コントロールドラマとは、私たちが子供の頃に親から受けたしつけや役割を通じて身につけた人間関係のパターンです。多くの人が無意識にこれらのドラマを演じています。前回は「脅迫者」と「被害者」のドラマについてお話しましたが、今回は「尋問者」のドラマに焦点を当てます。
「尋問者」と聞くと、刑事ドラマの厳しい取り調べシーンを思い浮かべるかもしれません。しかし、日常生活の中でも私たちはこの「尋問者」の役割を知らず知らずのうちに演じてしまうことがあります。
尋問者のドラマとは
尋問者は、自分の正当性を確立するために、相手の欠点や弱点を見つけ出して攻撃することが特徴です。尋問者は自分が正しいと思い込んでおり、相手を問い詰めることでエネルギーを奪おうとします。この行動は無意識に行われ、結果として相手を弱らせてしまいます。
私が尋問者のドラマを目の当たりにしたのは、子育て真っ最中の頃でした。ある日、電車で私の前に立っていた母親と娘の会話が聞こえてきました。娘さんは宿題を忘れてしまったようで、母親は「どうして宿題をやらなかったの?」と厳しく問い詰めていました。娘は目をうるうるさせ、何も言えずに立っていました。この母親はまさに尋問者の役割を果たしており、娘さんは被害者になっていました。
尋問者は自分が正義だと思い込み、相手の間違いや弱点を攻撃します。例えば、「どうして宿題をやらなかったの?」という質問は、宿題をやらなかったこと自体が悪いと決めつけています。尋問者は相手に自分の誤りを認めさせようとし、その過程で相手を精神的に追い詰めてしまいます。
尋問を受ける側、つまり被害者は自信を失い、エネルギーを奪われます。このような状況が続くと、自分自身に対する信頼が揺らぎ、相手に対する恐怖心が増してしまいます。
エネルギーの循環と自分軸
私たちのエネルギーは、この世界のエネルギーの一部であり、常に循環しています。エネルギーが不足していると感じるときでも、それは一時的なものであり、必ず再び満たされる時が来ます。コントロールドラマを通じて他人からエネルギーを奪おうとするのではなく、このエネルギーの循環を理解し、自分自身を信じることが重要です。
コントロールドラマに巻き込まれないためには、自分軸を持つことが大切です。自分の価値観や信念に基づいて行動し、他人の期待や圧力に流されないようにすることが、健康な人間関係を築く鍵です。
尋問者のドラマは、私たちの日常生活の中で頻繁に見られるものです。しかし、このパターンに気づき、それを変えることは可能です。自分や他人がコントロールドラマを演じていることに気づいたら、冷静に観察し、自分軸を持つことでその舞台に上がらないようにしましょう。
感情とコントロールドラマ講座を開催
コントロールドラマに関する講座を再開しますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。この知識を持つことで、人間関係がよりスムーズになり、相手の心理を理解する助けとなるでしょう。日常の中でコントロールドラマを意識し、より良い人間関係を築いていきましょう。
皆さんの毎日が少しでも楽しく、心地よく過ごせるように、そして豊かな人間関係を築けるように、お役に立てれば嬉しいです。ご参加、お待ちしております。
感情とコントロールドラマ講座
日時:6月29日(土)11時から13時
開催場所:zoomにて(オンライン開催)
残席 3席